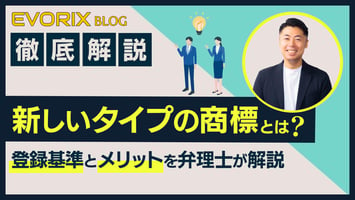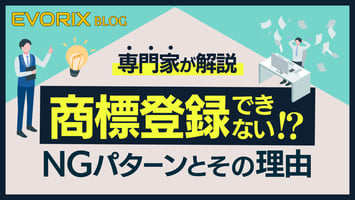...
【弁理士が解説】商標登録できないのはどんな時?新しいタイプの商標の審査基準と不登録事由を徹底解説!

はじめまして。弁理士の杉浦健文と申します。
企業のブランド戦略において、商標登録は非常に重要です。商品やサービスの名前、ロゴなどを商標として登録することで、排他的に使用する権利が得られ、他社による模倣を防ぐことができます。
近年では、従来の文字や図形といった商標だけでなく、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標といった、より多様なタイプの商標も登録できるようになりました。これにより、企業はより多角的なブランド表現を保護することが可能になっています。
しかし、どのような商標でも登録できるわけではありません。商標法には、商標登録が認められない「不登録事由」が定められています。特に新しいタイプの商標については、従来の商標とは異なる特性を持つため、その審査基準も独特です。
本記事では、商標登録の専門家である弁理士の視点から、商標が登録できない主な理由である「不登録事由」について解説します。特に、新しいタイプの商標に焦点を当て、それぞれの類否判断や不登録事由に関する審査基準を掘り下げてご紹介します。
この記事をお読みいただくことで、あなたの考えた商標が登録できるかどうかのヒントが得られ、商標登録出願に向けた準備に役立てていただければ幸いです。
不登録事由とは?なぜ商標登録できないケースがあるのか
商標登録出願が審査される際には、その商標が商標法に定められた「不登録事由」に該当しないかどうかが厳しくチェックされます。不登録事由に該当すると判断された場合、残念ながら商標登録は認められません。
不登録事由は多岐にわたりますが、中でも特に重要な基準の一つが、「他の登録商標との類否判断」です。これは、出願された商標が、既に登録されている他社の商標と似ていないか、消費者が商品やサービスを見たときに混同する恐れがないかを判断するものです。
商標の類否判断においては、商標の外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味合い)などを総合的に考慮しますが、新しいタイプの商標では、その特性に応じて考慮すべき要素や判断の基準が異なります。
次からは、新しいタイプの商標ごとに、その類否判断の基準と関連する不登録事由を見ていきましょう。
動き商標の審査基準と不登録事由
動き商標は、標章(文字、図形など)と、その標章が時間の経過に伴って変化する状態とを組み合わせて構成される商標です。アニメーションロゴなどがこれに該当します。
動き商標の類否判断
動き商標の類否判断は、標章を構成する要素と、その標章が時間経過に伴い変化する状態とを総合して、商標全体として考察しなければならないとされています。ホログラム商標や位置商標と同様に、表彰と変化する状態の全体を一つとして観察する考え方です。
原則として、動き商標を構成する要素のうち、動き(変化する状態)の部分については、独立した商品・役務の識別標識としての機能を果たし、要部(商標の重要な部分)として抽出することはないとされています。基本的に、標章の部分について類否判断を行うことになります。
例えば、識別機能が認められる非類似の標章が、同一または類似の同じように変化するが、変化の軌跡が残らないような動き商標同士は、原則として類似しないものとされます。標章自体が全く一致していないため、商標全体としても類似しないという判断になります。
ただし、例外的なケースもあります。標章の変化する状態が軌跡として画面等に表示されることで、文字等が商品・役務の識別機能が認められる標章を形成する場合です。この場合、軌跡として残った部分も標章として判断することになります。
このような、軌跡が残って形成された標章と、同一または類似の標章からなる動き商標は、原則として類似するものとされます。この場合は、動きの部分が軌跡として残った部分について、類似するかどうかを判断し、それが類似していれば、動き商標全体として類似すると判断されるのです。
動き商標と、図形商標や文字商標との類否についても基準が示されています。
標章の変化の状態が軌跡として表示されることで、文字等が商品・役務の識別機能が認められる標章を形成する動き商標と、その軌跡により形成される標章と同一または類似の標章からなる文字商標等は、原則として類似するものとされます。動き商標が動いて変化した状態が軌跡として残った場合、その部分も商標の一部と考え、それと類似する文字商標等があれば、動き商標全体としてその文字商標等と類似すると判断されるわけです。
文字や図形等で商品・役務の識別機能が認められる標章が変化する動き商標と、その標章と同一または類似の標章のみからなる図形商標とは、原則として類似するものとされます。これは、移動する標章自体に識別力がある場合です。この場合、まず標章について類否判断を行い、それと同一または類似の図形商標等があれば、動き商標全体としてその図形商標等と類似するという判断になります。
また、このような識別力のある標章が変化する状態(動き)が標章として要部抽出される場合、それに同一または類似の動き商標があれば、商標全体として類似するという基準も示されています。
このように、動き商標の類否判断は、標章自体の識別力の有無や、動きが軌跡として残るかどうかによって判断のポイントが異なります。
動き商標の不登録事由
動き商標に特有の不登録事由については、他の新しいタイプの商標(色彩のみ、音)と同様に、商品等の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(4条1項18号)や、商品等の機能確保のために不可欠な形状のみからなる商標などの一般的な不登録事由の適用も考えられます。例えば、商品の取扱説明などで商品の動作を示すアニメーションが、商品の機能を示すものとして判断される場合などです。この点は、個別のケースごとに判断が必要となります。
ホログラム商標の審査基準と不登録事由
ホログラム商標は、標章(文字、図形など)と、ホログラフィーその他の技術により視覚効果として変化する状態とを組み合わせて構成される商標です。見る角度によって絵柄が変わるようなものがこれに該当します。
ホログラム商標の類否判断
ホログラム商標の類否判断も、文字や図形等の標章と、それがホログラフィーその他の技術による視覚効果により変化する状態とを総合して、商標全体として考察しなければならないとされています。動き商標と同様に、標章と変化の状態を全体として観察します。
ただし、変化する部分については、立体的に描画される効果や、光の反射により輝いて見える効果など、文字や図形等の標章を単に装飾する効果が施されているホログラム商標については、表示面に表された文字や図形等の標章から生じる外観、称呼、観念を要部として抽出して類否判断を行うとされています。つまり、装飾的な変化部分は原則として要部としない、ということです。
少し特殊なケースとして、見る角度により複数の表示面が見える効果が施され、複数の表示面から構成されているホログラム商標の類否判断が挙げられます。この場合は、個々の表示面に表された文字や図形等から生じる外観、称呼、観念を判断の元としつつ、その表示面が商標全体に占める割合、表示される文脈、他の表示面の標章との関連性などを総合して、商標全体として考察しなければならないとされています。これは、各表示面ごとに判断するか、それとも複数の表示面を一つの標章として判断するかを、他の表示面との関連性から判断するという基準に基づいています。
この基準に基づき、例えば「MOUNTAIN」という一つの単語が、見る角度によって「MOUN」と「TAIN」のように分割されて表示されるような場合、もともとは一つの単語であることが明らかなときは、分割された一部からなる文字商標と、一つの表示面の標章と同一または類似の標章からなる文字商標等とは、原則として類似しないものとされます。これは、ホログラム商標については全体を一つとして観察するという考え方に基づいているためです。このような場合、「MOUNTAIN」という単語全体と類似するかどうかで判断することになります。
一方、特段の意味を有しない記号や文字等の標章が複数の表示面にそれぞれ表され、各表示面の標章の商標全体に占める割合が低く、複数の表示面の標章をまとめて観察することが不自然な場合(例えば、見る角度によって「H」「B」「G」という関連性のない文字が個別に表示されるようなケース)、このような場合は、各表示面に表示された標章と同一または類似の商標(文字商標や図形商標等)とは、原則として類似するものとされます。これは、関連性のない文字が分割表示されているため、各表示面ごとに類否判断を行うという考え方に基づいています。そのため、「H」「B」「G」のいずれかに類似または同一の文字商標があれば、そのホログラム商標全体が類似すると判断されることになります。
ホログラム商標の不登録事由
ホログラム商標に特有の不登録事由についても、ホログラムによる視覚効果が商品の機能確保のために不可欠な場合などには、他の新しいタイプの商標と同様に不登録事由(4条1項18号など)に該当する可能性があります。
色彩のみからなる商標の審査基準と不登録事由
色彩のみからなる商標は、単色または複数の色彩の組合せのみで構成され、その色彩自体が商品・役務の識別標識として機能する商標です。例えば、コンビニエンスストアの看板の色や、商品のパッケージの色などがこれに該当します。
色彩のみからなる商標の類否判断
色彩のみからなる商標の類否判断は、当該色彩が有する色相(色の種類)、彩度(鮮やかさ)、明度(明るさ)を総合して、商標全体として考察しなければならないとされています。色彩のみで構成される商標の場合、色彩自体が表彰となるため、従来の商標よりも色彩についてより詳細に観察する必要があります。特に、色相、彩度、明度の三要素が観察上重要になるとされています。
複数の色彩を組み合わせた商標の場合は、上記の要素に加え、色彩の組み合わせにより構成される全体の外観を総合して考察します。これは、従来の結合商標の類否判断の基準に準じた考え方です。
色彩のみからなる商標と、他のタイプの商標との類否についても基準が示されています。
まず、単色の色彩のみからなる商標と、他の単色の色彩のみからなる商標との類否です。単色の色彩のみからなる商標は、単一の色そのものが商標全体として観察されるため、たとえそれと同一の単色商標があったとしても、原則として類似しないものとされます。これは、単色のみの場合、色彩自体が識別力を持ちにくいためと考えられます。
次に、単色の色彩のみからなる商標と、文字と色彩の結合商標との類否です。単色の色彩のみからなる商標は、その使用方法が複数考えられるため、原則として文字と色彩の結合商標とは類似しないものとされます。結合商標の場合は、文字部分が要部となることが多いため、色彩のみの商標とは異なると考えられます。
さらに、単色の色彩のみからなる商標と、文字商標等との類否についてです。文字商標との類否判断において、外観、称呼、観念が同一または類似であったとしても、色彩のみからなる商標は主として色彩の外観が重要な判断要素となることから、原則として類似しないものとされます。例えば、赤いリンゴの絵柄(図形商標)と、赤い色のみからなる商標について、観念は「赤いリンゴ」として類似すると言えるかもしれませんが、色彩のみからなる商標では色彩の外観が特に重要視されるため、このような商標間は類似しないという判断になります。
一方、図形と色彩の結合商標の類否判断についても触れられています。図形と色彩を組み合わせた登録商標があり、本願商標が同様の図形と色彩の組み合わせである場合、色彩の配置や割合等が同一または類似であれば、原則として類似するものとされます。これは、色彩のみからなる商標の類否判断とは異なり、図形商標を基にした判断となります。例えば、黄色と青色を特定の配置で組み合わせた図形と色彩の結合商標があり、本願商標も同様の組み合わせであれば、原則として類似と判断されるということです。
ただし、図形と色彩を組み合わせた登録商標に対して、本願商標が色彩のみからなる商標であるようなケースの場合、色彩の組み合わせ商標はその使用態様が図形商標の使用態様と必ずしも一致するわけではないため、個別の判断で類似するかどうかが判断されることになります。
色彩のみからなる商標の不登録事由
色彩のみからなる商標については、商標法4条1項1号(国旗等)および18号(商品等の特徴表示、機能確保)についても基準が定められています。
まず、4条1項1号についてです。色彩のみからなる商標のうち、単色の色彩のみからなるものが、国旗(外国のものを含む)の色彩と同一または類似の著名な標章である場合は、原則として同号に該当するものとされます。色彩のみからなる商標が保護対象となったことに伴い、国旗の色に関する基準が追加されました。
次に、4条1項18号についてです。この条項は、商品等が当然に備える特徴のみからなる商標は登録できないとしています。色彩のみからなる商標がこの条項に該当するかどうかの判断基準として、以下の点が挙げられています。
- 当該色彩のみからなる商標が、商品等から自然発生する色彩のみからなるものであること。
- 当該色彩のみからなる商標が、商品等の機能確保のために不可欠な色彩のみからなるものであること。
したがって、商品そのものの色として自然に生じる色や、商品やパッケージの機能(例えば、高温注意を示す赤色、冷却が必要なものを示す青色など)のために不可欠な色は、原則として商標登録が認められないことになります。
音商標の審査基準と不登録事由
音商標は、メロディー、スローガンを付したCMソング、効果音などが該当し、音自体が商品・役務の識別標識として機能する商標です。
音商標の類否判断
音商標の類否判断は、商標を構成する音の要素(音楽的要素)および言語的要素(歌詞など)、並びに現実に適用される状況などを総合して、商標全体として考察しなければならないとされています。音商標は、音の要素と言語的要素の二つの要素からなる場合があるため、結合商標として全体を観察するという考え方です。
音楽的要素のみからなる音商標の類否判断では、商品・役務の識別機能を有しない部分(例えば、単なる背景音など)については、要部として抽出せず、類否判断の比較対象とはしないとされています。識別力がある部分(メロディーなど)のみを要部として抽出するということです。
識別機能を有する部分を要部として抽出し、音商標の類否を判断するにあたっては、少なくともメロディーが同一または類似であることを要件とするとされています。音の要素には、メロディー、リズム、ハーモニー、音色、テンポなど様々な要素がありますが、最も重要なのはメロディーであるため、メロディーの同一性または類似性が最低限必要となるということです。
言語的要素を含む音商標の類否判断は、音の要素と言語的要素のそれぞれが識別力があるかどうかに応じて判断が分かれます。
例えば、音の要素のみに商品・役務の識別機能が認められる場合は、音の要素について類否判断を行います。一方、言語的要素のみに識別機能が認められる場合は、言語的要素について類否判断を行います。
音の要素および言語的要素のいずれにも識別機能が認められる場合は、それぞれの要素の商品・役務の識別機能の強弱を考慮して類否判断を行います。具体的には、例えば音楽的要素については著名性がなく識別機能が弱く、言語的要素については著名性があり識別機能が強い場合などには、言語的要素のみが要部として抽出される場合があります。
このように言語的要素が要部として抽出される場合、言語的要素を構成する文字の文字商標との類否判断を行います。例えば、音商標の言語的要素が「JTO」である場合に、文字商標として「JTO」というものがあれば、両者は類似すると判断されることになります。
音商標の不登録事由
音商標についても、商標法4条1項9号(公序良俗違反)および18号(商品等の特徴表示、機能確保)に関する基準が追加されています。
4条1項9号(公序良俗違反)についてです。音商標が、例えば以下のような場合は、公序良俗違反に該当する可能性があります。
- 音自体が、国家または外国の国歌を想起させる場合。
- 音商標が、周知の緊急車両のサイレン等、特定の音である場合。
国歌や緊急車両のサイレンなど、特定の公共性や周知性の高い音は、原則として商標登録が認められないということです。
4条1項18号については、色彩のみからなる商標と同様に適用されます。商品等から自然発生する音や、商品等の機能確保のために不可欠な音については、不登録事由に該当するものとされています。例えば、電子機器の起動音や、自動車のエンジン音など、商品の機能に不可欠な音は、原則として登録できません。
位置商標の審査基準と不登録事由
位置商標は、文字、図形等の標章と、その標章を付する商品や役務を提供される場所における特定の位置とを組み合わせて構成される商標です。例えば、バッグの特定の位置に付されたタグや、衣類の特定の位置に縫い付けられたラベルなどがこれに該当します。
位置商標の類否判断
位置商標の類否判断は、文字や図形等の標章と、その標章を付する位置とを総合して、商標全体として考察しなければならないとされています。動き商標やホログラム商標と同様に、位置商標も特定の態様で使用されることを前提としており、標章部分とその位置である特定の態様を全体として観察するという考え方です。
ただし、原則として、位置(標章を付する場所)自体については、独立した商品・役務の識別標識としての機能を果たし、要部として抽出することはないとされています。あくまでも、標章部分について類否判断を行うことが基本となります。
この原則には、標章部分に識別力がある場合とない場合で、判断の仕方が異なります。
標章に識別力がない場合についてです。商品等に付された標章に商品等との関連で識別機能が認められない場合(例えば、単なる飾りや模様と見なされるような標章)、類否判断は、商品等に付される位置等によって、需要者および取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察しなければならないとされています。
例えば、動物のぬいぐるみ(商品)について、動物の耳に赤いタグが付されているという位置商標の例が挙げられています。この赤いタグ自体には識別力がない場合、赤いタグという標章と、それが動物のぬいぐるみの耳に付けられているという位置を全体として観察して類否判断を行います。したがって、ウサギの耳に赤いタグ、クマの耳に少し形の違う赤いタグ、ゾウの耳にアップルの形をした形の異なる赤いタグが付いている場合、これらは全体として類似した印象を与えるため、これらの商標は類似すると判断されることになります。
また、位置商標と図形商標等との類否についても、標章に識別力がない場合は、位置商標を構成する要素が要部として抽出されないため、上記と同様に標章と位置を全体として観察して類否判断を行います。
次に、標章に識別力がある場合についてです。
まず、位置商標同士の類否についてです。標章が同一または類似であれば、その標章を付する位置が異なっていても、原則として商標全体として類似するものとされます。これは、識別力のある標章部分が要部として重視されるためです。例えば、卓球ラケットの特定の場所に「JPO」という文字が付されている場合、この「JPO」という文字部分には識別力が認められるため、たとえラケット上の付される位置が異なる場合でも、商標全体として類似と判断されることになります。
次に、位置商標と図形商標等との類否についてです。位置商標を構成する標章が要部として抽出される場合は、その標章が同一または類似の図形商標等とは、原則として商標全体として類似するものとされます。例えば、位置商標として「JPO」という文字を特定の場所(例えば、パッケージの右下)に付した場合、この「JPO」という文字部分が要部として抽出されることになります。したがって、これと類似する「JPO」という文字商標があれば、位置商標全体としてその文字商標と類似すると判断されることになります。
このように、位置商標の類否判断は、付されている標章自体に識別力があるかどうかが重要なポイントとなります。識別力のある標章が付されている場合は、位置が異なっても類似と判断される可能性が高くなります。
位置商標の不登録事由
位置商標に特有の不登録事由についても、他の新しいタイプの商標と同様に、商品等の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章を、当該商品等において普通に使用される位置にのみ付した場合などには、4条1項18号に該当する可能性があります。例えば、衣類のサイズを示すタグを、一般的にサイズタグが付される位置に付した場合などです。また、位置自体が商品の機能確保に不可欠な場合も該当しうるでしょう。
弁理士からのアドバイス:迷ったら専門家へ相談を
ここまで、新しいタイプの商標(動き、ホログラム、色彩のみ、音、位置)の類否判断や不登録事由について、その審査基準を見てきました。
ご覧いただいたように、新しいタイプの商標の審査基準は、従来の文字や図形商標と比べて考慮すべき要素が多く、判断も複雑になるケースがあります。特に、自社の商標が他の登録商標と類似するかどうかの判断や、不登録事由に該当しないかどうかの判断は、専門的な知識と経験が必要です。
「この商標、登録できるのかな?」 「考えた商標が、どの不登録事由に引っかかるか心配…」
このように感じたら、ぜひ商標の専門家である弁理士にご相談ください。
弁理士は、最新の審査基準や過去の審決例などを踏まえ、あなたの考えた商標が登録できる可能性を的確に判断することができます。また、不登録事由に該当するリスクを回避するためのアドバイスや、より登録可能性の高い商標にするための工夫、出願戦略の提案なども行うことができます。
せっかく時間や費用をかけて出願しても、登録が認められなければ意味がありません。出願前に弁理士に相談することで、無駄な手続きを避け、スムーズな商標権の取得を目指すことができます。
当事務所では、新しいタイプの商標を含む、様々な商標の出願相談を承っております。まずは、お気軽にご相談ください。
まとめ
本記事では、商標登録が認められない「不登録事由」の基本的な考え方と、特に新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標)の類否判断および不登録事由に関する審査基準について解説しました。
新しいタイプの商標は、企業がブランドイメージを多様に表現するための強力なツールとなり得ますが、その登録には独自の基準が存在します。ご自身の商標がこれらの基準を満たすかどうか、不登録事由に該当しないかどうかを確認することが、円滑な商標登録への第一歩です。
商標は、あなたのビジネスにとって大切な資産です。適切に保護するためにも、ぜひ専門家である弁理士の力を活用してください。
当事務所へのご相談は、以下の連絡先までお気軽にどうぞ。
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)