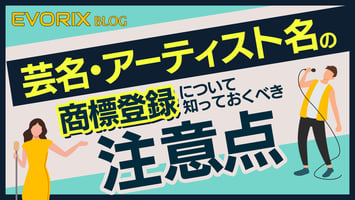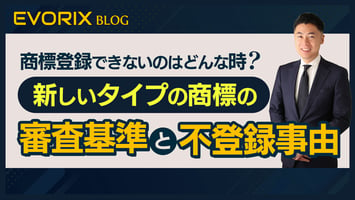芸名・アーティスト名の商標登録について知っておくべき注意点...
アメリカの商標制度概要
1. 商標登録の流れ(出願から登録まで)
-
出願(申請): 商標の図案や名称、使用する商品・サービスなどを定めて、米国特許商標庁(USPTO)に出願します。出願時には、実際に商標を使用しているか、将来使用する意図があるかといった「出願の基礎」を明示する必要があります(詳細は後述)。
-
審査: 出願後、USPTOの審査官が形式面と実質面の審査を行います。ここでは、(a) 商標に識別力(他人の商品・サービスと区別できる力)があること(例えば商標が普通名称そのものや単なる商品説明になっていないか)や、(b) 既に似た商標が登録されていないか(類似する先行商標との抵触がないか)などがチェックされます。審査は出願から数ヶ月程度で結果が出るのが一般的です。審査で問題が指摘された場合、出願人は通知から6ヶ月以内に応答(補正や反論)する機会があります。
-
公告と異議申立て: 審査を無事に通過すると、商標はUSPTO公報に公開されます。他人がその商標登録に反対する場合、公告日から30日以内に異議申立てを行うことができます。異議申立ての手続は裁判に準じた形式で行われ、当事者間の和解交渉などで解決を図るケースも多いです。異議が出されず期間が経過すれば、登録手続きへ進みます。
-
登録(成立): 公報で異議が出されなかった場合(または異議が解決した場合)、商標が正式に登録されます。USPTOから商標登録証が発行され、登録商標には登録マーク「®」を表示できるようになります(連邦登録商標のみ®マーク使用可)。ただし、出願時に「使用意思(Intent to Use)」に基づいていた場合は、すぐには登録証は発行されません。この場合まずUSPTOから**登録許可通知(Notice of Allowance)が発行され、通知後6ヶ月以内(最大5回の延長申請が可能)に実際の商標使用を証明する書類(使用宣誓書と使用証拠)を提出して初めて正式に登録が認められます。提出期限までに使用証明を行わないと登録は成立しないので注意が必要です。
2. 使用主義・先使用権の特徴
-
使用主義とは: アメリカの商標制度の最大の特徴は「使用主義」で、商標権は実際の使用によって発生します。これは「先に出願した者を優先する」日本の先願主義(登録主義)とは異なり、「先に商標を使用した者に権利を認める」という考え方です。言い換えれば、商標を登録していなくても先にその商標をビジネスで使用していれば、その使用している地域において一定の権利(先使用権)が認められます。これをアメリカではコモンロー上の商標権とも呼び、例えばまだ登録されていなくても地道に使い続けて知名度を得た商標は、その地域で保護され得るのです。
-
先使用権と連邦登録のメリット: 未登録でも先使用により権利が発生しますが、その権利範囲は実際に使っている地域や商品分野に限定されます。ビジネスが成長すれば他地域にも展開したくなるでしょう。その際、全国的な独占権を主張するには連邦商標登録を取得する必要があります。連邦登録をすれば、出願日以降は合衆国全土でその商標を使用していたものとみなされるなど法的なメリットが生じ、登録していない場合と比べて第三者に対する権利主張が有利になります。例えば連邦登録により (1) 登録商標の使用権を米国全域で主張でき第三者の無断使用を牽制できる、(2) 税関登録を通じて模倣品の輸入差止め請求ができる、(3) ®マークを付してブランド価値を示せる、(4) 5年間継続使用すると登録の不可争性(以後、権利の有効性を第三者が争えなくなる地位)を得られる、といった利点があります。要するに、アメリカでは単に先に使っているだけで満足せず、全国規模で権利を安定させるため登録する意義が大きいと言えます。
3. 登録要件(識別力、使用証明など)
-
識別力と拒絶理由: アメリカで商標登録するには、その商標が他人の提供する商品・サービスときちんと区別できること(識別力)が求められます。例えば一般的な商品名そのもの(普通名称)や商品の性質を直接表すだけの語(記述的標章)などは識別力がなく、登録できません。また、公序良俗に反する標章や他人の有名人名を無断で含むものなど法律で定められた不登録事由に該当する商標も登録不可です。さらに先に類似商標が登録されている場合も、出所の混同を避けるため原則登録は認められません。USPTO審査官はこれら絶対的・相対的な拒絶理由について審査し、問題がある場合は拒絶通知が出されます。
-
使用の証明(使用宣誓書と使用証拠): 米国商標は実際に商取引で使用していることが登録の重要な条件です。出願時にすでに米国内で使用している場合はその使用開始日を申告し、使用を証明する写真などの使用証拠を提出する必要があります。一方、まだ使用していない場合は「誠実に使用する意思」があることを宣誓して出願できますが、この場合でも審査通過後、登録前に必ず商標を使用開始しなければなりません。具体的には、先述のとおり登録許可後に使用証拠を提出して初めて正式登録となります。また、外国(日本など)での登録に基づいて米国出願するルートもありますが、この場合でも登録後5~6年目および更新時には結局、商標を使っている証拠の提出が必要となります。以上のように、米国では**「使っていない商標は権利として維持させない」**運用がなされており、これは使用主義ならではの特徴です。
4. 管轄機関(USPTOなど)
-
連邦レベルの管轄: アメリカ合衆国では**米国特許商標庁(USPTO)**が商標登録業務を所管しています。USPTOは商務省管轄の政府機関で、特許と商標の権利付与を担当しています。米国で商標の連邦登録を行う場合、USPTOに対して出願を行い、同庁の審査・登録手続を経ることになります。
-
州レベルの管轄: アメリカには連邦登録とは別に各州ごとの商標登録制度も存在します。州登録を行う場合、その州政府(通常は州務長官の事務所)に商標出願し、州法に基づく審査・登録が行われます。ただし州登録で得られる権利は当該州内のみ有効で、全国的な効力はありません(州登録と連邦登録の詳細な違いは後述)。一般に全米規模で事業を行う場合は連邦登録が利用され、州登録は地域限定のビジネス向けと言えます。
5. 登録後の更新・維持義務
-
存続期間と更新: アメリカの連邦商標権の有効期間は登録日から10年間です。10年ごとに更新手続きを行えば、費用を支払い続ける限り何度でも権利を延長(更新)することができます。したがって、理論上は商標権は半永久的に存続させることも可能です。
-
5~6年目の使用宣誓: 権利を維持するためには、登録後5~6年目(登録日から数えて5年経過後から6年経過前まで)の間に、USPTOに対して**使用宣誓書(Declaration of Use)を提出する必要があります。これは「登録後も商標をきちんと使っています」という宣誓であり、併せて現在商標を使用中であることを示す使用証拠(例:商標を付した商品の写真や広告画像)も提出します。この手続きを怠ると、USPTOはその商標登録を失効(取消)**させてしまいます。つまり、登録だけして放置されている商標はここで整理される仕組みです。
-
10年ごとの更新時の義務: 上記の中間メンテナンスに加え、10年ごとの更新申請時にも商標の使用状況を証明する宣誓書と使用証拠の提出が義務付けられています。更新時においても、指定商品・サービスについて実際に商標を使用していない場合は、その商品・サービスについて登録を維持することはできません。このように米国では商標を使い続けていることが権利維持の前提となっており、使っていない権利は更新できずに抹消されます。
6. 不使用取消・無効審判制度
-
不使用による取消(使用の義務): アメリカでは商標を一定期間使わないと権利が取り消される可能性があります。具体的には、連続して3年間商標を使用しないと、その商標は「商取引で使用する意思なく放棄された(abandoned)」ものと法律上推定されます。第三者はUSPTOの審判部(商標審判廷)に不使用取消の申立てを行うことができ、正当な使用がなければ登録は取り消され得ます。商標の「使用」には通常、真剣な営業目的での使用であることが必要とされ、権利維持のためだけに形だけ行う使用は認められません。この厳格な運用により、市場で使われていない商標が独占権として温存されるのを防いでいます。
-
無効審判(登録の取消し): 登録された商標であっても、登録時に問題があった場合には無効(取消)を求める制度があります。例えば「本来は識別力が無い記述的な商標が誤って登録されてしまった」「他社の商標に酷似しており本来登録されるべきでなかった」といった場合、利害関係人は登録無効の申立て(日本でいう無効審判に相当)を起こすことができます。米国ではこれらの争いは主にUSPTO内の商標審判部(Trademark Trial and Appeal Board)や連邦裁判所で扱われ、審理の結果、登録が取り消されることもあります。また、悪意の出願や詐欺的な使用証明による登録は発覚すれば無効・取消しの対象です。なお、登録から5年以上経過した商標は法律上不可争性を得て、記述的であることなど一部の理由を除き無効主張ができなくなる仕組みもあります(長期間問題なく使用され市場に定着した商標を保護するため)。
7. 州登録と連邦登録の違い
-
連邦商標登録(Federal Registration): アメリカ合衆国連邦法(通称ランハム法)に基づく商標登録制度です。州際取引(州と州をまたぐ取引)や国際取引で使用する商標が登録対象となり、登録された商標権の効力はアメリカ全土に及びます。出願・審査はUSPTOで行われ、登録された商標には®マークを付して登録商標であることを表示できます。全国的に事業展開する企業は通常この連邦登録を利用します。
-
州商標登録(State Registration): アメリカ各州の法律に基づく商標登録制度です。州内のみの商取引(intrastate commerce)で使用する商標が対象で、その商標権の効力も当該州内に限定されます。例えばビジネスが一つの州の中だけで完結している場合には連邦登録は利用できず、州登録によって商標保護を図ることになります。しかし現代では流通が広域化し州内だけで完結するケースは少ないため、実務上、州登録が活用される場面は限定的です。なお州登録では®マークは使用できず、未登録商標と同様に™マークなどで表示するにとどまります(®は連邦登録商標のみ使用可)。
-
その他の違い: 手続面では、連邦登録は審査に時間と費用がかかる一方、州登録は比較的迅速かつ安価ですが得られる権利の範囲が狭いという違いもあります。また、連邦登録商標に対する侵害訴訟は連邦裁判所で提起できますが、州登録のみの場合は基本的に州法に基づく救済となります。もっとも上述のように連邦登録の方が広範なメリットがあるため、全米展開を志向する企業はまず連邦商標の取得を目指すのが通常です。
8. 他国との制度比較(日本・EUとの主な違い)
-
日本(先願主義・登録主義)との違い: 日本の商標制度では、商標は登録によって初めて権利が発生します。出願時点でその商標を実際に使用している必要はなく、将来的に使用する意思があれば現時点で未使用でも登録が認められます。これは「使う予定は未定だが先に権利だけ押さえておく」ということも可能な仕組みです。一方、アメリカは前述の通り使用を重視し、使用していない商標は原則として登録も維持もできません。日本でも登録後3年間不使用の商標は取り消し得る制度がありますが、登録時に使用証明を要求されることはなく、更新時にも米国のような使用宣誓は不要です。要するに、日本は「早い者勝ち」で権利取得できるのに対し、米国は「使った者勝ち」であり、使っていなければ権利が成立しない点が大きな相違点です。
-
欧州連合(EU)との違い: EUも日本と同様に先願主義(最も早く出願した者に権利を与える制度)を採用しています。欧州連合知的財産庁(EUIPO)に出願して登録を受ければ、単一の「EU商標」としてEU加盟全域で効力を持つ商標権が得られます。出願時や更新時に商標の使用状況を証明する必要はなく、登録後5年が経過するまでは不使用を理由に取り消されることもありません(5年以上連続して未使用の場合、第三者により権利剥奪の請求が可能)※。したがってEUも基本は登録主義であり、米国のように登録前から使用していることを要求される場面はありません。ただし、一度EU商標を登録すれば加盟国すべてで一括保護される反面、どこか一国ででも拒絶理由(例えば類似商標の存在)があればEU全体で登録拒絶となるなどの違いもあります。総じて、米国は「使用の有無」を非常に重視するのに対し、日本やEUは「出願の早さ」を重視する制度であると言えます。
参考: 上記は一般的な概要であり、国ごとに細かな例外や手続の違いがあります。実際の商標出願にあたっては各国の最新制度や要件を専門家と確認することをお勧めします。
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)