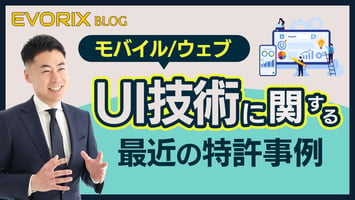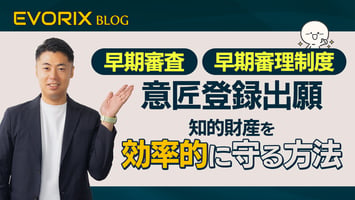...
ドイツの意匠制度概要
意匠権の保護対象と定義
ドイツ・EUにおける意匠の定義: ドイツ意匠法(Designgesetz)において「意匠」とは「製品(工業的または手工業的に製造された物品)の全体または一部の外観」を指し、その外観は線や輪郭、色彩、形状、素材、模様など視覚的特徴により構成されます。つまり製品の具体的な形状・模様・色彩の組み合わせが保護対象であり、抽象的なアイデアやコンセプトそのものは保護されません。工業製品のみならず手工芸品、包装、グラフィカルなシンボル(アイコン等の図形)やタイポグラフィ(書体)も「製品」に含まれます。さらに製品の一部分も意匠として登録可能で、例として靴の靴底やペンのキャップ部分のみを独立した意匠として保護することができます。建築物の外観デザインも物品の一種として保護対象に含まれると解されています(EUの定義上「建築物」も工業的製品とみなされる)。他方、**純粋に機能にのみ左右される形状(機能上他の形状を取り得ないもの)**や、国家の紋章・旗など公序良俗に反するデザインは登録が認められません。
日本における意匠の定義: 日本の意匠法でも同様に物品の形状・模様・色彩(または結合)であって視覚を通じて美感を起こさせるものが保護対象です(意匠法2条)。日本では2020年の法改正で保護対象が拡張され、従来の「物品」(その部分を含む)に加え、新たに「建築物」(その部分を含む)および「画像」が含まれるようになりました。ここでいう「画像」とは、電子機器の操作画面やその機能によって表示される画面デザイン(GUIなど)を指し、従来は物品に附随する形でしか保護できなかったグラフィカルユーザインタフェース等を、単独の意匠として保護可能としています。さらに日本独自のカテゴリとして**「内装の意匠」**も追加されました。これは店舗や室内空間の統一的なデザイン(家具の配置や内装全体の美感)を一つの意匠として保護する制度です。一方で、日本意匠法も公序良俗に反する意匠や他人の著作物・他人肖像等を含む意匠は登録不可としています(意匠法5条各号)。
要約すると、ドイツ・EU・日本ともに「物品等の具体的なデザイン」を保護しており、部分的デザイン(部分意匠)の保護も可能です。ただし日本では画像や内装など独自に細かくカテゴリー分けがなされている点が特徴です。また保護対象はあくまで「視覚を通じて得られる美感」に限られるため、極めて純粋に機能のみで決まる形状は意匠とは認められない点は共通しています。
出願要件と手続(必要書類・言語・図面など)
ドイツにおける出願要件: ドイツの意匠出願はドイツ特許商標庁(DPMA)で行います。基本的な必要書類は、(1)出願人の情報を記載した願書(書式R5703、独語)、(2)意匠を表した図面または写真(形式要件を満たす画像ファイル。電子出願ではJPEG形式、紙出願では所定の用紙に貼付)最大10点まで、(3)意匠が使用される製品の名称(品目の表示。あらかじめ定められた語彙リストから該当する名称を記載)です。出願言語はドイツ語が原則で、書類も独語のフォーマットを用います。日本から直接出願する場合、ドイツに居所や営業所を持たないため現地代理人(弁理士または弁護士)の選任が必要です。電子出願(DPMAdirektWeb/Pro)が推奨されており、オンラインなら最大20意匠までの出願に対応しています。紙出願の場合は最大100意匠を一括出願でき(複数意匠一括出願制度、後述)、その際は追加のシート(R5703.2)に各意匠の情報を記載します。
図面・画像の要件(ドイツ/EU): 提出する意匠の図面・写真には厳格な形式要件があります。1画像には1視点から見た意匠のみを描き、複数のバリエーションを1枚の図にまとめてはいけません。また意匠以外の余計な物(背景の他の物品や説明用の番号・文字等)を映り込ませないよう、無地で中立的な背景上に意匠のみを示す必要があります。画像は最低300dpi・355x355ピクセル以上の解像度が求められ、1ファイル2MB以内に抑える必要があります。図面は写真実物でもCGでも構いませんが、出願時に提出した図に写っていない部分は保護を受けられないため、保護したい特徴が明確にわかるよう複数角度から十分な図面を用意することが重要です。例えば立体物なら主要な六面図や斜視図を含め、必要に応じ最大10図面まで提出できます。色彩も図面で示された通りに保護範囲に影響します(白黒図面の場合は色彩については請求しないものと解されます)。
日本における出願要件: 日本では特許庁への意匠出願時、必要書類は(1)願書(日本語)と(2)図面等です。願書には出願人情報、意匠の名称(物品名または建築物・画像の用途等)、創作者情報などを記載します。日本語での提出が原則であり、図面の説明や意匠の説明(必要なら)も日本語で記載します。図面については通常、物品の六面図(正面・背面・左右側面・上面・下面)および必要に応じて斜視図など、意匠の全貌が分かる一連の図を提出します。日本では一出願一意匠が原則で、複数意匠を一括出願する制度はありません(後述の関連意匠制度は別個の出願として扱われます)。ゆえに意匠ごとに願書と図面一式を個別に用意する必要があります。また、日本出願では願書に「意匠に係る物品または画像等の名称」を記載しますが、この名称はできるだけ既存の意匠分類や慣用語に沿った簡潔なものが求められます(不適切な名称だと補正を指示されることがあります)。図面要件もドイツと同様に他の物品や文字を含めない明瞭な図である必要があり、部分意匠の場合には破線等で非請求部分を示すことが許容されています。なお、日本では図面に代えて写真やCGも認められていますが、審査実務上は線画の方が形状の把握が容易なため望ましいとされています。
出願言語・電子出願: 日本への意匠出願は基本日本語で行い、外国語で提出した場合は日本語訳の提出を要します。一方、欧州共同意匠(RCD)をEUIPOへ直接出願する場合、英語などEU言語を使用できます(日本企業は通常英語で出願)。ドイツ国内意匠は前述の通りドイツ語が原則です。ただしハーグ国際出願(後述)を利用する場合、一括して英語やフランス語で出願しドイツや日本を指定することも可能です。
費用面: ドイツ意匠の出願料は1出願あたり電子申請で60ユーロ(紙なら70ユーロ)と比較的安価で、これは1件の意匠を含む場合の基本料です(複数意匠一括出願時は意匠の件数に応じ追加費用)。日本の意匠出願料は16,000円(電子出願の場合)と定められています(2023年時点)※。また、日本は登録時に登録料(初年度~3年度分の一括納付等)が必要ですが、ドイツでは出願料に初期5年分の保護が含まれる形です(更新は後述)。
新規性・創作性・独自性などの保護要件
意匠権を取得するためには、意匠の内容が法律上の保護要件を満たす必要があります。主要な要件は新規性と**独自性(創作性)**です。
ドイツ・EUにおける保護要件: ドイツ意匠法第2条に基づき、登録される意匠は**「新規」であり「個性(インディビジュアルキャラクター)を有すること」が求められます。新規性とは、その意匠と同一またはごく細部を除き実質的に同一のデザインが出願前に公衆に開示されていないことを意味します。ここでいう公開には、製品の市場提供、展示会出品、Web掲載など一般に入手可能な形での公表が含まれます。ただし例外として新規性のグレースピリオド(猶予期間)が設けられており、出願前12ヶ月以内に創作者本人(または権利承継人)が自ら公表した意匠**であれば、それによって新規性が喪失したとはみなされません。これは「市場の反応を見てから出願するための1年猶予」を与える趣旨の規定です。なお第三者による無断公開について明示的な猶予はありませんが、秘密保持義務下での開示(社内開発や取引先との秘密デモ等)は公衆への開示に当たらないと解されています。
「個性」(Individual Character)とは、当該意匠の全体的印象が、出願前に公知となっている他の意匠とは異なることを指します。判断は当該分野の知識を持つ**「熟練した利用者 (informed user)」**の目を通じて行われ、細部ではなく意匠全体から受ける印象の違いに基づきます。デザインの創作自由度も考慮され、既存類似デザインが多数存在しうる分野(例えば車輪のホイールリムなど)では小さな差異でも個性が認められる場合があります。逆に、自由度が高い分野ではより顕著な差異が求められます。高度な芸術性や奇抜さ自体は要求されず、あくまで既存デザインとの差異に着目した要件です。
ドイツ(EU)では上記新規性・個性の要件について、庁による実体審査は行いません。新規性・個性を欠くデザインであっても一旦登録はされますが、後述のように無効審判や侵害訴訟の場面でこれら要件が改めて審査され、満たさない場合は登録が無効と判断されます。したがって出願人の自己責任で新規性・個性を満たす意匠のみを出願することが重要です。
日本における保護要件: 日本も基本は新規性と創作非容易性(独自性)を要求します。新規性とは公開された先行意匠と同一またはほとんど同じ意匠は登録できないという要件です(意匠法3条1項各号)。日本でも2018年改正以降、新規性喪失の例外期間が6ヶ月から1年に延長されました。これにより、出願前1年以内であれば、創作者や権利者自身による公表(学会発表、展示会出品、SNS公開など)や一定の公式展示会出品については、新規性喪失の例外適用を受けることができます。ただし日本では**出願時に所定の手続(例外適用の申請書と証明書の提出)**が必要です。この点、ドイツ/EUでは手続不要で期間内の自己公表は自動的に猶予適用されるのに対し、日本は形式手続を怠ると猶予が受けられない実務上の注意点があります。
創作非容易性(高度性)とは、平易に言えば「ごくありふれたデザインではないこと」という要件です。意匠法3条2項にて、「その意匠を属する分野の通常の知識を有する者が容易に創作できた意匠」は登録できないと定めています。これは欧州でいう「個性(異なる全体印象)」と似ていますが、日本の場合は類似する先行意匠から容易に考案できるような些細な違いしかない意匠は登録不可という基準です。たとえば色を変えただけ、寸法比を変えただけで美感がほとんど変わらないような意匠は「容易に創作できる」と判断される可能性があります。判断基準は需要者(消費者)の視覚による美感を基準に、先行意匠との差異の要部・全体的印象を比較して総合評価されます。基本的には日本でも「需要者に与える美感が異なるかどうか」を見る点でEUの個性要件と通底しています。ただし日本実務では「容易想到性」の判断には審査基準が細かく定められており、先行デザイン群から当該意匠を構成要素の単純な転用や組み合わせで生み出せるか等を検討します。結果としてEUの「個性」要件と大きく結論が異なるわけではありませんが、日本は審査段階で創作容易かどうか厳格にチェックする(後述)点が実務上の相違となります。
登録までの流れと審査制度
ドイツ(無審査登録主義): ドイツ意匠は形式審査主義(無実体審査)で運用されています。出願後、DPMAにてまず方式要件のチェックが行われ、願書の記載・図面の形式(画像が規定どおりか)・手数料支払いなどに不備がなければ、速やかに登録手続に入ります。審査官は提出図面から判断してそれが意匠の定義に該当するか(単なるアイデアではなく具体的形状を有するか、公共の秩序や善良の風俗に反しないか等)を審査します。例えば図面が抽象すぎる場合や、公序良俗違反のデザイン(猥褻な表現や違法行為を助長する形状等)、国家紋章の模倣などに該当する場合は拒絶されます。しかし新規性・個性の実体要件については審査されず、それらは登録後に問題があれば無効審判や訴訟で争われる事項とされています。このため、出願から登録公告までの期間は非常に短く、願書・図面に問題がなければ2~4週間程度で登録が完了します。もし方式不備があれば補正通知が来ますが、それでも数ヶ月(3~4ヶ月以内)で登録に至るのが通常です。登録されると即日効力が発生し、電子登録原簿(DPMAregister)および意匠公報(Designblatt)で意匠の画像・情報が公開されます。
補足: ドイツでは一件の出願で最大100意匠を含めることができます(ただし実務上、それら意匠は製品の分類が同一である必要があります。EU指令では類似する製品区分に属する複数意匠の一括出願が認められており、ドイツもこれに準じています)。一括出願された複数意匠は登録後もそれぞれ独立した権利として扱われ、更新も個別になります。
日本(実体審査主義): 日本の意匠出願は特許庁の審査官による実体審査を経て登録可否が決まります。出願から数週間程度でまず方式チェックが行われ、願書記載不備や図面不足があれば補正指令が出ます。方式面クリア後、審査官が過去の登録意匠・出願公開公報・製品カタログ等を調査し、その意匠が新規性を有するか、類似の先行意匠から容易に考案できるものでないかを判断します。必要に応じて拒絶理由通知が出され、出願人は意見書や補正(例えば図面の一部削除や限定など)で応答します。それでも要件不備が解消しない場合は拒絶査定となり、要件を満たすと判断されれば登録査定が出ます。登録査定後、所定の登録料(設定登録料)を納付して初めて意匠権が発生します。日本の審査期間は近年迅速化していますが、概ね6ヶ月~1年程度で一次審査結果が通知される傾向です(案件の分野や繁閑により変動)。日本では意匠も審査請求制度はなく、出願すれば自動的に審査されます(特許と異なり請求不要)。
審査で登録となった意匠は意匠公報に図面付きで公開されます。ただし日本には秘密意匠制度があり、希望すれば登録日から最長3年間、公報において意匠の詳細(図面等)を非公開にできる仕組みがあります(その間は出願番号や出願日などの bibliographic data のみ公表)。秘密にした期間中も意匠権は発生しますが、公表されていないため第三者に対する権利行使は制限があります(例えば独立創作に対しては秘密意匠では措置を取れず、模倣であることの立証が必要とされています)。3年の猶予期間終了後または任意のタイミングで意匠を公表すると、以後は通常通り権利行使が可能です。欧州の公開延長(deferment)制度と趣旨は近く、企業が新製品発表のタイミングに合わせて意匠公開を調整する手段となっています。
審査の有無による長所短所: 無審査のドイツ(EU)制度では早期かつ安価に権利化できる反面、新規性が怪しい意匠も一旦登録されるため、権利の安定性は低い(後から無効が認められるリスク)と言えます。一方、日本のような実体審査制度では権利化に時間と費用がかかるものの、登録された意匠は新規性・創作性が担保されている分強い権利として信頼性が高いです。近年、日本でもデザインの保護ニーズに合わせ迅速・安価な登録制度への意見もありましたが、審査付き制度が維持されています。このように出願から登録までの流れは両国で大きく異なり、出願戦略にも影響します(後述の実務ポイント参照)。
意匠権の効力・存続期間・権利行使
権利の発生と存続期間: ドイツ意匠権(登録意匠)は登録日に発生し、最初の保護期間は5年間です。以後、出願日(優先日)から数えて最大25年まで、5年毎に更新料を支払うことで存続期間を延長できます。具体的には5年目ごとに更新手数料を納付し、5年 × 5期=25年まで延長可能です。更新しなければその時点で権利消滅します。ドイツでは複数意匠一括登録の場合でも更新料は意匠ごとに必要です。一方、日本の意匠権も2020年施行の改正後は出願日から最長25年存続します(改正前は登録日から20年)。日本では登録時に設定登録料として最初の数年分(通常1~3年分)を納付し、その後は毎年ごとの年金(特許年金に相当)を支払うことで25年目まで維持します。例えば2025年現在、1~3年目は各8,500円、4年目以降は各16,900円を毎年納付する体系です。25年目まで納付すれば満了し、それ以上の延長制度はありません(意匠権は更新不可)。このように権利の最長期間はドイツ/EU・日本とも同じ25年ですが、年金の支払いサイクル(5年毎 vs 毎年)に違いがあります。
意匠権の効力範囲: 登録された意匠権は専用権であり、権利者だけがその意匠を業として実施(製造、販売、輸出入などの行為)することができます。第三者が無断で意匠を実施すれば意匠権侵害となります。ドイツ(EU)の場合、侵害か否かの基準は**「登録意匠と同一か、または情報を得た利用者(informed user)にとって異なる全体的印象を与えない意匠」であるかにかかっています。言い換えれば、見た目の印象が登録意匠と実質的に同じであれば、細部が多少異なっていても侵害とみなされうるということです。例えば色違いやごく一部の形状変更では、全体印象が変わらなければ侵害と判断されるでしょう。日本でも考え方は近く、意匠権の効力は「登録意匠およびそれに類似する意匠**」に及ぶと法律で規定されています(意匠法23条)。ここで「類似する意匠」とは需要者の目から見て美感を共通にする範囲を指し、物品の用途・機能及び形状などを総合勘案して判断されます。要するに日本でもドイツ/EUでも、第三者が登録意匠とほぼ同じデザインの商品を作れば権利侵害となります。両者の表現の違いとして、EUは「情報を有する利用者にとって異なる印象を与えない」、日本は「需要者の視覚による美感を通じて同一または類似と感じられる」というように述べられますが、実質的な判断基準は近いものです。
もっとも、意匠権の権利行使には注意点もあります。例えばドイツ/EUでは未公開状態(非公開期間中や未登録)の意匠には原則として権利行使できません。前述のようにドイツでは公開を30ヶ月延長中の意匠は「コピー防止」の効力しかなく、独立に創作された同様のデザインには差止請求できません。EU意匠制度でも、後述の未登録意匠の場合はコピー品に対してのみ権利行使可能で、偶然の類似には権利が及びません。日本の秘密意匠も公開前は他人が知らずに同じデザインを作っても権利主張しにくい状況です。
権利行使(侵害対応): 意匠権侵害が発見された場合、権利者は相手に対し差止請求(製造や販売の停止、在庫物の廃棄など)や損害賠償請求を行えます。ドイツでは民事訴訟で侵害差止命令を請求でき、故意・過失があれば損害賠償も認められます。またEU域内共通の意匠権(共同意匠)であれば、EU加盟国全域を効果地域とする差止命令を各国裁判所(加盟国ごとに指定された意匠権侵害管轄裁判所)で取得できます。日本でも意匠権侵害は民事上の差止・賠償の対象であり、悪質な侵害は刑事罰(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金:意匠法69条)も規定されています。もっとも意匠侵害訴訟は専門的判断を要するため、実務ではまず警告書による是正要求→交渉による和解が図られることも多いです。権利者は製品カタログや展示会等で模倣品を発見した際、速やかに法的措置を検討する必要があります。また、国境を越えた模倣品流通に対しては税関での**輸入差止(税関差止)**を申立てることで、水際でコピー商品の流入を防ぐことも有効です(日本・ドイツ共に税関への意匠権登録制度があります)。
総じて、意匠権は強力な独占権ですが、その及ぶ範囲(類似範囲)の解釈は国や制度によって細部が異なります。ドイツ/EUでは「全体的な印象」に重きが置かれ、日本では「物品の用途・形態両面からの類否判断」を行うなどアプローチが違いますが、結論として他人が見て「同じようなデザインだ」と感じるレベルなら侵害となる点は変わりません。
ドイツ国内意匠と欧州共同意匠制度(EUIPO)との関係
ドイツはEU加盟国であるため、デザイン保護にはドイツ国内の意匠権と、EU全域をカバーする欧州連合意匠(旧称:共同体意匠)の二つのルートがあります。それぞれ管轄官庁や効力範囲、手続が異なりますが、相補的に利用できます。
ドイツ国内意匠 (German Design): DPMAで登録され、有効範囲はドイツ連邦共和国国内のみです。保護期間や要件は前述の通りで最長25年、審査なし登録、公開延長可などの特徴があります。ドイツにのみ事業展開する場合や、費用を抑えたい場合に適しています。出願も独語で国内手続となるため、ドイツに代理人を立てる必要があります。しかし登録まで極めて迅速なため、製品発売に合わせ短期間で権利化したい場合にも有用です。
欧州共同意匠 (EU Design: RCD): EU知的財産庁(EUIPO、本部スペイン・アリカンテ)に出願して取得するデザイン権で、EU加盟全国に一括効力を有します。一度の登録でドイツを含むEU27か国すべてをカバーできるのが最大の利点です。手続言語は英語などのEU公用語で、日本企業も利用しやすくなっています。EUIPOでの審査も実質的には無審査登録で、早ければ数日〜数週間で登録が完了します。存続期間や更新も25年まで5年ごとの更新という点でドイツと同じです。費用は初期出願で1意匠あたり350ユーロ程度からで、複数意匠を一括出願すると2件目以降割安になります。なおEUIPOへの一括出願は最大100意匠まで可能ですが、全ての意匠が**同一のロカルノ分類(同種の製品カテゴリ)**に属する必要があります。
未登録意匠制度 (Unregistered Community Design): EUには特色ある制度として未登録共同意匠権(UCD)があります。これはデザインを公表するだけで自動的に発生する3年間限定の権利で、EU域内で新デザインを初公開するとその瞬間からEU全域で効力が認められます。登録手続や費用無しに短期保護が得られるため、流行のファッションや季節商品などライフサイクルが短い製品に活用されています。ただしUCDの効力はコピー品に対する差止に限られ、独立に創作された同様デザインには権利行使できません。また期間も延長不可で3年で消滅します。一方、日本には未登録で発生する意匠権は存在しません。デザイン公開から出願まで猶予期間を過ぎれば権利化は不可能です。そのため欧州では公開→UCD取得→必要なら1年以内に出願という戦略も可能ですが、日本では常に出願前の公開は慎重に扱う必要があります。
ドイツ意匠とEU意匠の選択: ドイツ国内のみの権利は費用面で有利ですが、保護範囲が狭く、他国では効力がありません。EU意匠は広域保護できますが、出願費用・管理費用はやや高くなります。また言語や手続の点で、例えばドイツ語に不慣れな企業が英語で手続できるEUIPOを選ぶケースもあります。実務上は、ドイツを含む複数国で商売するならEU意匠を、ドイツ限定なら国内意匠をといった選択になります。ただ両者は共存可能で、同じデザインを二重にドイツ意匠とEU意匠で登録しておくことも一応は可能です(もっとも費用対効果は薄いでしょう)。なおEU意匠制度は2025年に改正され名称が「欧州連合意匠(EU Design)」に変わりましたが、本質的な制度は従来と変わりません。
国際出願との連携(ハーグ制度等)
海外でデザイン保護を得る方法として、各国ごとに出願する以外にハーグ協定による国際意匠登録制度があります。ドイツ・日本ともハーグ協定の加盟国であり、この制度を活用できます。
ハーグ国際意匠登録制度: ハーグ協定はWIPOが管轄する国際登録制度で、1件の国際出願で最大100意匠、指定可能な国は現在80余り(EU加盟国はまとめて一つの指定として選択可能)を一括出願できます。出願は英語・フランス語(またはスペイン語)で行い、WIPO国際事務局が各指定国官庁への手続きを代行します。出願人は自国官庁を通じて国際出願するか、直接WIPOにオンライン出願します。例えば日本企業がハーグ制度を用いて「EU、米国、中国、韓国」を指定すれば、一度の英語出願でこれら各国の意匠出願として扱われます。各指定国ごとに審査が行われ、拒絶理由がなければ国際公表から6ヶ月〜数年以内に保護が認められます。ドイツやEUIPOもハーグ指定可能なので、日本企業がドイツで意匠を取りたければ、直接DPMAに独語出願する代わりにハーグで「ドイツ」を指定することもできます(この場合、言語は英語で済みます)。ハーグ出願の効果としては、指定国で通常の国内出願をしたのと同等の権利が得られます。
ハーグ制度の利点は手続窓口が一本化できることと、全体として費用や手間を削減できることです。例えば複数国を指定すると各国への個別出願より出願料合計が安くなることがあります。また各国語への翻訳が原則不要(願書は一言語で足りる)ため、翻訳費用もかかりません。国際出願したデザインはWIPO公報(国際意匠公報)で公表されますが、最長30ヶ月の公開延期も選択可能で、これはEU意匠制度やドイツと同様です。
注意点として、ハーグ出願後に各国官庁から拒絶理由が通知された場合、それぞれに個別対応する必要があります(現地代理人を任意に起用して応答可能)。また日本を指定した場合、日本は一意匠制のため多意匠を含む国際出願は分割審査扱いになり、結果として日本では一意匠ずつ登録となります。欧州や米国など国ごとの制度差もあるため、万能ではありませんが、広範囲の権利取得には極めて便利です。
例えば、ドイツと日本の双方で意匠権を取りたい場合、(1)日本庁へ日本語で出願し、別途ドイツ庁へ独語で出願するか、(2)ハーグ制度で日本とEU(またはドイツ)を同時指定する方法が考えられます。近年は日本企業もハーグ利用が増えており、WIPO統計でも日本は上位のユーザー国です。ハーグ出願する場合、日本企業なら自国(日本特許庁)を経由して出願できますし、ドイツ企業ならDPMA経由または直接WIPOにオンライン出願できます。まとめると、ハーグ制度は多国同時出願をシンプルにするツールであり、ドイツ・欧州・日本といった複数地域への意匠戦略では是非検討すべき選択肢です。
実務的な注意点
最後に、意匠出願・権利化における実務上のポイントをいくつか解説します。図面の作成方法や出願タイミング、情報公開との関係など、日独で共通する事項と相違点を交えて述べます。
図面作成上の注意
-
明確で過不足ない表現: 意匠の権利範囲は提出した図面に表れたものに限定されます。したがって保護したい形状・模様は全て図面にしっかり示す必要があります。見えない裏側や内部構造は保護対象外なので、必要なら断面図や背面図も検討します。逆に保護したくない部分(例えば環境物や可変表示の一コマ等)は図示しないか破線で描くなどして、権利範囲を曖昧に広げすぎないようにします。
-
他の物や文字は描かない: 前述のとおり、図面/写真に製品以外の物(背景小物やスケール表示など)が写り込むと不備になります。背景は単色でコントラストを付け、製品だけを浮き立たせます。また図中に「正面図」「○○部分」など説明文字を入れるのも不可です。説明は願書や図面の簡易説明欄に記載し、図そのものは純粋な視覚情報だけにします。
-
色彩とモノクロ: 色も意匠の一要素なので、色の差異まで権利でカバーしたければカラー図を提出します。逆に形状だけを保護したい場合はモノクロ図面や線図にすることで、色に左右されない権利とするのが一般的です(例えばドイツ/EUでは白黒写真を提出すると色彩は権利範囲に含まれない)。日本でも同様ですが、近年カラー意匠も増えており、出願戦略次第です。
-
部分意匠・関連意匠の活用: 日本では部分意匠制度により製品の一部のみを破線で切り出して登録できます。ドイツ/EUでも実質的に同じことは可能で、製品の一部だけを描けばその部分デザインとして登録されます。さらに日本独自の関連意匠制度では、自社の類似バリエーションデザインを時期をずらしても10年以内なら関連出願できるため、シリーズデザインを網羅的に権利化することが可能です。欧州には形式上「関連意匠」の概念はありませんが、必要なバリエーションは全て別個に出願し、公開前であれば互いが新規性を害さないよう同時期に出願する配慮が必要です(※欧州では自己の先願が公開されると、それに類似する後願は自己であっても保護できなくなるため、日本のような関連意匠制度的救済がありません)。
-
複数意匠の一括出願: ドイツ・EUでは複数の意匠を一出願で手続できますが、それでも各意匠ごとに図面のセットが必要です。一枚の図に複数製品を並べて「まとめて一意匠」とすることはできません(それは一出願多意匠ではなく一意匠内に複数デザインを混在させた状態となり無効の原因になります)。複数デザインを一つの図に描いてしまうミスは、欧州実務でもしばしばあり無効事例があるため注意してください。
早期出願の意義と新規性喪失との関係
-
公開前の出願徹底: 意匠は新規性が命です。他人に先に出願・公開されると自分の意匠は保護できなくなります。したがって新製品のデザインは極力市場デビューより前に出願を済ませるのが鉄則です。特に日本では未登録意匠権が無いため、公開後に急いで出願しても(例外期間を超えれば)間に合いません。欧州でも1年のグレースピリオドはありますが、それは創作者自身の公開に限られ、第三者が類似品を公表すると新規性が失われます。またグレースピリオドを過信すると、手続きを失念したり1年を過ぎたりするリスクもあります。**「思い立ったが吉日」**で、完成デザインの確定次第すぐ出願するマインドが重要です。
-
展示会出品やネット掲載: 製品発表会や展示会への出品、カタログ・ウェブへの掲載は「公衆への開示」に当たります。これらを行う前に出願できればベストですが、もし先行してしまった場合でも速やかに猶予期間内に出願してください。日本なら公開から1年以内に出願し、なおかつ30日以内に証明書提出を忘れないこと。欧州では1年以内出願で特に届出不要ですが、公開日や内容の証拠は保存しておくと無効審判などで役立ちます。また第三者に製品デザインを見せる際はND契約を結ぶなど秘密保持し、新規性維持する工夫も大切です。
-
意匠と特許・商標との調整: デザインによっては特許(機能発明)や商標(立体商標等)との兼ね合いもあります。特許出願のために図面を公開すると意匠の新規性を失う恐れがありますし、その逆もあります。意匠と特許は別物であり、双方で保護可能な場合はそれぞれ出願するのが望ましいですが、出願順序や公開タイミングに注意しましょう。商標の立体形状とも重なる場合、一方を取得すると他方に影響するケースも考えられます(例えば日本では同一形状について意匠登録と商標登録を併存可能ですが、運用に注意が必要)。
公開タイミングとデザイン戦略
-
非公開期間の活用: ドイツやEUでは最長30ヶ月、日本では最長3年の公開猶予(非公開)制度があります。これを利用すると、製品発売直前までデザインを秘密に保ちつつ権利だけ確保できます。例えばファッション業界では新作発表シーズンに合わせて意匠権を公開するため、それまでは非公開にしておく戦略が取られます。逆に早期に公報公開することで第三者に牽制効果を与えるという考え方もあります(公開された登録意匠は誰でも検索でき、潜在的侵害者に警告となる)。製品サイクルや模倣被害状況に応じ、公開タイミングを選択できるのは意匠制度の利点です。
-
未登録意匠 vs 登録意匠: 欧州では流行品に未登録意匠(UCD)をまず取って、ヒットすれば1年以内に登録出願という二段構えもあります。ただし未登録だと独立創作を防げないため、競合が容易に類似品を独自開発する恐れがあります。日本企業が欧州でUCDを使う場合、必ずEU域内で最初に公開する必要があります(初公開が日本だとUCDは発生しない)。その点も踏まえ、グローバルな発売順序を調整することがあります。日本では未登録権利が無いため、意匠は登録してなんぼです。発売前に権利取得できなかった場合、ライフサイクルが短い商品であればいっそ公開してしまい営業秘密保護や不正競争防止法による保護を検討するなど、別のアプローチに切り替える判断も必要でしょう。
-
権利ポートフォリオ: 重要デザインに対しては、主要国で意匠権を多面的に取得することが推奨されます。欧州はEU意匠で一網打尽にし、日本・米国・中国・韓国等は個別出願またはハーグ出願で押さえる、といった具合です。その際、日本の関連意匠制度でバリエーションを補完し、欧米では必要数だけ個別登録するなど、国ごと制度を理解した上でポートフォリオを組むことが実務上のポイントです。デザインは模倣されやすいため、予め広めに権利化しておき、市場参入障壁を構築することが知財戦略となります。
以上の注意点を踏まえ、次にドイツ(およびEU)と日本の意匠制度の違いを一覧表にまとめます。
日本の意匠制度との主な違い(比較表)
以下に、ドイツ(およびEU)の意匠制度と日本の意匠制度の主要な相違点を比較表にまとめます。制度設計の違いが一目で分かるよう、項目ごとに両者の特徴を整理しました。
| 項目 | ドイツ・EUの意匠制度 | 日本の意匠制度 |
|---|---|---|
| 保護対象 | 工業的または手工業的に製造された製品の外観(全体または一部)。包装、グラフィカルな図形、書体なども含む。建築物も製品とみなされ保護可能。※部分意匠:製品の一部もそのまま出願可(図面で部分を示す)。※GUI等の画像:製品に表示される画面デザインは「製品(graphic symbol)」として保護可。※内装デザイン:複数製品の組合せとして一意匠に含めるのは不可(一つの出願に一製品のデザインのみ)(内装は複数意匠の集合で表現する必要)。 | 物品(部分を含む)の形状・模様・色彩の結合、建築物(部分含む)の形状等、画像(操作画面等、部分含む)で視覚を通じ美感を起こすもの。※部分意匠:可能(破線等で示す)。※画像:操作GUIや表示画像も保護対象(2019改正)。※内装:「内装の意匠」として店舗や室内空間全体の統一デザインも保護(2019改正)。 |
| 審査方式 | 無審査登録主義(方式審査のみ)。新規性・個性は登録時審査せず、異議申立制度も無し。無効主張は利害関係人による無効審判or侵害訴訟で行う。迅速登録(出願から数週間)。 | 実体審査主義。審査官が新規性・創作性等を精査し、拒絶理由通知~意見書/補正~査定のプロセスあり。権利化に半年~1年程度。拒絶査定不服は審判請求可。 |
| 存続期間 | 出願日から最長25年(5年ごとの更新×4回まで)。初回登録料で最初5年保護。更新は5年分一括払い(DPMA) or 毎5年(EUIPO、5年目末までに次期分)。 | 出願日から最長25年(2020年以降出願)。設定登録時に1~3年分納付、以降毎年年金納付。更新制度なし(25年満了まで)。 |
| 一出願での意匠数 | 多意匠可: ドイツ出願は最大100意匠まで包含可(通常同一分類内に限る)。EUIPO出願も100意匠まで(同一ロカルノ分類に限る)。一括出願でも各意匠は独立権利。 | 一意匠一出願: 原則1出願1意匠のみ。同一または類似デザインを複数保護する場合、関連意匠制度により本意匠の出願から10年以内なら類似意匠を別出願で関連付け可(ただし各々独立の権利)。一括出願制度はなし。 |
| 新規性要件 | 絶対的新規性: 世界中で公然知られた意匠と同一なら不可。欧州内で専門家が知らない程度の公開は除外。グレースピリオド: 創作者による公開から12ヶ月以内の出願は新規性喪失の例外(手続不要)。 | 絶対的新規性: 公知意匠と同一・類似なら不可。国内外問わず公開物が対象。グレースピリオド: 創作者等による公開から12ヶ月以内(2018改正、従前6ヶ月)。出願時に例外適用手続必要。展示会や学術発表も対象条件あり。 |
| 創作性要件 | 個性(個性的特徴): 既存デザインと異なる全体的印象を与えること。情報を持つユーザー視点で判断。設計の自由度が考慮され、小さな差異でも個性となり得る。一定の美感の水準は不問。※実審査なし。権利行使/無効審判時に判断。 | 創作非容易性(容易に考案できないこと): ありふれた変更や組合せではないこと(意匠法3条2項)。先行意匠群から当該意匠への着想が容易か否かで判断。需要者が受ける美感の違いで総合評価。※審査官が審査でチェックし、容易すぎると拒絶。 |
| 公開・非公開 | 登録と同時に公開(DPMAregister掲載・公報掲載)。公開猶予: 最大30ヶ月(出願時請求)。猶予中は画像非公開で一時保護。5年存続させるには30ヶ月以内に追加費用払って公開・正式登録。猶予中は故意のコピーのみ差止可。EUIPOでも同様に最長30ヶ月公開延期可。 | 登録と同時に公報発行。秘密意匠: 登録日から最長3年間、図面非公開可(出願時請求)。秘密期間中は他人に権利行使できない(模倣の証明が事実上困難)。期間経過または任意のタイミングで公開可能。その後通常の権利行使可。 |
| 権利範囲(侵害判断) | 同一・同様の全体印象なら侵害。侵害判断は「情報を持つ利用者」による全体視感で行う。意匠の要部だけでなく全体比較。未登録意匠(UCD): 3年保護だがコピー行為にのみ及ぶ(独立創作は不侵害)。 | 同一・類似の意匠まで権利範囲(意匠法23条)。侵害判断は需要者の視覚による美感の印象で総合判断。物品用途が異なると非類似となりやすいが、一部用途共通なら類似認定可能。※未登録意匠の権利保護制度なし。 |
| 管轄庁 | ドイツ国内意匠: DPMA(ミュンヘン)EU意匠: EUIPO(アリカンテ)無効審判: DPMA意匠部門 / EUIPO異議部門侵害訴訟: ドイツ各地の特許庁管轄裁判所 / 他EU加盟国も管轄あり(単一訴訟でEU全域差止も可) | 日本意匠: 特許庁(経産省外局・東京)無効審判: 特許庁審判部(意匠無効審判)侵害訴訟: 東京・大阪地裁(知財高裁控訴) |
| 国際出願 | ハーグ協定加入(ドイツもEUも加盟)。WIPO経由で指定可能。ドイツ単独指定も可、EU指定も可。 | 同左(2015年加盟)。ハーグ経由で日本指定可。日本を指定した国際登録は審査付き(不登録の場合通知)。 |
※上記表で「ドイツ・EUの意匠制度」は主にドイツ国内意匠とEU共同意匠の共通点を中心に記載しています。一部ドイツ固有(例えば言語要件や費用)とEU固有(未登録意匠など)の事項を併記しました。
まとめと活用の提言
ドイツと日本の意匠制度は基本理念こそ同じものの、運用面で審査の有無や制度オプションの違いなど多くの相違点があります。知財実務者にとっては、これらの違いを正確に把握し、ケースバイケースで最適な戦略を立てることが重要です。例えば、ドイツでは迅速に権利化できる長所を活かして早期に登録を押さえつつ、欧州全域のカバーが必要ならEU意匠も併用する、といった戦略が考えられます。日本では審査期間を見越して計画的に出願し、関連意匠制度で自社デザイン群を丁寧に保護することが肝要でしょう。
公式情報源によれば、ドイツ意匠は手続簡易で出願から登録までわずか数週間とされ、日本意匠は審査ありで権利安定性が高いと評価されています。どちらが優れるというより、デザインの種類や事業展開地域に応じて両制度を使い分け、補完し合うことが肝心です。グローバル企業であれば、ハーグ制度も駆使して日本・ドイツ・EUの意匠権をワンセットで取得し、模倣品対策やブランド戦略に活用するのが望ましいでしょう。
本稿で述べた比較とポイントが、日独両国の意匠実務に携わる皆様の参考になれば幸いです。デザインの価値がますます重視される現代、各国制度の違いを乗りこなし、知的財産としての意匠を最大限に活用していただくことを期待しています。
参考文献・出典: 本文中に【】付きで示した番号は出典を表し、以下に対応する情報源を示します。
【1】DPMA (ドイツ特許商標庁)「Examination and Registration - Designs」公式サイトより抜粋(ドイツ意匠の方式審査内容、新規性非審査等)
【3】DPMA公式サイト「Design protection」より(意匠の定義・保護対象・権利内容)
【4】DPMA公式サイト「Requirements of Protection」より(新規性・個性要件と12ヶ月グレースピリオド説明)
【10】DPMA公式サイト「Application」より(出願手続概要、オンライン出願、複数意匠100件まで可、処理期間等)
【11】DPMA公式サイト「Required data and documents」より(提出図面要件、最大10図面、図示対象の限定等)
【12】DPMA公式サイト「Required data」より(図面の3つの要件:1画像1視点、背景単色、説明等不可)
【18】INPIT「意匠権の存続期間はどのくらいですか。」FAQ(日本意匠の存続期間25年、経過措置)
【20】INPIT「意匠とは何かについて教えてください。」(日本意匠法の目的・定義条文)
【24】Wikipedia "European Union design"(EU意匠制度の概要。未登録意匠3年保護や全体的印象の侵害判断について)
【25】WIPO Hague Systemページ「What is the Hague System?」(ハーグ国際出願の概要:100意匠/1出願・指定国数)
【7】特許庁「意匠の新規性喪失の例外期間延長について」(平成30年法改正解説)
【6】特許庁「意匠 新規性喪失例外 手続について」ページ(証明書提出期限30日等)
【17】特許庁プレスリリース「令和元年意匠法改正の概要」(関連意匠10年延長、画像・建築物・内装追加)
【9】Seifried IP法律事務所ブログ「Design application EUIPO DPMA」(図面の誤り事例:複数製品を1意匠に描いた無効例等)
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)