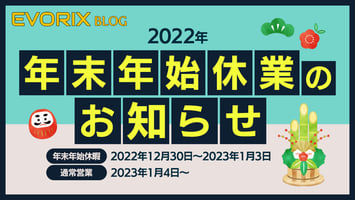1. 登録要件...
フィンランドの意匠制度概要
登録要件(新規性・独自性など)
フィンランドの意匠(デザイン)法では、「意匠」とは「製品の外観であって、当該製品自体またはその装飾の特徴(線、輪郭、色彩、形状、織り模様、素材の特徴に由来するもの)」と定義されています。ここでいう「製品」には、工業製品または手工芸品に加え、複合製品の構成部品、包装、外装、図形的表象、印刷書体なども含まれます。ただし部分意匠制度は採用されておらず、製品の一部分だけを独立した意匠として登録することはできません。
意匠登録を受けるには、その意匠が新規性および独自性(創作性)の要件を満たす必要があります。新規性とは、出願日または優先日より前に同一の意匠が公衆に公開されていないことを意味します。世界中のいかなる場所でも同一のデザインが公知となっていた場合、フィンランドでは新規性が否定されます。独自性(個性)とは、登録出願前に公衆に知られている意匠と比べて、当該意匠が異なる全体的印象を与えることを指します。この独自性の判断にあたっては、当該意匠が属する製品分野における創作の自由度も考慮されます。
さらに、フィンランド意匠法には不登録事由(登録が認められない要件)も定められています。主な不登録事由として以下が挙げられます:
-
法律上の「意匠」の定義に適合しないもの(例えば純粋に技術的機能のみで定まる形状)
-
公序良俗に反するもの
-
他人の有する公式の紋章・記章などと紛らわしいもの
-
純粋に製品の技術的機能によって決まる形状のデザイン(機能美のみの形状は保護対象外)
-
他の製品との機械的接合部(いわゆる「互換部品」)の正確な形状・寸法のみから成るデザイン(接続のために不可欠な形状のみのもの)
また、既に公知となっている意匠と実質的に同一のデザインや、先にフィンランドで登録された他人の意匠と同一のデザインも登録できません。これらは新規性・独自性の観点から拒絶されることになります。
出願手続
フィンランドで意匠権を取得するには、フィンランド特許登録庁(PRH)に対して意匠登録出願を行います。出願はフィンランド語またはスウェーデン語で行う必要があります。オンライン電子出願が可能で、紙やEメールでの出願より手数料面で割安に設定されています(後述の減免制度参照)。
出願に必要な書類・情報は以下の通りです:
-
出願人および創作者(デザイナー)の氏名・住所
-
意匠を表す図面または写真(デザインの全体を視覚的に示すもの)
-
意匠の対象となる製品の名称(出願人がその意匠をどの製品に用いるかを指定)
-
優先権を主張する場合は、その最初の出願の国、出願日、出願番号
-
所定の出願手数料の納付証明
-
出願人が創作者本人でない場合は意匠を承継したことを証明する書面(譲渡証など)
フィンランドでは一つの出願で複数の意匠をまとめて出願すること(Multiple design application)が認められています。複数意匠を一括出願する場合、原則として全ての意匠が同一または類似する製品分類(ロカルノ分類)に属している必要があります(分類が異なる場合でも手数料を追加することで包含可能)。出願件数を減らすために類似する意匠を一出願にまとめる戦略も可能ですが、意匠ごとに追加手数料が発生します。
代理人・委任状:出願人がフィンランド国内(またはEU・EEA域内)に居所がない場合、フィンランドの代理人(代理業務資格者)を選任しなければなりません。代理人を通じて出願する際には、後述するように委任状(Power of Attorney)を提出する必要があります。委任状は出願時または特許庁からの通知に応答して提出することができ、通知を受けた場合は2ヶ月以内に提出すれば足ります。
審査手続:フィンランドの意匠出願は全件について方式および実体審査が行われます。日本とは異なり、意匠出願の公開制度(出願から一定期間後に内容を公開する仕組み)はなく、また審査請求制度もありません。出願を行うと直ちに審査官による審査が開始され、方式要件や不登録事由の有無、新規性・独自性などが総合的にチェックされます。審査は自動的に行われるため別途の審査請求は不要であり、出願から登録までの平均処理期間は約5ヶ月程度とされています。
異議申立て:審査で登録適格と判断された場合、正式に登録となる前にその内容が意匠公報で公告されます(出願公告)。公告日から2ヶ月間は第三者が異議申立てできる期間となっており、公告された意匠に対して「不登録事由に該当する」「新規性や独自性が欠ける」等の理由で異議申立てを行うことが可能です。異議期間内に異議が申し立てられなかった場合、または異議が棄却された場合には、意匠登録が確定します。
最終登録・登録料:審査通過後、フィンランド特許登録庁から登録の通知(許可)が出されます。その際に所定の登録料を支払う必要があります。登録料は通知から原則2ヶ月以内に納付しなければなりません。フィンランドでは2019年の手数料改定により従来必要とされていた意匠公報掲載料(発行料)を廃止し、現在は出願料に統合されています。オンライン出願の場合、2020年時点で出願基本料は250ユーロ(紙やメール出願は300ユーロ)と設定されています。登録が完了すると登録証が発行され、意匠権が発生します。
保護対象(権利の内容・範囲)
フィンランドの意匠権による保護対象は、上記の定義に適合する製品の外観デザインです。具体的には、工業製品・手工芸品の外観や、その製品に施された装飾的な形状・模様・色彩など、視覚を通じて美感を起こさせるデザインが保護されます。包装や容器のデザイン、製品に描かれたグラフィックシンボルやパターン、タイポグラフィ(書体デザイン)なども含めて保護の対象となり得ます。なお、ソフトウェアの画面デザイン(GUI)についても図形的表象として保護可能です。
部分意匠について: 前述の通りフィンランドには日本のような「部分意匠」制度はありません。したがって、製品の一部分だけに創作的なデザインが施されている場合でも、その部分だけを切り出して意匠登録することはできません。保護したい部分がある場合は、その部分自体を一つの「製品」(例えば「自動車のバンパー」など部品自体を製品名とする)として出願する必要があります。意匠権の効力はあくまで登録された「製品の外観」に及ぶため、製品全体として意匠を特定することが求められます。
権利範囲: フィンランドの登録意匠権を得ると、同一または類似の意匠の製品を無断で業として製造・販売・輸入・輸出する行為を差し止める権利が発生します。ここでいう「類似の意匠」とは、登録意匠と全体的印象において似ているデザインを指し、模倣品が与える視覚的印象を比較して侵害か否かが判断されます。ただし意匠権は、製品の技術的機能そのものには及びません。デザインに技術的な機能上不可欠な形状が含まれていても、それは意匠権ではなく特許や実用新案で保護すべき領域となります。また、接続用部品のように技術的理由で形状・寸法が決まる部分については、意匠権による独占から除外される傾向にあります。
フィンランドではEU指令に基づき、自動車などの複合製品の修理用部品(元の外観を復元する目的のスペアパーツ)については意匠権の保護期間を制限する特例があります(後述)。これに関連し、複合製品の部品のデザインであっても、純粋に外観上の特徴で競争上重要なものは保護対象となりますが、単に元の製品と寸法・形状を合わせるためだけの部分は保護範囲から事実上除外されます。したがって、他社製品との交換部品等に関わるデザインは、意匠権で長期独占することはできない仕組みになっています。
新規性喪失の例外(グレースピリオド)
フィンランドの意匠法には、一定の場合に限り出願前の公表が新規性を喪失したものとみなされない新規性喪失の例外(グレースピリオド)が設けられています。具体的には、意匠の創作者(またはその承継人)本人による公表、または創作者の意思に反して第三者が無断で行った公表については、その公表から12ヶ月以内にフィンランドで意匠出願すれば、新規性が失われていないものとみなされます。例えば、デザイナーが製品発表会や展示会で自らデザインを公開した場合や、盗用や漏洩により第三者が勝手に公表してしまった場合でも、公表日から1年以内であれば救済されるということです。
このグレースピリオドを適用するには、出願時に公表の事実や日時を申告し、所定の証明書類を提出することが求められます(※フィンランド法には詳細な手続規定があります)。日本の意匠法でも2020年の改正で同様の新規性喪失の例外期間(1年)が導入されましたが、フィンランドでは自己の公表・第三者の不正公表のいずれの場合も一律12ヶ月の猶予となっている点で共通しています。
注意点として、グレースピリオド経過後に出願された場合や、第三者による単なる先使用・先公開はこの例外の適用対象外です。他者に先に公開された場合でも1年を超えてしまうと新規性は喪失します。また、グレースピリオド中であっても他人が独立に同じデザインを創作・出願していた場合には先願優先となるため、自身の公表後はできるだけ早く出願することが推奨されます。
減免制度(手数料の減免措置)
フィンランドの意匠制度には、日本のような中小企業等を対象とした公式な手数料減免制度(審査請求料や年金の減額措置など)は特に設けられていません。意匠登録にかかる手数料は法令に基づき一定に定められており、全ての出願人に一律に適用されます。ただし、手続上・運用上の配慮として以下のような費用軽減策が存在します。
-
オンライン出願割引:電子出願により事務負担が減る分、オンラインでの意匠出願基本料は紙出願よりも安価に設定されています。2020年の改定時点でオンライン出願料は250ユーロ、書面出願は300ユーロと明示されており、この差額が事実上の割引措置となっています。また商標の分野ではオンライン手続への移行が義務化されていますが、意匠も電子出願が推奨されています。
-
複数意匠一括出願によるコスト節減:一出願で複数の意匠を含めることが可能であり、その場合各意匠ごとに追加手数料は発生しますが、別々に出願するよりも総額は抑えられる設定になっています。例えば基本料で1意匠分をカバーし、2意匠目以降は追加意匠手数料を加算する方式です。同時に複数デザインを権利化したい場合には、この制度を活用することで費用・手間の両面で効率化できます。
-
周辺費用の見直し:前述の通り、フィンランド特許庁は近年意匠登録の公告料(発表料)を撤廃しました。これにより、従来は登録時に別途必要だった費用が不要となり、出願人の負担軽減につながっています。また登録料も出願料に統合されワンストップ化されたため、手続きが簡素化されています。
なお、フィンランド特許庁(PRH)は公式サイトで料金表を公開しており、意匠登録・更新等の各種手数料額が確認できます。また、手数料は随時見直されることがあるため、出願時には最新の料金を確認することが重要です。年金(更新料)支払いにも猶予期間や追加料金(後述)が設定されていますが、これは減免ではなく遅延時の追加コストに関する規定です。
以上のように、フィンランドの意匠制度自体に特別な減免措置はありませんが、電子化や手数料体系の簡素化によって出願人の経済的負担に配慮した運用となっています。
委任状(代理人の必要性)
フィンランドに出願人本人が住所または営業所を有していない場合、現地代理人の選任が必須となります。特に欧州経済地域(EEA)外の出願人は、フィンランドまたはEEA域内居住の代理人を通じて手続きを行わなければなりません。代理人としてはフィンランドの特許代理人や弁護士が該当し、日本から出願する場合は現地の提携代理人に委任する形になります。
代理人を立てる際は、委任状(Power of Attorney)の提出が必要です。フィンランド特許庁の運用では、出願時に署名済みの委任状を添付するか、もしくは出願後に庁からの要求(Office Action)に応答して提出することが認められています。仮に出願時に委任状を省略した場合でも、後日PRHから通知を受け取ってから2ヶ月以内に提出すれば手続上問題ありません。委任状には出願人(権利者)が代理人に手続きを委任する旨を明記し、署名が必要です。ただしフィンランドでは一般に委任状の認証(公証人や領事による認証)は要求されず、署名のみで有効とされています。
日本の実務と比較すると、フィンランドでは委任状原本の提出が求められる点に注意が必要です(日本では電子出願時に委任状省略が可能な場合がありますが、フィンランドでは提出が原則)。提出はPDF等スキャンコピーでも受理される場合がありますが、特許庁から要求があれば原本提出も検討します。委任状のフォーマットは特に法律で規定されていませんが、出願人・代理人の情報と委任事項(意匠出願手続一切を委任する等)を記載します。英語またはフィンランド語で作成するのが一般的です。
まとめると、フィンランドで意匠出願・権利維持を行う場合、現地代理人を通じる必要があり、その法定要件として委任状の提出が求められるということになります。これは円滑な手続のための要件であり、期限内に適切な委任状を提出しないと手続が進行しない恐れがありますので注意が必要です。
図面要件(出願時の図面・写真の形式)
フィンランドの意匠出願では、そのデザインを視覚的に明確に表現した図面または写真を提出する必要があります。提出された図面等のみを基に新規性・独自性の審査が行われるため、意匠の特徴が十分に把握できる図示が重要です。図面要件の主なポイントは次の通りです。
-
視覚資料の種類:線画の図面でも写真でも構いません。製品の形状や模様を正確に示せる形式であればカラー写真やCG画像も許容されます。ただし画像は鮮明でコントラストがはっきりしたものを用意します。必要に応じて背景を単色にするなど、デザイン自体が際立つよう工夫します。
-
複数の視点図:立体物のデザインの場合、複数の角度から見た図を提出することが推奨されます。一般には正面・背面・側面・上面・下面・斜めからの透視図など、少なくとも6面図+斜視図程度を用意すると良いでしょう。フィンランド法自体は提出図面数を明示していませんが、審査官がデザインの全貌を把握できるよう十分な図面を添付することが望まれます。
-
同一意匠につき一組の図面:一出願において一つの意匠(デザイン)について複数枚の図を提出する場合、それらは全て同じ意匠を表すものでなければなりません。例えば一出願に含まれる複数の図が、それぞれ異なるバリエーションの製品デザインを示すようなことは許容されません(その場合は複数意匠出願として扱われる)。各図面は互いに補完し合い、立体物であれば全方向からの情報を提供するものとなります。
-
図面の内容制限:図面中に寸法線や文字、番号など説明的な表示を付加することは禁止されています。純粋にデザインのみを示し、願書などテキスト部で必要事項を説明する運用です。また、背景に余計な物品や模様が映り込まないよう配慮します。願書には製品名称等を記載しますが、図面自体には製品名や用途などの記載は不要です。
-
部分の表現:部分意匠制度が無いフィンランドでは、図面の一部を不実線(破線)で描いてその部分は権利範囲に含めない、という部分的クレームは原則できません。すべて実線で描かれた部分が意匠権の保護対象とみなされます。ただし、製品と関係ない環境(例えば装着例を示すために他の製品と組み合わせた図など)を示す場合には、それと分かるように破線やぼかしで描くことは実務上行われます。その際も、登録を受けようとする製品自体のデザインは明瞭に実線で描く必要があります。
-
実物の提出:フィンランドでは二次元物品のデザイン(例えば布地の模様)について、例外的に現物の見本を提出することも可能です。この場合、別途「見本保管手数料」が発生します。もっとも現在は高品質な画像提出が主流であり、現物提出は特殊なケースとなっています。
以上の図面要件を満たさない場合、特許庁から補正を求められることがあります。例えば図が不鮮明だったり、デザインの一部が判別困難な場合です。その際は指示に従い図面の差し替えや追加を行います(補正にも所定の補正手数料が必要です)。適切な図面を最初に提出することが、スムーズな登録への近道となります。
保護期間と権利維持
フィンランドの登録意匠権の存続期間(保護期間)は、出願日から最初の5年間です。意匠権者は希望に応じて、この5年の存続期間を4回まで更新することができます。更新はそれぞれ5年ごとに行われ、最大で25年間まで権利を維持することが可能です。25年経過すると意匠権は満了し、そのデザインは公有(パブリックドメイン)となります。
更新手続は、現在の存続期間が満了する前1年以内から更新期限までの間に行います。フィンランドでは更新料の納付期間が定められており、現行の5年期間の満了前年から更新申請が可能です。期限までに更新料を支払えば次の5年間の延長が認められます。もし更新期限を過ぎてしまった場合でも、満了後6ヶ月以内であれば遅延付加料(割増料金)を支払うことで更新手続を完了できます。この6ヶ月の猶予期間内に更新しないと、意匠権は消滅します。
修理用部品に関する特例:EUデザイン指令の規定により、フィンランドでは複合製品の部品で、その製品の元の外観を修復する目的で使用されるもの(いわゆるスペアパーツ)に関して、意匠権の保護期間が最大15年に制限されています。これは自動車の車体部品などに典型的に適用されるルールで、意匠権による独占を一定期間(15年)に留め、その後は競合他社による補修部品の供給を可能にする趣旨です。通常の意匠は25年まで更新できますが、この種の部品デザインは15年を超えての権利延長が認められません。
年金(維持費):意匠権を維持するための更新料(年金)は、更新する5年ごとに支払います。更新料は更新申請時にまとめて納付し、次の5年分を前払いします。フィンランドでは更新回数ごとに料金が段階的に上がることはなく、一律の体系ですが、将来的な法改定で変更される可能性もあります。権利者は更新期限を管理し、特許庁からの更新案内通知などを見逃さないようにする必要があります(代理人経由で案内が届くこともあります)。
以上のように、フィンランドの意匠権は5年×最大5期間=25年の範囲で保護されます。更新を怠らなければ四半世紀にわたりデザインを独占できる計算ですが、技術革新や流行の変化が早い分野では、25年より前に実質的価値が薄れる場合もあります。適切な期間、権利を維持するかどうかは権利者のビジネス判断となります。
侵害訴訟(民事措置)
フィンランドにおいて意匠権を侵害された場合、権利者は民事訴訟によって救済を求めることができます。意匠権侵害訴訟の管轄は、知的財産事件を専門に扱う市場裁判所(Market Court)です。市場裁判所は知的財産権、競争法、市場規制に関する紛争を第一審として取り扱う特別裁判所であり、意匠権侵害の差止め・損害賠償請求訴訟は原則ここに提起されます。市場裁判所の判決に対する控訴は、高等裁判所を飛ばして直接最高裁判所に上訴する仕組みとなっています。
民事的救済:意匠権者が侵害訴訟で請求できる主な救済は、差止命令(侵害行為の停止)と損害賠償です。差止命令は裁判所が侵害者に対し違法な製造・販売等を停止するよう命じるもので、フィンランドでは判決確定前でも仮差止(暫定的な差止措置)を求めることが可能です。差止命令には第三者(仲介業者)に対する差止めも含まれ、例えば侵害品を流通させているプラットフォームや運送業者に対しても、関与停止を命じることができます。裁判所はこの差止命令に違反した場合に罰金を科す旨を付すことができ、命令の実効性を担保します。
損害賠償については、意匠権侵害によって被った実損の賠償が認められます。フィンランド法では侵害者の故意・過失の程度によって賠償額が考慮され、侵害者に軽過失しかない場合には賠償額が減額され得ると規定されています。故意または重大な過失による侵害であれば権利者の逸失利益や侵害品から得た利益相当額等、幅広い損害項目が請求可能です。裁判所は必要に応じて懲罰的要素を含む補償金(Punitive damagesに近い概念)はフィンランド法にはありませんが、悪質なケースでは上限の罰金刑(後述)とは別に高額の賠償を命じる傾向があります。
立証と手続:意匠侵害訴訟では、原告側(意匠権者)が自らの意匠権の有効性および被告による侵害事実を立証する必要があります。フィンランドの意匠は登録前に実体審査が行われているため、基本的には有効な権利ですが、被告は反訴または抗弁として「その意匠登録は無効(新規性欠如等)である」と主張することもできます。無効主張が認められれば侵害以前に権利が否定されるため、被告は責任を免れます。無効理由の判断は市場裁判所が行い、場合によっては特許庁の登録無効審判と並行することもあります。市場裁判所は専門性が高く、技術およびデザインに明るい裁判官や専門委員が審理に関与します。
侵害品の取り扱い:勝訴した権利者は、侵害品やその製造設備の廃棄・差し押さえなども請求できます。裁判所は侵害品が流通市場から排除されるよう、在庫品の回収・廃棄処分や輸入品の場合は再輸出禁止などの命令を下すことが可能です。これらの措置はEUの知財権執行指令に基づき各国法に整備されています。
行政摘発(刑事手段・税関措置)
フィンランドでは、民事訴訟による救済に加えて刑事罰や税関による取締り(行政的措置)といった公的手段も知的財産権侵害に対して用意されています。
刑事罰:意匠権の侵害行為が故意に行われた場合、侵害者には刑事罰が科される可能性があります。フィンランド刑法は知的財産権侵害を産業財産権に対する犯罪の一種と位置付けており、悪質な意匠権侵害者に対して罰金刑または最長で2年以下の懲役刑を科す規定があります(※刑法第49章に産業財産権侵害罪が定められています)。実際の適用においては、商標や著作権の偽造品・海賊版ほど頻繁ではないものの、意図的なデザイン盗用で営業上他者に損害を与えた場合には刑事事件となり得ます。
フィンランドの刑事手続では、意匠権侵害の罪は親告罪に類する扱いで、被害者(権利者)の告訴がなければ起訴されません。そのため、刑事摘発を望む場合は権利者自ら警察に被害届を出し、捜査を求める必要があります。警察が捜査を行い、検察官が起訴に踏み切れば刑事裁判となり、有罪なら前述の刑罰が科されます。刑事裁判においても、被害者である権利者は附帯私訴で損害賠償請求を提起することが可能で、これは刑事手続に併合して審理されます。刑事上の有罪判決が確定した場合、侵害者は生じた損害の賠償義務も負います(軽過失の場合は賠償額の減額もあり)。
税関での水際取締り:フィンランドはEU共通の知的財産権侵害物品取締制度を採用しており、税関による模倣品の水際措置が利用できます。意匠権者は税関当局に対し、自身の意匠権を侵害する疑いのある物品の輸出入を差し止めるよう申請(Recordation)することができます。申請が受理されると、税関は輸出入検査の際に対象デザインの模倣品らしき貨物を発見した場合、その通関を一時停止または留置(押さえ置き)します。税関が怪しい貨物を発見した際は権利者および輸入業者に通知が行われ、一定期間内に権利者が差止め命令を裁判所に求めるか、当事者間で同意による廃棄処分にするかなどの対応が取られます。権利者からの正式な差止め申請が無い場合でも、税関官が職権で知的財産侵害の疑いがある物品を発見した際には自主的に通関を保留しうる権限もあります。このように、行政当局が国境で模倣品の流通を阻止する仕組みが整っています。
フィンランド国内法としても関税法に「行政的留置」の規定があり、犯罪の予防または捜査のため合理的理由がある場合には税関が輸出入貨物を留置できると定めています。最終的な差押えや没収には裁判所の手続が必要ですが、税関レベルでまず荷止めをして被害拡大を防ぐことが可能です。知的財産権者にとっては、侵害品が市場に出回る前に押さえるこの水際措置は効果的な手段であり、特に大量輸入される模倣品への対策として重要です。
その他の行政的措置:意匠権侵害に特化した行政機関による取締り(例えば日本のような経産省による警告など)はフィンランドにはありません。しかし、消費者安全や製品表示の観点で問題がある場合には別途行政当局が動くことも考えられます(例えば模倣品が安全基準を満たさない場合の市場からの撤去命令等)。基本的には知財侵害は民事・刑事・税関措置の組み合わせで対処されます。
国際出願との関係(ハーグ制度含む)
フィンランドは国際意匠登録制度である**ハーグ協定(ジュネーブ改正協定)の加盟国です。そのため、フィンランドを指定国として国際意匠出願(ハーグ出願)**を行うことが可能です。日本からもハーグ経由でフィンランドを指定して意匠登録することができますし、フィンランドの出願人が国際出願を通じて他国で保護を得ることもできます。
ハーグ出願の効果:国際登録簿にフィンランドを指定して登録された意匠は、国際事務局(WIPO)から付与された国際登録日以降、フィンランド国内出願と同一の効力を有します。つまり、ハーグで登録完了すれば自動的にフィンランド国内でも意匠権に相当する地位を得ます。ただし実際に権利が維持されるためには、フィンランド特許庁(PRH)による審査を経て拒絶されないことが条件です。
拒絶審査:フィンランドは実体審査主義の国であるため、ハーグ経由の国際登録についても国内出願と同様の基準で審査を行い、登録要件(定義適合性、新規性、独自性、不登録事由など)を満たさない場合には拒絶通報を発します。フィンランド特許庁が国際登録の公告(国際公報掲載)を知ってから12か月以内に拒絶の通報をWIPO国際事務局に送付することになっており、この期間内に通報がなければフィンランドにおいてその意匠は保護されることが確定します。拒絶理由通知が出された場合、国際登録の権利者(出願人)は指定期間内にフィンランド特許庁に意見書を提出して対応することができます。意見書で反論が認められれば拒絶は覆り、国際登録はフィンランドでも有効となります。もし対応が不十分で拒絶が確定すると、その国際登録はフィンランドにおいて無効(効果なし)となり、その旨が意匠公報に公告されます。
ハーグ経由の意匠権についての保護期間や権利内容は、基本的にフィンランド国内登録と同じです。更新も国際登録としてWIPOに申請することで、フィンランドを含む指定国すべてに対して一括更新できます。フィンランド個別に年金を支払う必要はありませんが、WIPOへの国際更新料を期限ごとに納付します。
EU意匠制度との関係:フィンランドは欧州連合の加盟国であるため、EU全域で有効な意匠権である意匠の共同体意匠(Registered Community Design, RCD)でもフィンランド領域をカバーできます。EUIPO(欧州連合知的財産庁)に出願して登録された意匠権はフィンランドを含むEU加盟国全てで効力を発揮します。EUIPOで登録される意匠は無審査登録(新規性や独自性について実質審査を行わず登録される)ですが、第三者から無効審判請求があれば審理される制度です。フィンランド国内のみで権利が必要な場合でも、費用や手続の効率からEU意匠を選択する企業も多いとされています。実際、EUIPOでの意匠登録は通常1ヶ月程度で完了し費用も抑えられるため、フィンランド企業も国内意匠ではなくEU意匠を利用するケースが一般的です。
もっとも、フィンランド独自の意匠制度は上記のように手厚い審査と長期の存続期間を特徴としており、国内意匠登録には異議申立て制度もあるなど、クオリティの高い権利が付与されるメリットがあります。そのため、重要なデザインについてはフィンランド国内出願を行い、補完的にEU意匠やハーグ国際出願も活用するといった戦略が考えられます。日本企業がフィンランドで意匠保護を図る場合、ハーグ経由でフィンランドを指定する方法と、EU意匠を取得して包括的にカバーする方法、そしてフィンランドに直接国内出願する方法が選択肢となります。目的や予算に応じて最適なルートを検討すると良いでしょう。
以上、フィンランドの意匠制度について各項目別に解説しました。最後に、日本と比較しやすいよう主要項目を一覧表にまとめます。
フィンランド意匠制度の概要比較表
| 項目 | フィンランドの意匠制度 |
|---|---|
| 登録要件 | ・新規性(世界公知でないこと)、独自性(異なる全体的印象)・純粋に機能による形状や公序良俗違反など不登録事由あり・部分意匠制度なし(製品全体で登録) |
| 出願手続 | ・PRH(フィンランド特許登録庁)に出願(言語:芬蘭語/瑞典語)・願書に出願人・創作者情報、図面/写真、製品名、優先権情報等を記載・電子出願可(オンライン料金割引あり)・複数意匠一括出願可能(追加手数料で対応) |
| 保護対象 | ・製品の外観デザイン(線・形状・色彩・模様・材質感等)・工業製品・手工芸品、部品、包装、図形、書体など幅広く含む・技術的機能のみの形状や接続部品形状は権利範囲外 |
| 新規性喪失の例外 | ・自己の公表または無断公表から12ヶ月以内の出願は新規性を喪失しない・グレースピリオド期間は一律12ヶ月(自己・第三者いずれも対象)・適用には出願時の申告・証明が必要(事後の立証) |
| 手数料減免制度 | ・特別減免制度は無し(一律の料金体系)・電子出願基本料は紙出願より低廉(例:250€ vs 300€)・意匠公報掲載料を2019年に廃止(出願料に統合)・複数意匠出願でコスト効率化可能(追加料必要) |
| 委任状(代理) | ・EEA域外の出願人はフィンランド/EEA在住代理人必須・代理人経由手続には委任状提出必要・委任状は出願時または庁の催告後2ヶ月以内に提出・署名のみで有効(公証不要)、原本提出が原則 |
| 図面要件 | ・意匠を明確に示す図面または写真が必要・複数視点からの図を提出(6面図+斜視図推奨)・図中に文字や寸法等は不可(デザインのみ描画)・部分意匠不可のため基本全て実線描写(環境部品は破線可) |
| 保護期間 | ・登録日から5年×最大5期=25年まで更新可・各更新時に更新料支払い(期限後6ヶ月は猶予更新可)・複合製品の修理用部品は保護上限15年 |
| 侵害訴訟(民事) | ・市場裁判所が管轄(知財専門裁判所)・差止請求(仮処分含む)と損害賠償請求が主・故意・重大過失なら高額賠償、軽過失なら賠償額減額の考慮・第三者関与者への差止も可能(ISP等) |
| 行政摘発(刑事・税関) | ・故意侵害は刑事罰の対象(罰金刑または最大2年以下の懲役)・刑事訴追は権利者の告訴が必要(親告罪的運用)・税関による模倣品水際措置あり(申請により輸入差止め)・税関は職権でも疑義品を留置可能 |
| 国際出願との関係 | ・ハーグ協定加盟:国際登録でフィンランド指定可・国際登録は国内出願と同等効力(12ヶ月内に拒絶なければ有効)・拒絶通報期限12ヶ月、意見書提出可・EU意匠制度あり:RCDでフィンランドを含むEU全域保護 |
参考文献・出典
-
遠藤誠 「フィンランドの知的財産法」 BLJ法律事務所 (2020) 他.
-
IP Guide: Industrial Design in Finland – Patentia Oy提供情報 (IP Coster, 2024) 他.
-
特許庁 「フィンランド意匠法(日本語仮訳)」(2013年法改正反映)他.
-
Country Index – Finland (SMD Group, 2020年改定) .
-
Boco IP (フィンランド特許事務所) 「Designs – Applying for and registering protection」 (2021) .
-
フィンランド関税法・EU規則に基づく模倣品取締り(BLJ法律事務所資料).
-
その他:欧州委員会・EUIPO公開情報、JETRO・特許庁公開資料 等.
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)


.jpg?height=200&name=unnamed%20(94).jpg)