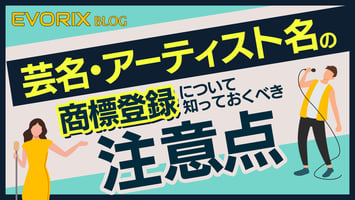この度、知的財産事務所エボリクスは、2021年8月で4年目を迎えました。
カナダの意匠制度概要
1. 登録要件(意匠の定義・創作性・新規性など)
カナダにおける意匠の定義: カナダでは意匠(Industrial Design)とは製品の「見た目」を保護するものであり、製品に適用される独自の視覚的特徴が対象となります。具体的には、完成品(finished article)に施された三次元の形状・配置(shape, configuration)および二次元の模様・装飾(pattern, ornament)(色彩を含む)から成るデザインが保護対象です。製品全体のデザインだけでなく、その一部のデザイン(部分意匠)も保護可能です。これら視覚的特徴は「目に訴える」(appeal to and judged solely by the eye)ものでなければなりません。逆に、製品の機能にのみ由来する形状等(純粋に機能上の必然から生じた形状)や、アイデアそのもの、製造方法、材料は意匠として保護されません。また、公序良俗に反する意匠は登録不可です。
創作性要件: カナダの意匠制度では、日本の旧来の「創作容易性」のような高度の創作性要件は明示的には設けられていません。意匠が登録されるためには新規性(novelty)が要求されており、これは同一または実質的に類似した意匠が世界のいかなる場所でも公衆に開示されていないことを意味します。新規性の判断において、既存の意匠と**「実質的に同一かどうか」が基準となり、それに該当すれば登録不可となります。したがって、先行意匠との差異が小さいような場合は新規性欠如と判断され、これが実質上創作性のハードルとなります。純粋に機能に由来するデザインも登録不可であるため、機能的必然から容易に想定できる形状はそもそも保護対象外となります。総じて、カナダでは「新規であること」**が主要な登録要件であり、日本のような創作容易性(容易想到性)に関する独立の拒絶理由規定はありません。
新規性の具体的運用: カナダ知的財産庁(CIPO)は、出願された意匠について、同一または実質的に類似する意匠がカナダ国内外で公表されていないか審査します。ここでいう「実質的に類似」とは、意匠全体として見た場合に同じ視覚的印象を与える程度の類似を指し、細部に差異があっても全体として酷似していれば新規とは認められません。審査では、カナダ国内の登録・出願中意匠だけでなく、海外で公表された意匠も調査対象となります。この新規性要件を満たさない場合(既存意匠に埋没する場合)は登録が拒絶されます。
2. 出願手続(出願方法、必要書類、オンライン出願の可否)
出願の管轄と代理人: カナダで意匠登録を受けるには、カナダ知的財産庁(Canadian Intellectual Property Office, CIPO)に出願します。出願人は原則として意匠の創作者(またはその承継人)であり、創作者が他者のために意匠を創作した場合はその他者が出願人となります。日本企業がカナダに直接出願する場合、必ずしも現地代理人の起用は法的に義務付けられてはいません(代理人なしで自己出願することも制度上可能)。しかし、実務上は手続や審査対応が専門的であるためカナダの弁理士等の代理人に依頼することが強く推奨されています。代理人を任命する場合には委任状の提出は不要ですが、後述のようにCIPOへの届出(通知書)によって代理人を公式に指名する必要があります。外国企業(日本企業)が代理人無しで出願することも可能とはいえ、CIPOとのやりとりや通知は英語または仏語で行われ、期限管理も必要になるため、通常は現地代理人を選任するのが一般的です。
出願方法とオンライン出願: カナダへの意匠出願はオンライン出願と紙面提出の両方が可能です。CIPOが提供する電子出願システム(Industrial Design E-Services)を利用してウェブ上で手続可能であり、ユーザーフレンドリーなインターフェースが整備されています。オンライン出願では電子フォームに必要事項を入力し、図面データ等をアップロードして送信します。紙面での出願も受け付けられており、その場合は所定の宛先(CIPO意匠部門宛)に書類一式を郵送します。電子出願が推奨されますが、どちらの方法でも受理される点でオンライン出願「可」の体制です。
必要的記載事項: カナダ意匠出願には以下の内容が必須となります。
-
出願人(申請人)の氏名および郵便住所
CIPOとのやり取りには出願人または代理人の郵送先住所が必要です。代理人を任命した場合、庁からの通信は代理人宛に行われます。代理人を任命しない場合、出願人自身がCIPOとの連絡窓口となります。 -
完成品の名称(Name of the finished article)
出願書類には、その意匠が施される完成品の一般的な名称を記載します。これは消費者に一般に認識されている名称である必要があります(例えば「自動車」や「イス」等)。完成品の特定は意匠権の権利範囲(何の製品に対する意匠か)を画定する重要な情報です。 -
意匠の画像(図面または写真)
出願には少なくとも1枚以上の意匠の表現(再現図)が必要です。白黒またはカラーの線画(drawing)や写真で提出でき、製品のデザインを明瞭に示したものを添付します。図面・写真の要件については後述しますが、意匠の特徴を十分に開示する必要があり、そのため必要に応じて複数枚の図(各方向からの図など)を提出します。提出図には通し番号を付すことが推奨され、例えば「Fig.1(正面図)、Fig.2(側面図)…」等の説明を添えることが望ましいとされています。 -
手数料(出願料)
所定の出願料金を納付する必要があります。支払いはクレジットカード、銀行送金、小切手などが利用可能で、カナダドルでCIPOに納付します。料金額は時期によって改定されることがあり、CIPOサイト上で最新額が公開されています。
これらに加え、出願時には以下の事項を任意で含めることもできます。
-
優先権情報(Priority claim): パリ条約に基づく優先権を主張する場合は、その出願の出願日・国等を記載し、最先の優先日から6か月以内に請求する必要があります。カナダでは優先権主張は出願日から遅くとも登録決定前までに行えば認められますが、通常6か月を経過すると優先権享受はできません。
-
部分意匠に関する声明(Limitation statement): 提出図中のどの部分を権利としてクレームするか明確にするため、保護しない部分を破線で描き、または「意匠は製品の一部についてのみである」旨の記載を加えることができます。例えば「破線で示す部分は意匠の範囲に含まれない」といった声明を記すことで、権利範囲を限定できます。これは出願人の任意ですが、部分意匠を明確化する実務上重要なポイントです。
-
(簡単な)説明文: カナダでは意匠の説明(特徴説明)は任意となっています。多くの場合、図面で十分に特徴を示せれば説明文は省略されます。ただし図の各視点に対する図の名称(図面の説明)は付記することが望ましいとされます(例:「図1.1はメガネの正面図である」等)。
出願手続の流れ: 出願書類がCIPOに受理されると、まず方式的要件のチェックが行われます(願書に必要事項が揃っているか、所定の図があるか、料金が支払われているか等)。必要最低限の要件が満たされていれば、出願日(filing date)の確定通知(Notice of Filing)が送付され、出願番号が付与されます。仮に書類不備や情報欠落がある場合、CIPOから**補正要求(Omission Notice)**が出され、通常2か月以内に不足情報を補充する機会が与えられます。
方式審査をクリアすると、次に実体審査(substantive examination)が行われます。CIPOの審査官はまず出願意匠に適切な意匠分類(ロカルノ分類)を付与し、提出図・記事から意匠の範囲が明確か(図面に矛盾がないか、保護対象が明確に示されているか)を確認します。また、一つの出願が複数の意匠を含んでいないかもチェックされます。カナダでは原則として1出願1意匠ですが、「バリエーション」(variants)と位置付けられるごく近似した意匠であれば1件の出願にまとめることが許容されています。審査官は図面を検討し、もし出願中の複数デザインが「実質的に異ならない」範囲のバリエーションであれば一出願で受け付け、そうでなければ出願の分割・補正を求めることになります。
意匠の範囲が確定すると、世界的な先行意匠調査が行われます。審査官はカナダ国内の既登録・出願中意匠データベースのみならず、海外の公報データベースも検索し、同一または類似のデザインが公開済みでないか調査します。その上で新規性の判断が下され、登録適否が決定されます。
審査結果への対応: 実体審査の結果、登録可能と判断されれば速やかに登録処分へと進みます。一方、拒絶理由(欠陥)がある場合、審査報告書(Examination Report)という形で拒絶理由通知が送付されます。出願人(または代理人)は通常3か月以内に応答する必要があり、指摘に対し意見書で反論するか、場合によっては図面やクレームの補正を行います。ただし、この補正によって出願時の意匠の範囲を実質的に変更することはできません(大きくデザインを変えるような補正は不許可)。審査官との応答を経てもなお拒絶理由が解消しない場合、最終的に最終審査報告(Final Examination Report)が発行され、出願人に最後の反論機会が与えられます。それでも審査官が登録不可と判断すれば拒絶査定となり、出願は拒絶されます。その際、出願人は連邦裁判所(Federal Court)に司法審査を求めて不服申し立てを行うことができます。
登録と公開: 登録が認められる場合、CIPOは意匠登録証(Notice of Industrial Design Registration)を発行し、登録番号・登録日などを通知します。カナダの意匠出願は、出願から登録まで非公開で進みます。ただし出願日(または優先日)から30か月経過時点までに未登録の場合は、その時点で出願内容が自動的に公開されます(30か月以内に登録されれば公開は登録時点)。出願人の戦略によっては、製品発売とタイミングを合わせるため登録をあえて遅らせることも可能です。実際、CIPOに登録の遅延(delay of registration)を申請すれば、最長で30か月目まで登録処分を延期することができます。逆に早期登録を望む場合、審査促進を申請する制度もあります。カナダ制度には公告・異議申立て制度はなく、第三者が出願段階で意見を述べる仕組みはありません。したがって、登録後に異議がある場合は利害関係人が無効手続(後述)をとることになります。
以上が出願から登録までの大まかな手続の流れです。平均的な処理期間は、通常の国内出願で約18か月、ハーグ経由の国際出願では約11か月とされています。日本企業が出願する際は、電子出願を活用しつつ現地代理人と協力して、期限内の応答・適切な補正を行うことが重要です。
3. 保護対象
保護される意匠の範囲: カナダ意匠法に基づき保護されるのは、前述したように製品(完成品)の見た目の特徴です。立体的造形(形状・輪郭)や平面的な図柄・配色といった視覚的要素が対象となり、それらが製品に適用されたものが意匠として登録し得ます。保護対象となる完成品は、有形の工業製品全般を指し、日用品から機械装置、電子機器の外観まで多岐にわたります。例えば、自動車のボンネットの独特な曲面形状、スマートフォン画面上のアイコン配置やGUIデザイン、靴の模様や形状など、「製品の審美的デザイン」が該当します。カナダでは製品全体だけでなく部品や部分についても意匠権を取得可能であり、製品の一部の形状のみを抽出して権利化すること(部分意匠)も認められています。これは、日本の部分意匠制度と類似の考え方で、製品の一部が新規独自であればその部分のみの権利取得が可能です。
GUI・画面デザイン: 現代のデザイン保護のトピックとして、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)やアイコン等の画面上の意匠もカナダでは保護し得ます。画面表示自体は無形ですが、それがデバイスという完成品に表示される視覚的要素であれば意匠法の対象となります。例えばスマートフォンのホーム画面のレイアウトやアニメーションするアイコンデザインなども、「電子機器の表示画面に適用された装飾」として登録可能です。もっとも、それ自体が独立した完成品ではないため、何らかの製品に付随して表示されることが要件となります。近年、日本でもGUI画像や画面遷移のデザインが意匠登録可能になりましたが、カナダでも同様の傾向でGUIが保護対象に含まれています(ただし単なる美術画像で製品と関連しないものは保護対象外)。
保護されないもの: カナダ意匠で保護されない対象も明確にされています。まず、機能そのものや機能から必然的に導かれる形状は意匠権で保護できません。例えば、ある部品の形状が純粋に機能上の要請(性能や結合要件など)だけで決まる場合、その形状は「美的選択の余地がない」ため意匠とは認められません。法律上、「実用品の純粋に機能に由来する特徴」は登録不可とされています(いわゆる機能的形状の排除)。また公序良俗違反のデザイン(反社会的なシンボル等)は登録が拒絶されます。さらに、アイデア段階のもの、製品のアイデアコンセプト自体や、製法、材料など見た目以外の要素は意匠権では一切カバーされません。例えば「この製品はカーボン素材でできている」という点や「折りたたみ機構」という機能上の特徴は意匠の保護範囲には入らないということです。意匠権はあくまで「視覚美」に関する権利であり、他の知的財産(発明特許、商標、著作権等)とは守備範囲が異なる点に注意が必要です。
建築物・内装の扱い: なお、カナダでは意匠法上「完成品(finished article)」の定義に**不動産(建築物や建築物内の内装)**は含まれないと解されます。伝統的に、建物そのものは工業的に量産される「製品」ではないため、建築物の外観デザインや室内装飾デザインはカナダ意匠制度では保護対象外です(意匠権の対象とはみなされません)。一方、日本では2019年改正により建築物のデザインや内装も意匠登録が可能となりました。この点は両国制度の相違として認識すべき事項です。例えば店舗の内装コンセプトや建築ファサードのデザインは、日本では意匠権取得できますが、カナダでは意匠権の直接の保護対象とはなりません(別途著作権や商標の枠組みで検討することになります)。
複数デザインの保護: 一つの製品に複数のバリエーションデザインが考えられる場合、カナダでは類似するバリエーションは単一出願内で同時に保護できますが、それ以外は別出願が必要です(※同一または近似意匠はvariantsとして一括出願可)。日本では関連意匠制度があり、登録後でも10年以内であれば類似意匠を別途出願して保護することができます。カナダには日本の関連意匠に相当する制度はありません。そのため、カナダでシリーズデザインを保護するには、出願時にあらかじめ全バリエーションを盛り込む(あるいは個別に同時期に出願する)必要があります。出願後にデザイン変更版を追加で保護することは困難なので、この点は日本との大きな違いであり、日本企業はカナダ出願戦略として初期段階で保護したいバリエーションを網羅する計画が重要です。
4. 新規性喪失の例外制度
カナダにも新規性喪失の例外(グレースピリオド)が設けられています。出願人(デザイナー)自身が意図せずまたは製品発表等の目的で自らデザインを公開してしまった場合でも、その公開日から12か月以内であれば、その公開は当該意匠の新規性を害しないとする救済措置です。具体的には、出願人またはその権利承継人に由来する公表(applicant-derived disclosure)があっても、最初の公開日から1年以内にカナダ出願(または優先出願)すれば、その公開情報は先行意匠とみなされず、新規性要件を満たすことができます。言い換えれば、デザイナー自身の公開について一年間の猶予が与えられているということです。
この例外適用には、公開が出願人自身によるもの、もしくは出願人から情報を得た第三者による公開であることが条件と解されます。競合他社など全く無関係の第三者が独自に同一デザインを公開していた場合はグレースピリオドの適用対象外であり、その公開は新規性を奪う要因となります(真の意味での新規性喪失)ので注意が必要です。
カナダのグレースピリオドは期間が12か月であり、これは現在の日本の制度と同じ長さです。日本でも2018年の法改正以降、意匠の新規性例外期間は従来の6か月から12か月に延長されました。したがって期間の点では両国とも1年の猶予があります。ただし、適用手続には若干の違いがあります。日本では、出願人が自らの公開に対する例外適用を受けるには、出願時に「新規性喪失の例外の適用を受けたい」旨を願書で申告し、所定の書面や証明資料を出願から30日以内に提出することが求められます(これを失念すると適用されません)。一方、カナダでは特別な届出手続きを要さず、法律上自動的に例外が認められる運用です。つまり審査官は、もし出願から遡って1年以内の公開物が見つかった場合、その公開者が出願人本人であると判明すればそれを無視して新規性を判断します。とはいえ、公開者が出願人と同一かどうか等は審査官には自明でない場合もあるため、実務上は出願時に「◯年◯月◯日に自社がこのデザインをプレス発表済み。本出願はその公開から◯ヶ月以内。」といったメモを添える例もあります。公式には不要ですが、審査上の誤解を防ぐ工夫です。
なお、優先権を主張する場合、グレースピリオドの起算点は優先日基準となります。例えば最初の公開から1年以内に日本に出願し、その出願の優先権を主張してカナダにさらに6か月以内に出願した場合、カナダでは優先日を基準に公開から1年以内か判定します。この点も日本とほぼ同様の扱いです。
総じて、カナダでは出願人に起因する公表であれば12ヶ月間は自己侵害にならないという寛容措置が取られており、展示会や製品テストマーケティングなどで先行公開してしまった場合でも、迅速に1年内に出願すれば救済可能です。もっとも競合他社による模倣が発生するリスクや、公開から出願までの間に第三者が別途出願してしまうリスクもあるため、グレースピリオドをあてにせずできるだけ早期に出願するのが望ましい点は言うまでもありません。
5. 委任状の要否
カナダでは意匠出願時に委任状(Power of Attorney)の提出は不要です。出願人が代理人を指定する場合でも、署名済みの委任状を提出する義務はなく、代理人選任届(Notice of Appointment of Agent)を提出して代理人の氏名・住所を届出すれば足ります。CIPOは届出があった代理人のみからの連絡・手続きを受け付け、出願人本人からの直接の指示は原則無視される運用です(代理人二重指定による混乱を避けるため)。したがって、日本のように代表者の捺印・署名入りの委任状書面を取り交わす手間が省け、手続きが簡便になっています。
実務的には、カナダの現地代理人(弁理士)は出願時に自身を代理人として届出し、そのまま代理業務を行うケースが多いです。「No Power of Attorney is required」とされる通り、CIPOに対して委任状を郵送・提出するプロセス自体が存在しません。ただし、代理人は出願人から正式に依頼を受けていることが前提であるため、法的には出願人と代理人との間での委任関係契約は当然必要です。カナダではその証明を庁に示すことを要求していないだけで、万一代理権に争いが生じた場合に備え、代理人側は内部で委任状を保管しておくことが一般には推奨されています。
一方、日本では意匠出願に際して代理人を立てる場合、委任状の提出が基本的に必要です。特に外国企業が日本の弁理士に依頼して出願する場合、JPO(日本特許庁)に対し所定形式の委任状(英語も可)を提出する慣行があります。日本では出願と同時またはその後一定期間内に委任状を提出しないと手続補正指令が来る場合があり、委任状不備のままでは審査が進まない可能性があります。カナダではそのような煩雑さがないため、迅速な出願手続が可能となっています。この点は実務上の大きな違いであり、日本企業がカナダに直接出願する際には委任状書類を用意する必要がないことを覚えておくとよいでしょう(依頼から出願までのリードタイム短縮につながります)。
6. 図面・写真要件(形式、視点、数量など)
提出形式: カナダ意匠出願では、図面(ラインドローイング)でも写真でも、いずれの形式で提出しても構いません。白黒図面が典型的ですが、デザインの特徴を明確に示すためであればカラー図や高解像度の写真も受け付けられます。図面の場合、製品の輪郭や模様を正確に描画した線図が望ましく、写真の場合も背景を消すなどして製品の外観がはっきり判別できるものが必要です。いずれの場合も、提出された図面・写真に基づいてしか意匠権の範囲は確定しないため、出願人はクレームしたい視覚上の特徴を余すところなく図示することが重要です。
必要視点と図数: 最低1枚の図が必須とされていますが、実務上は通常、製品の全貌を理解できるよう複数の角度からの図を提出します。典型的には6面図(正面・背面・左右側面・上面・下面)および斜視図を揃えると望ましいですが、必ずしも6方向全てが要求されるわけではありません。日本ではかつて六面図の提出が強く求められていましたが、カナダでは当初から「十分な開示」のために必要な枚数を出せばよいとされています。例えば対象が平面的デザインの場合は正面図1枚で足りることもありますし、対称形状なら片側だけ示せば足りる場合もあります。要は、意匠の形態を第三者が再現できる程度に明確に表現できているかが基準です。出願人は不足の無いよう、必要と思われる視点を網羅することが推奨されます。
CIPOは提出図に図番号を付すことを推奨しています。一つの出願に複数図がある場合は、「1.1, 1.2, 1.3,...」のように図番号を付けたり、単に「Fig.1, Fig.2,...」と番号を振る方法が案内されています。また各図に簡単な図の説明(例:「Fig.1は完成品の斜視図」「Fig.2は正面図」等)を付すことで、審査官や第三者にとって理解しやすくなります。これらは義務ではありませんが、出願人に有利な補助情報となります。
部分的な破線等の利用: カナダでは、図面中で破線(点線)を用いることでその部分を「意匠の範囲に含まない」ことを表現できます。法令上も、破線で描かれた部分は出願意匠には含まれないものとみなす旨が規定されています。したがって、例えば製品全体の中の特定部分のみを権利化したい場合、その他の部分を破線で描けば、その破線部分は登録意匠の構成には入らず、実質的に部分意匠として扱われます。また、可動部分の一部だけ長さが可変であることを示す場合などに「点線+切欠き線(break lines)」で示す手法も取られます。このように、破線やぼかし等で非本質部分を描くテクニックが認められており、出願人は権利範囲を視覚的に調整することが可能です。他方、実線で描かれた部分は意匠権で独占する部分となるため、そちらに新規性・独自性が必要です。日本でも破線による非部分の表示は一般的で、考え方は共通しています。
図面の品質: 提出する図面・写真は意匠の特徴を明確かつ正確に識別できる品質が要求されます。不鮮明だったり、小さ過ぎたりすると審査で補正を求められる可能性があります。また図同士で不整合(例えば正面図と側面図で形状が食い違う等)がある場合も拒絶理由となり得ます。そのため、図面作成段階で整合性・明瞭性に十分注意する必要があります。カナダでは図面の線の太さや陰影の付け方について細かな規則はありませんが、極端なデフォルメや影の多用で形状認識が妨げられるような場合は問題視されます。基本的に第三者がその図面から製品の形を理解・再現できることが重要です。
写真提出時の注意: 写真を使う場合、背景や不要な部分を除去し製品だけがはっきりと写るようにします。写真のコントラストや解像度が不足していると「図面の品質不備」で拒絶理由になることがあります。また複数の写真で色味や明るさが極端に異なると同一製品に見えない恐れがあるため、統一感のある画像提出が推奨されます。この点、カナダはカラー写真も受け付けていますが、白黒に統一した方が各図間の一貫性が保ちやすいでしょう(色そのものを権利要素に含めたい場合は別ですが)。
日本との比較: 日本では以前は六面図提出が事実上必須で欠けていると補正指令となりましたが、2019年の運用緩和で必ずしも6図すべて不要となりケースバイケースになりました。とはいえ現在でも多くの場合、審査基準上6面の図またはそれに代わる充分な図面を要求される点で、日本はカナダよりフォーマルです。カナダでは一枚の図だけでも受理され得ますが、日本では出願後に審査官から不足図面を求められる可能性が高いです。また、日本出願では「意匠に係る物品の説明」「意匠の創作に係る事項」等を記載する欄がありますが、カナダではそうした文章情報は原則審査や権利範囲には影響しません。このように図面中心主義である点は共通しつつも、提出図面の形式要件はカナダの方が柔軟と言えます。日本企業がカナダへ出願する場合、日頃の日本での図面作成ノウハウを活かしつつ、カナダの基準(不明瞭さえなければ形式自由)に合わせて必要十分な図を提出すれば問題ないでしょう。
7. 保護期間(起算点、更新の可否)
権利発生の起点: カナダの意匠権(industrial design registration)は登録日に発生します。特許のような出願日基準ではなく、登録完了をもって法的効力を生じる点に注意が必要です。出願から登録までは権利は未成立であり、その期間中に他人が同じデザインを模倣しても正式な権利侵害とはなりません(ただし後で登録された場合、登録日以降の行為には権利行使可能)。この取り扱いは日本の意匠法と同様です(日本も意匠権は設定登録日に発生)。
存続期間: 2018年改正以降、カナダ意匠権の存続期間は出願日から最長15年と定められています。ただし、少なくとも登録日から10年間は保護されるよう期間が調整されます。具体的には、「登録日後10年」と「出願日後15年」のいずれか遅い日まで権利が存続します。例えば、出願から1年で登録に至った場合、出願日から15年後が満了となり、これは登録日から14年後程度になります。一方、審査長期化等で出願から7年後に登録になった場合は、登録日から10年後が出願日から17年後に相当し、15年ルールを超えます。この場合は遅い方である登録後10年(=出願後17年)が適用され、結果的に15年を超える期間が与えられます。このように、審査遅延による実質保護期間の減少を補填する仕組みです。もっとも大半のケースでは出願~登録が数年以内に完了するため、実質的には「出願日から15年」が標準の保護期間となります。
維持料(メンテナンスフィー): カナダでは意匠権の存続期間中に1度だけ維持年金の支払いが必要です。具体的には、登録日から5年以内に所定の維持料を納付する必要があります。この維持料支払いによって、前述の最大存続期間(10年~15年)まで権利を維持できます。言い換えると、登録後最初の5年間は無条件で権利が有効ですが、5年経過時までに維持料を払わなければ権利は5年で失効します。維持料には6か月の猶予期間があり、期限を過ぎても6ヶ月以内であれば追加の延滞料金を支払って納付可能です。この期間を過ぎると権利は完全に消滅します。
維持料は一度支払えば残余期間すべて有効となります。例えば登録5年目に維持料を納付すれば、その後は最終満了日(出願日から15年又は登録日から10年の遅い方)まで追加の費用負担なく権利が続きます。カナダではこの1回の維持料のみで更新(延長)の制度はなく、15年を超えて権利期間を延ばすことはできません。また意匠権に関して年次の維持年金を毎年払う必要もありません(5年目の一度きりです)。料金額は比較的低額に設定されていますが、未納により5年で権利失効しないよう注意が必要です。
日本の保護期間との比較: 日本の意匠権の存続期間は、2019年改正後の現行法では出願日から25年と世界的にも長期になっています(改正前は登録日から20年でしたが延長されました)。したがって期間だけ見ると、日本はカナダより10年も長い保護を与えていることになります。日本ではこの25年期間を延長することはできず、満了後は公有となります。カナダ同様、延長更新制度はありません。
維持費用について、日本では**毎年の年金(登録料)**の納付が必要です。意匠登録時に一括で全期間分を支払うのではなく、特許と同様に年次ベースで維持費を払っていく仕組みです(日本では意匠登録料として初年度から第3年度までを一括納付し、その後4年目以降は年ごとまたは数年まとめて前払いする形を取ります)。一方カナダは5年目に一度きりの支払いなので、維持の手間は日本より少ないです。ただしカナダはそもそもの保護期間が短いため、長期保護が必要な場合は別の知財(例えば商標による形状商標登録など)での保護検討が必要となるでしょう。
なお、カナダでは意匠権満了後に延長できない点は前述のとおりですが、日本でも同様に延長制度はありません(特許のような医薬延長も意匠には存在しません)。したがって保護期間満了後は自由利用となります。存続期間が日本とカナダで大きく異なるため、日本企業は製品のライフサイクルに合わせてカナダでは権利切れが早く来ることを織り込んだ戦略が必要です。例えば、日本では25年保護されるデザインも、カナダでは15年で権利消滅するため、その後は模倣品が出回り得ることになります。重要デザインについてカナダで長く独占したい場合は、意匠以外の権利(商標で立体商標登録する、著作権性があれば主張する等)も併用検討するといった対策が考えられます。
8. 侵害訴訟制度(立証方法、救済手段)
意匠権侵害の判断基準: カナダにおける意匠権侵害は、登録意匠と同一または実質的に類似する意匠が登録意匠と同じ種類の製品に無断で施されている場合に成立します。意匠権者(または専用実施権者)は、自らの登録意匠が付された製品やそれとほとんど変わらないデザインの製品について、以下の行為を禁止する権利を有します。
-
製造(making): 登録意匠と同一・類似のデザインを製品に適用して製造する行為
-
販売・頒布(selling, offering for sale, renting): そのような製品を販売、レンタル、または販売目的で陳列する行為
-
輸入(importing for commercial purposes): 商業目的でそのような製品をカナダ国内に輸入する行為
以上の行為を権利者の許可なく行えば意匠権侵害となります。立証にあたっては、被疑製品のデザインが登録意匠と比較して視覚的に実質同一か(not differing substantially)を示すことが中心となります。カナダでは特に「目視による全体的な類似」テストが用いられ、専門家の鑑定意見などより裁判官が肉眼で見た印象が重視されます。もっとも技術的・美術的専門家の証言が認められる場合もあり、裁判では提出図面や写真を並べての詳細な比較が行われます。
被疑者側(被告)は、デザインが似ていないこと(non-infringement)を主張するのが典型的な抗弁です。すなわち、「自社製品の意匠は登録意匠とは実質的に異なる」という点を図面や現物で示します。また、被疑製品が登録意匠の指定物品と異なる種類の製品である場合も侵害は成立しません(例えば登録意匠は「椅子」に対するものだが被疑品は「テーブル」である、等)。その他、そもそも意匠権が無効であること(後述)や、権利者が正当な権利者でないこと(権利帰属の争い)なども抗弁として主張され得ます。
管轄と手続: 意匠権侵害訴訟は基本的に民事訴訟として提起されます。カナダでは連邦法に基づく知的財産権侵害訴訟は、**連邦裁判所(Federal Court)**または各州の高等裁判所(州裁判所)で扱うことが可能です。通常、侵害行為が複数の州にまたがる場合や全国的な差止命令が欲しい場合は連邦裁判所に提起されます。一方、例えば意匠権侵害と同時に不正競争行為(営業上の表示の無断使用など)も問題とする場合は州裁判所にまとめて提起することもあります。いずれにせよ、権利者は侵害が発生していると判断した際、差止や損害賠償を求めて訴訟を起こすことができます。
訴訟では、侵害の成立および意匠権の有効性が争点となります。これらは通常同一訴訟手続内で審理されます。すなわち、被告が「登録意匠は新規性欠如で無効」と反論すれば、裁判所は侵害と有効性をまとめて判断します(カナダでは意匠登録に対する異議制度がないため、無効主張は抗弁または別途の無効審判請求として行われます)。裁判手続は、当事者間の訴状・答弁書提出(pleadings)、証拠開示(discovery)、証人・鑑定人の証言など通常の民事訴訟プロセスを経て進行します。前段階で和解交渉が行われることも多いです。
立証方法: 原告(意匠権者)は、被疑製品を入手して登録意匠の図面と並べた比較図などを作成し、視覚的類似性を主張立証します。鑑定人(例えば工業デザイナー等)の「両デザインは実質同じ」との意見書が提出される場合もあります。一方被告は逆に「相違点」を詳細に指摘し、一般需要者の目から見て別の印象を与えると主張します。カナダの裁判所は、意匠全体の美感的印象に基づき侵害の有無を判断します。その際、意匠の一部が機能的形状である場合、その部分は類否判断で考慮されないこともあります(機能部分は保護対象でないため)。実質的相違が一箇所でもあれば非侵害とされる可能性がありますが、全体として些末な差異しかない場合は侵害となります。
救済手段: 権利者が勝訴した場合、カナダでは民事救済として以下のような措置が認められます。
-
差止命令(Injunction): 裁判所は被告に対し、侵害行為の停止を命じることができます。仮処分的な仮差止(臨時の差止命令)も理論上可能ですが、要件(深刻な損害の立証等)が厳しく、実際にはほとんど認められていません。最終的な恒久的差止は侵害成立時には通常発令され、被告は将来にわたりそのデザインの製造販売を禁じられます。
-
損害賠償(Damages)または利益の吐き出し(Accounting of Profits): 権利者が被った損害の賠償が命じられます。損害額算定は、権利者が侵害によって失った利益(販売機会の喪失による利益減など)を基準にします。また代替的に不当利得返還として、被告が侵害品の販売で得た利益相当額を吐き出させる救済も選択可能です。どちらか有利な方を原告が選べますが、二重取りはできません。カナダでは訴訟手続上、侵害・有効性と損害額は原則同一手続で審理されます(ただし双方合意等により損害額だけ後で審理を分離することも可能)。
-
懲罰的賠償(Punitive damages): 被告の行為が特に悪質な場合、懲罰的(制裁的)損害賠償が科されることもあります。例えば意図的かつ計画的に長期間にわたり権利侵害を行っていたようなケースでは、通常の損害賠償額に加えて罰金的な金額が上乗せされ得ます。これはカナダの法律で認められる例外的措置ですが、知財侵害訴訟でも適用例があります。
-
違法品の廃棄・引渡し(Delivery up or Destruction): 被告の手元にある侵害品やその製造用型などについて、裁判所は権利者への引渡し又は破壊処分を命じることができます。これにより市場から侵害品を排除し、再流通を防止します。
-
訴訟費用の回収(Cost recovery): 勝訴当事者は敗訴当事者に対し一定額の弁護士費用や裁判費用の支払いを求めることができます。連邦裁判所では通常、勝者への一部費用償還が認められており、商慣習的に実費の25~50%程度が相手方負担とされることがあります。もっとも全額賄われるわけではなく、多くの場合相当部分は自己負担となります。
立証上の留意点: カナダ意匠権侵害訴訟では、被告が「善意の侵害者(innocent infringer)」だった場合、損害賠償が制限されるという特有の規定があります。具体的には、被告が侵害当時その意匠が登録されていることを知らず、かつ知らなかったことについて合理的理由がある場合(例えば製品にⒹマークや権利者名の表示が無く認識できなかった等)、裁判所は損害賠償または利益返還を認めず差止のみの救済に留めることができます。言い換えれば、悪意なくデザインを使ってしまった者には金銭賠償責任を負わせない可能性があるのです。このため、権利者側は自社製品にⒹマークと権利者名を表示する(マーキング)ことが推奨されています。適切な表示があれば被告は「知らなかった」と主張できなくなり、賠償請求が通りやすくなります。日本にはこのような善意侵害者保護規定はなく、知らずに侵害していた場合でも民事賠償責任を負います。カナダ特有の留意点として、日本企業も製品マーキングや周知に努め、故意でないとの逃げ道を与えないことが戦略上重要です。
時効・除斥期間: カナダ意匠権侵害については、侵害行為から3年以上経過した分は救済を受けられないと法律で定められています。これは時効の一種で、訴訟提起前の過去3年分までしか損害賠償等請求ができないことを意味します。したがって、侵害に気付いたら悠長に構えていると、それ以前の侵害については請求権が失われてしまいます。速やかな権利行使が求められる所以です。日本では民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権は3年(2020年改正民法で5年に延長)ですが、意匠権侵害もそれに準じるとされます。また日本は刑事告訴も6ヶ月の親告罪告訴期間があります。カナダでは刑事が無い代わりに民事上3年制限が明示されていると言えます。
刑事罰の有無: カナダには意匠権侵害に対する刑事罰規定がありません。意匠権はあくまで民事上の権利であり、警察が摘発したり検察が起訴する類の犯罪行為とは位置付けられていません。したがって侵害者に科されるのは民事上の損害賠償等に限られ、懲役刑や罰金刑といった刑事罰はありません。これはカナダのみならず米国など多くの国で同様ですが、日本との比較では大きな違いです。日本では意匠権侵害は刑事罰の対象となり得ます。日本意匠法69条は、意匠権または専用実施権を侵害した者に対し「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)」を科し得ると規定しています。さらに法人が従業員の侵害行為を行わせていた場合、法人にも罰金(最大3億円)が科される両罰規定もあります。このように日本では悪質な意匠権侵害は刑事告訴されうる重い犯罪なのに対し、カナダでは民事救済のみです。従ってカナダで侵害対応する際は民事訴訟が唯一の手段となる点を認識し、刑事的な威嚇(例えば警察への通報)といったオプションは基本的に無いことに留意してください。
9. 行政摘発制度の有無
税関など行政的な差止制度: カナダの意匠制度には行政機関による侵害品摘発の仕組みは存在しません。例えば商標権では税関(カナダ国境サービス庁)が偽ブランド品を差し止める制度がありますが、意匠権に関しては税関による輸入差止め制度が法令上用意されていないのが現状です。カナダ意匠法や関税法には、意匠権を根拠に税関が職権で貨物を押収できる規定がありません。そのため、海外から意匠侵害品が輸入されていても、税関はそれを知的財産侵害品として差し止めできず、権利者自らが民事訴訟等で対応する必要があります。これは日本企業にとって注意が必要な点です。カナダ市場に模倣品が流入しても、日本のように税関に申し立てて行政的に止める制度が無いため、直接裁判所の差止命令を得て輸入業者に提示し、差し止めるなどの手段をとらねばなりません。
警察等の取締: 前述の通り、カナダでは意匠侵害は犯罪ではないため、警察が捜査して摘発することもありません。意匠については行政・刑事の両面で公的関与が無いため、100%民事上の自己救済手段(訴訟や差止請求)に依存することになります。意匠権者は自ら市場を監視し、侵害品を見つけたら民事措置を取る以外にありません。CIPO(知財庁)も「我々は市場監視や権利行使は行わない」と明言しており、権利者自身が積極的に動く必要があります。
日本の状況: これに対し日本では行政的な模倣品取締制度が存在します。日本の税関(税関庁)では、商標・著作権はもちろん、特許・意匠についても輸入差止申立制度が運用されています。意匠権者は税関長に対し、自分の意匠権に基づき侵害が疑われる輸入品の差止めを申請できます。税関は届出に基づき輸入貨物を監視し、権利侵害の疑いがある場合に通関保留し、権利者と輸入者双方の意見陳述を経て没収・廃棄等の措置を取ります。このような水際措置により、日本では侵害品の流通を行政が一定程度防ぐ役割を担っています。また、日本では意匠権侵害が刑事罰の対象であるため、悪質な模倣業者について警察への被害届提出→摘発・送致→起訴といった刑事手続での摘発も可能です。
要するに、日本: 行政(税関)+刑事警察による取締可能、カナダ: 行政・刑事の公的取締なしという対照的な構図です。日本企業は、カナダで模倣品問題が発生した際、税関頼みや刑事訴追はできず自力で民事対応せねばならない点を踏まえて現地対策を練る必要があります。例えば、主要港湾の業者に警告レターを送る、民事訴訟の仮処分を素早く取得して輸入差止めに使う等、民事訴訟を軸とした戦略が不可欠です。日本とは異なる法執行環境であることを認識し、現地弁護士とも協力して適切な実務対応を行うことが求められます。
10. ハーグ制度との関係(国際出願の可否、必要書類、手続上の留意点)
国際登録出願の可否: カナダは2018年11月5日にジュネーブ改正ハーグ協定(Hague Agreement)に加盟しており、ハーグ国際意匠登録制度を利用した国際出願が可能です。つまり、日本企業は一つの英文もしくは仏文の国際意匠出願をWIPOに提出し、指定国としてカナダを選択することで、カナダ国内に直接出願することなく意匠権取得手続を行えます。ハーグ出願では1件で最大100意匠まで(ただし全て同一ロカルノ分類クラス内)登録可能ですが、カナダを指定する場合も同様です。例えば、同一分類に属する家具デザイン10点をまとめて国際出願し、カナダとEUと米国を同時指定するといったことが可能です。カナダを指定国に含めることにより、CIPOがその国際登録の写しを受領し、それがカナダ出願として扱われます。
必要書類・情報: ハーグ国際出願自体の要件は国際ルールで決まっており、基本的には出願人の氏名・住所、意匠の図面/写真(各意匠につき1以上)、製品の名称(ロカルノ分類と関連付けて記載)、指定国、所定手数料です。カナダを指定する際に特別に追加すべき書類はありません。例えば委任状や現地代理人情報も不要(国際出願時点では代理人はWIPOへの代理人で足ります)です。日本企業が国際出願を利用する場合、英語またはフランス語(もしくはスペイン語)で手続きを行う必要がありますが、日本特許庁経由でハーグ出願をすることも可能です。必要図面・写真については、各指定国の基準(解像度や視点数など)を満たすよう用意するのが望ましいです。カナダ指定の場合、先述のとおり最低1図でよいなど柔軟な基準ですが、他国(例えば米国は線画のみ要求)も考慮して作成するのが一般的です。
手続の流れ: 国際出願がWIPOで方式審査を経て登録・公報発行されると、その情報が各指定国知財庁に送付されます。カナダ知財庁(CIPO)は国際登録の写しを受領すると、通常の国内出願と同様に実体審査を行います。審査内容・基準は国内出願と全く同じで、新規性や非機能性、図面の明確さなどをチェックします。仮に何らかの拒絶理由があれば、「拒絶通報(Notification of Refusal)」をWIPO経由で出願人(ホルダー)に通知します。この拒絶通報にはCIPO作成の審査報告が添付され、具体的な拒絶理由(例えば「図面が不明瞭」「この先行デザインに類似」等)が示されます。
出願人は、この拒絶理由に対し直接CIPOに応答する必要があります。国際出願の場合でも、各国審査への対応はその国ごとに行うルールのため、カナダ拒絶に対しては出願人自身か現地代理人がCIPOへ意見書・補正書を提出します。応答期間は原則通知日から3か月です。多くの場合、言語や法制度の壁からカナダ現地代理人に依頼して対応するのが実務的です。応答後、審査官が再審し、問題が解決すれば**登録許可(Statement of Grant of Protection)がWIPO経由で通知されます。もし最終まで不許可の場合は最終拒絶(Refusal)**となり、出願(国際登録のカナダ指定部分)は拒絶確定します。拒絶確定した場合、国際登録そのものは他国分は有効ですが、カナダ指定部分だけが無効となる形になります。
登録・権利発生: カナダでハーグ経由出願が登録に至った場合、CIPOは保護付与宣言(Statement of Grant of Protection)を発行しWIPOに送ります。その日がカナダでの登録日となり、権利が発生します。ハーグ国際登録の原簿にもカナダが保護付与した旨記録されます。権利内容は国内出願と同一で、国際登録番号に対応するカナダ登録番号が付与されます。なお、ハーグ出願では公開は国際公報で既に行われているため、カナダ独自の公開はありません(通知がそのまま登録告知となります)。
存続期間と更新: ハーグ経由で得たカナダ意匠権の存続期間も、国内出願と同じく出願日(国際登録日)から15年以内です。登録日から起算しても最低10年は保証されます。維持費用の考え方が少し特殊で、ハーグ国際登録自体は5年ごとにWIPOで更新料を払って存続させますが、カナダに関しては最初の5年更新料を払えばそれ以降のカナダ維持料は不要となります。具体的には、国際登録の日から5年以内に一度WIPOに更新料を払い国際登録を存続させれば、CIPOへの5年目維持料もそれに含まれる扱いとなり、以降15年まで追加でカナダに支払う必要はありません。ただしWIPOには10年目・15年目…と5年毎に国際登録更新手数料は支払い続ける必要があります(カナダ分は初回以降ゼロまたは極少額)。この点、ハーグ経由でも維持管理上の手続は残るため、更新期限管理を怠らないようにする必要があります。
手続上の留意点: 日本企業がカナダ指定でハーグ出願を行う際の注意点として、まず図面要件を各指定国に合わせて満たすことが挙げられます。カナダは図の形式自由度が高いですが、同じハーグ出願で例えば米国を指定すると線画のみ許容など厳しい要件があります。そのため各国の最も厳しい要件に合わせた図面作成をするのが一般的です。次に、カナダで拒絶理由が出た場合の**応答期間(3か月)**が比較的短いので、迅速に現地代理人に連絡して対応策を練る必要があります。ハーグ出願では出願時に現地代理人は不要ですが、拒絶応答段階でほぼ必須となるため、あらかじめ信頼できるカナダ代理人を確保しておくと安心です。
また、多意匠一括出願について、カナダ国内出願ではvariants以外は不可でしたが、ハーグ経由では同一クラス内であれば異なるデザインも一括処理されます。CIPOはそれぞれのデザインを個別に審査し、問題なければ全て登録、ある一部に問題があればそのデザインに限り拒絶通報する運用です。従って、出願人としては一括出願の各デザインごとに拒絶対応が必要になる可能性がある点を認識しておくべきです。必要なら国際登録を分割(designatable権利分割)して対処することも検討します。
最後に、日本も既にハーグ加盟国であり、日本企業にとってハーグを使ったカナダ意匠取得は有力な選択肢です。直接カナダに出願する方法(パリ経由の国内出願)と比較して、ハーグを使うメリットとしては一出願で多国同時手続・一括管理できる点、デザインの公開タイミングを一元管理できる点等が挙げられます。一方デメリットは拒絶対応で結局各国代理人費用が発生する可能性がある点や、国際出願手数料がかさむ場合がある点です。カナダ単独であれば直接出願でもよいですが、他国もまとめて取るならハーグ経由が便利でしょう。いずれの場合も、日本の意匠制度と大きく異なる部分(維持料時期や権利期間など)があるため、本報告書全体で述べたポイントを踏まえて適切な実務対応を行うことが大切です。
日本の意匠制度との比較表
日本の意匠制度とカナダの制度の主な相違点を以下の表にまとめました。制度上の違いに加え、実務対応上の注意点も付記しています。
| 項目 | カナダの意匠制度 | 日本の意匠制度 |
|---|---|---|
| 主管官庁 | カナダ知的財産庁(CIPO)による登録制度。異議申立て制度はなし(無効は裁判で争う)。 | 日本特許庁(JPO)による登録制度。異議申立て制度はなし(登録後は無効審判で争う)。 |
| 意匠の定義 | 物品(完成品)の見た目(視覚的特徴)に係るデザイン(形状・模様・色彩)。機能のみの形状は不可。 | 物品(改正後は建築物・画像含む)の形状・模様・色彩(または組合せ)。機能的形状は不可(意匠法3条2項)。建築物・内装も保護(2019改正)。 |
| 部分意匠の保護 | 可能(完成品の一部でも出願可)。破線等で非請求部分を示すことで部分意匠を表現。 | 可能(部分意匠制度あり)。一部を意匠として特定可(点線で表示)。2005年導入、日本でも一般的。 |
| 登録要件 | 新規性が要求される(世界基準、実質同一意匠の無公知)。創作容易性の明文規定なし(実質は新規性判断に包含)。公序良俗違反や純機能デザインは不可。 | 新規性・創作非容易性が要求される(従来は「容易に創作できる意匠」は拒絶理由、近年ガイドラインで緩和)。公序良俗違反・機能的形状は不可(意匠法5条各号)。 |
| 新規性喪失の例外 | 自己公開後12か月以内の出願であれば例外適用(出願人由来の公開のみ対象)。申請手続不要、自動適用。 | 自己公開後12か月以内(2018改正で6→12ヶ月)。適用には出願時申告と証明提出が必要(意匠法4条)。 |
| 出願方式 | 直接国内出願またはハーグ国際出願。【オンライン出願可】(CIPO電子システム)。紙出願も可。 | 直接国内出願またはハーグ国際出願。J-PlatPat電子出願システム利用可(要事前手続)、書面出願も可。 |
| 代理人要件 | 代理人任意(外国法人でも代理人無し出願可能)。代理人起用時も委任状不要。現地連絡先が無い場合は代理人推奨。 | 外国企業は代理人必須(日本在住の弁理士等)。委任状提出が必要。日本企業の場合も代理人起用が一般的。 |
| 願書記載事項 | 完成品の名称、出願人住所氏名、図面/写真、願書様式自由(専用フォーマット推奨)。説明文任意。 | 物品の名称、出願人情報、創作に係る事項の説明、図面6面(※2019年以降柔軟化)等。所定の願書フォーマット使用。 |
| 図面・写真の要件 | 図面 or 写真いずれも可。最低1図で可(複数推奨)。視点数の規定なし。破線による非保護部表示可。図の説明任意。 | 図面が原則(写真も可だが図面推奨)。従来6面図必須→現在は柔軟運用。必要十分な図を要求。破線等で部分意匠表示。図の簡単な説明は記載必要(法規定)。 |
| 一出願での複数意匠 | 不可(原則)。ただし**「バリエーション」**(同一製品で細部のみ異なる類似意匠)は1出願に包含可。大きく異なる複数デザインは分割要。 | 可能(2019改正)。複数意匠を1出願でまとめて提出可(各意匠ごとに審査・登録)。改正前は不可だった。関連意匠制度あり(本意匠出願から10年以内に類似意匠を別出願可能)。 |
| 審査方式 | 実体審査あり(無審査登録制度ではない)。審査期間目安18ヶ月。方式→実体審査。拒絶理由通知・応答(3ヶ月)。拒絶に不服なら連邦裁判所に司法審査請求。 | 実体審査あり。平均審査期間6~12ヶ月程度。拒絶理由通知・応答(原則3ヶ月)。拒絶査定不服は審判請求→知財高裁。 |
| 公開制度 | 非公開制度:出願は登録まで非公開。ただし出願/優先日から30ヶ月で自動公開。登録時に公開。登録遅延制度:任意で登録を最長30ヶ月遅らせ公開を延期可。 | 公開意匠公報制度:出願から原則6~8ヶ月で出願公告(意匠公報)として公開。秘密意匠制度:申請により最長非公開3年保持可(意匠法第14条)。 |
| 存続期間 | 出願日から15年(または登録日から10年後まで、長い方)。実質最長15年程度。延長不可。 | 出願日から25年(2019改正適用後)。延長不可。改正前出願は登録日から20年。 |
| 維持・更新 | 維持料1回のみ(登録5年目までに支払)。以後満了まで有効。5年以内未払いで権利消滅。更新制度なし。 | 毎年年金支払(初年度~3年目一括、その後毎年)。更新制度なし。年金未納で権利失効。 |
| 権利内容 | 同一または実質的に類似する意匠を同種製品に施す行為の差止め権・損害賠償請求権。意匠権は登録日に発生。 | 権利内容ほぼ同じ(意匠法23条)。意匠権は設定登録日に発生。 |
| 侵害に対する民事救済 | 民事差止め・損害賠償が中心。利益吐き出し請求可。懲罰的賠償あり得る。過去3年分まで請求可。無過失(善意)侵害者には損害賠償不可(差止のみ)。 | 民事差止め・損害賠償が中心。悪質なら損害額3倍までの惩罰的措置(意匠法施行規則による推定)も。時効:知財権も一般不法行為と同じく損害発見後3年(改正民法で5年)等。善意侵害者にも賠償責任あり(善意免責規定なし)。 |
| 刑事罰 | 無し。意匠権侵害は犯罪ではない。刑事手続なし。 | 有り。意匠権侵害は10年以下懲役・1,000万円以下罰金の刑事罰対象(親告罪)。警察・検察が関与しうる。 |
| 行政的取締(税関等) | 無し。税関による意匠侵害物品の差止制度なし。権利者自ら民事訴訟等で対応。 | 有り。税関に輸入差止め申立可能。侵害物品の没収・廃棄が行政手続で可能。 |
| 国際出願(ハーグ) | 加盟国(2018年~)。ハーグ経由でカナダ指定可。国内出願と同様に実体審査あり、拒絶通報に3ヶ月内応答要。国際登録からカナダ登録への変換処理はCIPOが対応。維持料は5年目国際更新でカバー。 | 加盟国(加盟2005年)。ハーグ指定可。実体審査あり(拒絶通報に応答要)。国際登録から日本登録への転換処理はJPO対応。維持年金は国内と同様毎年支払。 |
| 複製権との関係 | 無方式の意匠保護制度なし(未登録意匠の保護なし)。著作権・商標で補完保護可能な場合あり(意匠と商標の重複保護も可)。 | 未登録でも著作権法で美術的意匠は保護可能(ただし量産品は意匠登録しないと著作権保護限定、意匠法制定の趣旨あり)。商標的に立体商標登録する事例も。 |
※表中の【】内は出典箇所を示しています。日本制度の法条番号は参考として併記しました。
上記の通り、保護期間や保護客体、権利行使手段などにおいてカナダと日本の意匠制度にはいくつか重要な違いがあります。特に日本に比べカナダは保護期間が短く、行政的・刑事的なエンフォース手段が限られるため、日本企業はカナダでの権利活用戦略を立てる際に注意が必要です。例えば、カナダでは意匠権が早期に切れるため製品デザインのライフサイクル管理を日本と異なる前提で行う、模倣品対策は民事差止を念頭に迅速に動く、などの実務上の対応策が考えられます。また、出願段階でも、バリエーション展開のあるデザインはまとめて一括出願し、日本の関連意匠のような追従出願ができない点に備えるといった工夫も必要です。総合的に、カナダの制度を正しく理解し、日本での経験を踏まえつつ現地ルールに適合させた知財戦略を講じることが重要と言えるでしょう。
出典・参考文献
-
Canadian Intellectual Property Office (CIPO) – Industrial Designs Guide(カナダ知的財産庁「意匠ガイド」)など
カナダ意匠制度の公式ガイダンス。意匠の定義、登録要件、出願から登録・維持、ハーグ制度対応まで網羅的に解説。 -
Marks & Clerk – Insights into Designs Laws and Regulations: Canada
国際的な知財事務所Marks & Clerkによるカナダ意匠法Q&A(ICLGデザイン法2023年版)。グレースピリオド、委任状不要、侵害救済・無効理由など実務ポイントをQ&A形式で整理。 -
日本弁理士会(JPAA)– 意匠法の概要と改正ポイント
日本の意匠制度に関する解説記事。2019年改正による存続期間25年への延長、複数意匠一括出願の導入、関連意匠制度拡充等について解説しており、日本と外国制度比較の参考になる。 -
Taketo Nasu “Industrial design law in Japan” (2024)
エドワードエルガー社刊行のデザイン法の書籍に収録された日本の意匠法解説。日本における意匠権侵害の民事・刑事救済や税関措置について言及。 -
日本国・意匠法(英訳)(Japanese Design Act, translated)
日本の意匠法の公式英訳テキスト(法務省 Japanese Law Translation)。特に第69条の刑事罰規定等を参照。 -
カナダ意匠法・規則(Industrial Design Act and Regulations, Canada)
カナダ連邦法「意匠法」および同施行規則。新規性の定義や破線による範囲除外(Regulations 3(3))規定、意匠権期間等の原典。 -
WIPO Hague System – Guide to International Registration
WIPOハーグ協定のガイド。カナダ加盟に伴う指定時の留意事項、更新手続などについて基本情報を提供。 -
DLA Piper – Industrial designs: A lesser-known form of IP protection
DLAパイパー法律事務所によるカナダの意匠に関する記事。図面における破線による権利範囲の限定や、意匠権活用のポイントについて簡潔に言及。
(以上)
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)