...
フランスの意匠制度概要
登録要件(新規性・創作性など)
フランスで意匠(Design)として保護を受けるためには、主に新規性と**独自性(individual character)**の要件を満たす必要があります。以下、それぞれの要件と関連事項を整理します。
-
新規性:登録しようとする意匠は、出願前に世界のどこにも公然と知られていないものでなければなりません(絶対的新規性)。ただし、デザイナー本人(出願人)による公開や不正競争による漏洩の場合、12か月のグレースピリオド(新規性喪失の例外期間)が認められます。つまり、自己の公開から1年以内であればその意匠を出願しても新規性は失われない扱いとなります。※日本法でも2018年の改正によりグレースピリオドは6か月から1年に延長されています。
-
独自性(創作性):フランスの意匠法では**「独自の性格」とも訳され、登録意匠は先行意匠に対して異なる全体的印象を与えるものでなければなりません。この「全体的な印象」を受ける基準となるのは、当業者よりやや経験を積んだ「知識のあるユーザー (informed user)」**であり、そのユーザーが既存の意匠と比較して異なる美的印象を受けるかどうかで判断されます。平たく言えば、ありふれたデザインの単なる寄せ集めや微小な差異では独自性が認められず、登録できないということです。日本の意匠法における「創作非容易性」(先行意匠から容易に考案できないこと)の要件と概念的に類似しており、平凡な改変では登録できない点は共通しています。
-
その他の保護要件・除外:フランスも欧州連合(EU)の意匠保護指令に基づき、純粋に機能にのみ左右される形状(例えば部品の形状がすべて技術的機能の要請から決まるもの)は意匠登録の対象外とされています。また、公序良俗に反する意匠も登録不可です。さらにEU指令由来の特徴として、通常の使用過程で外部から見えない製品の部品(自動車のエンジン内部部品など)は意匠として保護されません。例えばプリンターのインクカートリッジのように、製品に組み込まれた後は消費者から見えなくなる部品のデザインは登録できないと解されています。日本法ではこの「見えない部品」明文除外規定はありません(もっとも、通常人目に触れない部分の意匠を出願するケース自体少ないでしょう)。一方、日本・フランスともに意匠法による保護の対象は「物品等の外観デザイン」に限られ, 例えば純粋なアイデアや概念そのものは保護対象外です。また、両国とも意匠法による登録を受けたデザインであっても、要件を満たせば著作権による保護も併存し得ます(フランスでは工業デザインも芸術的創作として著作権保護を受け得るとの原則が確立しています。日本でも近年、意匠と著作権の二重保護が見直されつつあります)。
出願手続(出願先、言語、手数料、審査制度など)
出願先と言語:フランスの意匠出願は、フランス特許庁に相当する産業財産庁(INPI)に行います。出願はフランス語で行うのが原則です。2019年10月以降、意匠出願はオンライン手続のみ受け付けられており、紙による手続は基本的に認められていません。また、出願人がフランスに居所・拠点のない外国企業の場合、現地の産業財産権代理人(弁理士)を選任する必要があります。
必要書類と方式:出願時には**願書(出願人の情報等)**に加え、意匠の図面または写真を提出します。図面/写真は保護を求めるデザインの美的特徴を正確に表す必要があり、同一製品については異なる角度や使用状態での複数画像を添付することが推奨されています。画像中にデザインと無関係な背景や装飾、文字等は含めてはならず、無地の背景にデザインのみを示す必要があります。
一出願で複数意匠:フランス(およびEU)では、1件の出願で複数の意匠をまとめて出願することが可能です(最大100件まで同時出願可)。ただしその場合、すべての意匠は同一の製品カテゴリ(ロカルノ分類上のクラス)に属している必要があります。例えば家具のデザイン100種を1件にまとめて出願するといったことも可能です。これにより手数料面・手続面で効率化が図れます。一方、日本では一意匠一出願が原則であり、複数の意匠を一括して出願する制度はありません(類似デザインについては後述する関連意匠制度で対応)ので、この点は大きな相違点です。
手数料:フランスの意匠出願にかかる費用は比較的低額です。2025年現在、基本の出願料は39ユーロで、さらに最初の保護期間を10年にする場合は追加52ユーロの登録料が必要です。したがって出願時に5年分の登録料しか払わなければ39€、10年分までまとめて払う場合でも計91€程度で済みます。また、提出する図面・写真の点数によって追加手数料が発生し、白黒図の場合1点あたり23ユーロ、カラー図の場合1点あたり47ユーロが課されます。例えば、カラー図面6面図で出願する場合は39€ + 6×47€ = 321€となります。なお、フランスには登録料の分割納付(更新時に5年ごと支払い)の制度がありますが、特別な最終登録料(grant fee)は不要で、方式審査通過後に自動的に登録されます。日本の場合、出願料は16,000円(電子出願の場合)で、登録料として初年度分8,500円(2,3年分もまとめて納付可)が必要となり、合計24,500円程度が初期費用の目安です。4年目以降は毎年登録料を納付し(4~25年目:各年16,900円)継続させる仕組みです。両国を比較すると、日本は出願から登録までに審査を経る分、初期費用は若干高くなりますが、全期間(25年)保護した場合の総額は概ね同程度と言えるでしょう。
審査方式:フランス(およびEU)の意匠出願は無審査登録主義に近い方式です。INPIでは出願後、方式的要件(書類不備や公序良俗違反がないか)のみを審査し、新規性や独自性についての実体審査は行いません。意匠公報(公式広報)への掲載準備が整い次第、平均3~4か月程度で登録・公開されます。審査官が先行意匠との類否を審理しないため処理が迅速なのが特徴です。その代わり、登録後に利害関係人が無効審判請求をしたり、侵害訴訟において被告が無効の抗弁を主張したりする場面で、新規性・独自性が改めて検討されることになります。日本の意匠制度ではこれと対照的に、特許庁の審査官による実体審査が課されています。出願から約6~12か月かけて、先行意匠の調査や新規性・創作非容易性の判断が行われ、登録適格と認められた場合のみ意匠公報の発行・設定登録となります。日本は実体審査を経るぶん信頼性が高い反面、登録までに時間を要する点で違いがあります(もっとも近年は審査の迅速化が進み平均7か月程度で査定が出るケースも少なくありません)。
公開の猶予(秘密意匠):フランスでは、出願人の希望により意匠の公開を最大3年間延期することができます。これを公開延長(ディフェラル)制度といい、製品発売までデザインを秘匿したい場合などに利用されます。具体的には、出願時に公開猶予を申請すると、出願から最長36か月間は意匠公報への掲載を保留し、その間は第三者にデザイン詳細が知られないようにできます。日本にも同様に、登録公報への掲載を遅らせる秘密意匠制度があります。日本の場合、登録日から3年以内であれば、出願時の請求によってその期間デザインを非公開にすることが可能です(※日本では出願と同時に請求する必要があります)。フランスと日本いずれも最長3年間の非公開が可能ですが、フランスは「出願から」、日本は「登録から」の起算である点が異なります。
保護期間(存続期間・更新など)
フランスの登録意匠の保護期間は、基本的に最大25年間です。ただしその運用は少し特殊で、初回登録期間を5年または10年で設定する仕組みになっています。出願時に5年分の登録料しか支払わなかった場合、登録後最初の5年間で権利が満了しますが、引き続き保護を望む場合は5年目の満了前に更新料を支払うことでさらに5年延長できます。同様に最大で5年×5期=25年まで更新可能です(10年分まとめ払いしていた場合は最初の10年が有効期間となり、その後5年毎に更新)。25年経過後は意匠権による保護は終了し、そのデザインは公有となります。なおフランスでは、意匠によって創作された物品は著作物足り得る場合には著作権による保護(作者の生存期間+死後70年)を並行して主張することも可能です。したがって、意匠権の存続期間満了後も、デザインに芸術性・創作性が認められる限り著作権で保護され続けるケースもあります。
一方、日本の意匠権の存続期間は出願日から25年と規定されています。2020年4月施行の法改正により従来の「登録日から20年」から延長されたもので、現在はフランス・EUと同じ25年保護が可能となりました。ただし日本の場合、存続期間中は毎年の年金(登録料)納付が必要で、未納があれば権利が途中で消滅します。フランスも5年毎の更新料が必要なので維持管理の手間はありますが、最大期間が同じ25年となったことで、日仏間で大きな差異はなくなりました。なおEUの共同体意匠も同様に5年毎更新で最長25年です。
※参考までに、EUには無方式(未登録)意匠という制度もあり、公開から3年間は登録なしでもデザインを保護できる場合があります。ただし未登録意匠は模倣行為にのみ適用される限定的な権利で、日本にこのような未登録の意匠権は存在しません(デザインの無断模倣対策としては日本では不正競争防止法等で対応)。
侵害訴訟(権利行使、裁判所、立証責任、損害賠償など)
フランスにおける意匠権侵害の訴訟手続について、その実務上のポイントを説明します。
-
管轄裁判所:フランスでは知的財産案件を扱う**専門部門を有する地方裁判所(Tribunal judiciaire)**が意匠侵害訴訟を管轄します。特にパリ大審裁判所(パリ司法裁判所)は知財専門部が設置され、共同体意匠(EUデザイン)に関する訴訟はパリ司法裁判所の専属管轄と定められています。フランス全国にいくつか知財専門の裁判所がありますが、重要案件はパリで扱われる傾向があります。一方、日本では意匠侵害訴訟は主に東京地方裁判所や大阪地方裁判所の知財専門部が第一審を担当し、控訴審は知的財産高等裁判所(東京高裁内)で審理されます。
-
権利行使の流れと立証:フランスでは訴訟提起前または提起と同時に、裁判所からの許可を得て相手方の侵害物の証拠を確保するサーシ・コントルファソン(Saisie-contrefaçon)と呼ばれる証拠保全手続を利用できます。これは執行官(司法官)が被疑侵害者の事業所等を訪問し、当該デザイン製品や生産書類を差し押さえ・撮影するもので、侵害の証拠収集に非常に有用です。この差止め(差押え)は原告が侵害の蓋然性を合理的に示せば訴訟前でも直ちに実施可能であり、証拠がなければ始まらないデザイン訴訟において強力な武器となっています。日本でも証拠収集の手段として文書提出命令などがありますが、フランスのサーシに比べると限定的であり、ここに実務上の差が見られます。
訴訟において原告(意匠権者)は、被告製品のデザインが自分の登録意匠と実質同じ範囲(同一又は差異がごく僅かな範囲)であることを立証します。フランス/EU法では、「被告製品のデザインが登録意匠と異なる『全体的印象』を与えない場合」には意匠権侵害が成立する、と規定されています。すなわち、見る人に与える美感が近似していれば、同じまたは類似のデザインとみなされ侵害になります。日本でも「登録意匠またはこれに類似する意匠」を業として実施すれば侵害と定められており(意匠法24条)、両国で実質的な侵害判断基準は近いものがあります。ただしフランスでは、被告は抗弁として登録意匠の無効(新規性・独自性欠如)を主張することができ、裁判所は侵害訴訟の中で権利の有効性も審理します。一方、日本では無効審判は特許庁に専属するため、被告は無効審判を別途請求しつつ侵害訴訟では権利濫用の抗弁(明白無効な場合)などで対抗する形になります。この違いから、フランスの裁判所では侵害と有効性を同時に判断して結論を出すケースが多い点に留意が必要です。
-
救済(差止・損害賠償など):侵害が認められた場合、原告は差止命令および損害賠償の救済を請求できます。フランスでは差止命令は仮処分として訴訟前にも発令可能で、勝訴後は執行猶予なしに直ちに効力が生じるのが通常です。また判決の履行を担保するため、被告が違反した場合に1日あたり○ユーロなどの科料(アストラン)を課す形で命じられることも一般的です。損害賠償については、フランスでは2000年代のEU指令実施以降、裁判所は原告の実損額(逸失利益、市場の風評被害など)に加え、被告の不当利得や仮想的なライセンス料相当額を考慮して賠償額を決定することになっています。立証が困難な場合でも、少なくとも「通常であれば得られたであろうロイヤリティ額」を一種の法定賠償額として認定することが可能で、被害者の救済漏れを防ぐ配慮がなされています。日本でも意匠法によって特許法と同様の損害推定規定(特許法102条準用)があり、侵害品の販売数量や被告の利益額を用いて損害額を推定できます。したがって算定手法に大きな差はありませんが、フランス裁判所は訴訟費用や弁護士費用の一部も被告に負担させることが多く(近年は実費に近い額を勝訴者に認める傾向)、経済的救済の範囲では日本より充実している面があります。
-
刑事罰:フランスでは意匠権侵害は故意犯に限り刑事罰の対象となり得ます。意図的な意匠侵害を行った者には最大で懲役3年及び30万ユーロの罰金が科される可能性があります(違反回数により加重)。刑事手続は税関当局や検察官、または権利者本人の告発によって開始できます。日本でも意匠権侵害は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金の対象(非親告罪化されています)であり、重大な模倣品事案では刑事摘発も行われます。もっとも日仏ともに民事での差止・賠償救済が主軸で、刑事訴追は悪質なケースに限定されるのが実情です。
国際出願との関係(ハーグ制度、欧州意匠との整合性)
ハーグ国際意匠制度:フランスはハーグ協定(ジュネーブ改正協定)加盟国であり、国際登録制度を利用することができます。すなわち、WIPO(世界知的所有権機関)に対して国際意匠出願を行い、フランスを指定国として登録することで、フランス国内の意匠登録と同等の効力を得ることが可能です。ハーグ出願は一度の出願で複数国のデザイン保護を得られる利点があり、フランス企業だけでなく日本企業も活用しています(日本も2015年にハーグ協定に加盟済み)。例えば、日本企業がハーグ経由でフランスを指定すれば、フランス庁(INPI)への直接出願を省略してフランス意匠権を取得できます。ただし、フランス独自の手数料(例えば先述の初回5年登録料など)も別途必要になる点には注意が必要です。
欧州共同体意匠(EUデザイン):フランスはEU加盟国であるため、EU全域で有効な「登録共同体意匠 (Registered Community Design: RCD)」制度との選択肢があります。共同体意匠はEU知的財産庁(EUIPO)に出願して取得するもので、一件の登録でフランスを含むEU全域(現在27か国)に意匠権が及ぶ強力な制度です。フランス国内法とEU共同体意匠制度の整合性については、EUの意匠保護指令(98/71/EC)により各国の実体要件が調和されています。したがってフランス意匠法の定義・要件・保護期間等はEU規則とほぼ一致しており、新規性・独自性の判断基準や最長25年の存続期間など、フランス国内意匠と共同体意匠で内容に差はありません。そのため実務上も、フランスローカルのデザイン保護とEU全域のデザイン保護で二重出願の必要は基本的になく、保護したい範囲に応じてどちらかを選択することになります。例えば、デザインの市場がフランス国内に限られる場合や費用を抑えたい場合はフランス意匠への出願(約39€~)を選び、欧州全域での商品展開を予定している場合は共同体意匠への出願(基本料350€~)を選択する、といった判断になります。なお、共同体意匠を取得すればフランス国内で別途登録を取る必要はありません(フランスを含むEU加盟国内で自動的に保護されます)。逆にフランス国内意匠権しかない場合でも、EU域内でそのデザインを独占したければ他国での権利化(共同体意匠や各国出願)を検討する必要があります。
また、EUには先述した未登録共同体意匠(3年保護)の制度があり、フランス国内でデザインを公開するだけで自動的に一定の保護を得られるケースもあります。未登録意匠は模倣品排除に限定されるとはいえ、例えばファッション業界など移り変わりが激しい分野では実務上重要です。日本には未登録意匠の制度はありませんが、フランス企業が日本展開する際には日本での意匠権取得を忘れると無防備になる点に注意が必要でしょう。
以上のように、フランスの意匠制度は単独でも完結した保護体系を持ちながら、EU全域制度と国際制度に有機的に組み込まれています。次項では、これらフランスと日本の意匠制度の主な共通点と相違点を一覧表でまとめます。
フランスと日本の意匠制度の比較
最後に、フランスと日本の意匠制度の重要ポイントを対比した表を示します。それぞれの制度の特徴を理解し、グローバルにデザイン保護戦略を立てる際の参考としてください。
| 項目 | フランス意匠制度 | 日本意匠制度 |
|---|---|---|
| 保護対象 | 製品(工業製品・手工業品)の外観デザイン(製品の一部も含む)。線・形状・色彩・質感・材料などに由来する形態。装飾的な図柄やタイポグラフィ(書体)も保護対象に含む。※機能のみで決まる形状、および通常見えない複合製品内部の部品は登録不可。 | 物品(工業上利用可能な有体物)および建築物・画像のデザインも含む(2020年法改正で拡張)。物品の部分の形状や模様、色彩の結合も含む。※法律上明示の除外規定はないが、純粋に機能だけで決まる形状は実質的に保護対象にならない。公序良俗に反する意匠は登録不可(意匠法5条)。 |
| 部分意匠制度 | 定義上製品の一部分の外観も意匠に含まれるが、部分のみを特別扱いする制度はない(一部を保護したい場合、該部分のみ描いた図面で出願)。 | 部分意匠制度あり。製品の一部分について他部分を破線等で示し、その部分のみのデザインとして登録可能(全体としては新規性がなくても部分に新規性があれば可)。 |
| 登録要件 | 新規性:出願前に公知の同一意匠が存在しないこと(世界基準、自己の公表は12か月以内なら例外)。独自性(創作性):既存の意匠に比べて異なる全体的印象を与えること(類似の範囲は独自性なしと判断)。※機能的形状・非可視部品は除外。 | 新規性:出願前に公然知られた同一または類似意匠が存在しないこと(国内外、公知・刊行物問わず)。自己の公表は1年以内なら新規性喪失の例外適用可。創作非容易性:既存の意匠から容易に考案できないこと(類似の意匠は「容易に考案された」とみなされ拒絶)。※一部に類似があっても全体として異なる美感を与えれば登録可能(類否判断は審査官が実施)。 |
| 審査方式 | 方式審査のみ(出願書類の形式・公序良俗のみ審査)。新規性・独自性は審査されず、出願から約3~4か月で登録公開。※実体審査がないため、登録後に無効審判や侵害訴訟で有効性が争われる。 | 実体審査あり(特許庁審査官が先行意匠との類否や創作容易性を審査)。平均6~12か月で審査結果が出る。拒絶理由がなければ登録査定・設定登録となり公報発行。※拒絶に不服なら審判可。登録後でも利害関係人は特許庁に無効審判を請求可能。 |
| 出願方式 | INPI(フランス産業財産庁)に電子出願。出願人の氏名・住所、意匠の図面/写真等を提出。1出願で最大100意匠まで包含可(同一ロカルノ分類内)。※代理人:出願人がフランス非居住の場合、フランスの代理人選任が必要。 | 日本特許庁(JPO)にオンラインまたは書面で出願。出願人情報、願書、図面等を提出。1出願1意匠が原則(類似デザインは関連意匠制度で別出願)。複数意匠一括出願制度は基本なし。※代理人:日本国外居住者は日本の弁理士等を代理人に選任必要(特許法施行規則に準拠)。 |
| 手数料・維持費用 | 出願料:39€(基本料)。**初回登録料:**5年分は出願料に含む。10年分登録希望時は+52€追加。**図面提出料:**白黒1点ごと23€、カラー1点ごと47€追加。**更新料:**6年目以降、5年延長ごとに所定の更新料(例:5年延長=52€程度)を支払う。最大25年まで延長可能。 | 出願料:16,000円(電子出願)。**登録料(設定登録時):**初年度分8,500円(2~3年分をまとめて前納可)。**年金(維持費用):**4年目以降、毎年16,900円を納付(2020年改定料金)。※2020年以前出願は旧料金体系(登録から20年)。現在は出願から25年に統一。 |
| 公開猶予制度 | 公開延長 (deferment):出願時請求により、意匠公報への掲載を最大3年間延期可能。非公開期間中は第三者にデザイン内容を秘匿できる。期間満了時に自動公開。 | 秘密意匠制度:出願と同時の請求で、登録日から最長3年間意匠公報への掲載をせず非公開にできる。秘密期間経過後に公報発行。※秘密意匠請求中でも願書の基本情報は公開される(デザインの詳細のみ非公開)。 |
| 存続期間 | 5年(または10年)+更新。初回登録期間は5年(希望により10年)。以後5年ごとに延長登録料を払い最長25年まで延長可。※25年経過後は権利消滅。著作権による保護に移行する場合あり。 | 25年一括。出願日から25年で満了(2020年4月以降の出願)。※旧法では登録日から20年であったが現行は25年に延長。途中で年金未納があるとその時点で権利消滅。 |
| 権利範囲 | 登録意匠と同一又は異ならない印象を与える意匠(製品の種類を問わない)の業としての実施が侵害となる。※意匠権は製品の見た目に対する絶対的排他権であり、意匠に類似するデザインも保護範囲に含む。 | 登録意匠またはこれに類似する意匠を業として実施すると侵害(意匠法23,24条)。※「類似」かどうかは需要者の注意を引く美感に基づき総合判断。登録意匠と物品の用途・機能が異なる場合でも見た目が似ていれば侵害になり得る(近年の法改正で他物品への類似も明文化)。 |
| 侵害訴訟管轄 | 専門部付地方裁判所が管轄(パリ、リヨン等指定裁判所)。共同体意匠侵害はパリ司法裁判所の専属管轄。※民事訴訟では無効理由も同時審理可能。 | **地方裁判所(東京・大阪等)の民事部(知財専門部)**が第一審管轄。控訴審は知的財産高等裁判所。※無効審判は特許庁に請求(審決不服は知財高裁)。侵害訴訟で無効主張する場合、明白無効でない限り裁判所は特許庁の判断を待つのが通例。 |
| 権利行使・救済 | 差止請求:仮処分的な差止(侵害禁止命令)取得可。勝訴時は本救済として差止命令が出る。履行確保のため違反1日あたり○€の科料を付すことも可能。損害賠償:実損額(利益減少分等)に加え、侵害者の得た利得やライセンス料相当額を考慮して算定。裁判所は必要に応じて鑑定人を任命し損害額を査定する。証拠収集:サーシ・コントルファソン(証拠保全差押え)制度で訴訟前に侵害製品を押収・確認可能。刑事罰:故意侵害に3年以下の懲役・30万€以下の罰金(法人は150万€迄)。税関差止や刑事告発も活用可。 | 差止請求:侵害の予防・停止を求める仮処分・本案判決による差止命令。間接強制(1日あたりの金銭)の制度も民訴上あり。損害賠償:意匠法38条で特許法105条の適用あり(損害額の推定)。逸失利益、侵害者の利益額、ライセンス料相当額のいずれかで算定。弁護士費用等も一定範囲で賠償請求可。証拠収集:文書提出命令、鑑定、検証申立て等で対応(日本独自の侵害品保全制度は未整備)。刑事罰:10年以下の懲役・1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)まで適用可能。近年は非親告罪となり所轄官庁による摘発もあり。 |
※出典:フランス意匠制度等、日本意匠制度等
以上の比較から、フランスと日本の意匠制度は基本的な枠組み(保護対象や期間など)は共通しつつ、審査方式や手続の柔軟性で違いが見られることが分かります。特に、フランス(EU)は無審査登録で迅速・低コストであるのに対し、日本は実体審査で権利の安定性を図るという対照的なアプローチを取っています。また、デザイン保護の国際的な利用では、フランスはEUデザインやハーグ協定を通じて広域かつ効率的な保護が可能であり、日本企業にとっても自国と欧州双方の制度をうまく使い分けることが重要です。上述の知見を踏まえ、実務においては各制度のメリット・デメリットを比較検討し、自社のデザイン戦略に適した権利化プランを構築することが望まれます。
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)

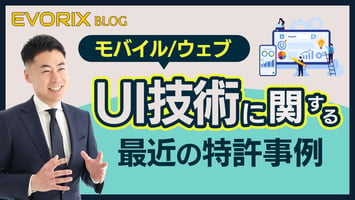
.jpg?height=200&name=unnamed%20(4).jpg)
