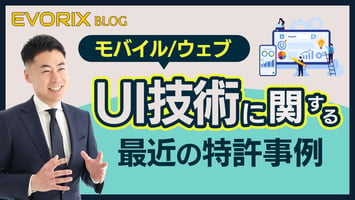...
スイスの意匠制度概要
登録要件
スイスの意匠を登録するためには、新規性および独自性が求められます。具体的には、その意匠がこれまでに公表・公衆利用されておらず、新規であること、そして既存の意匠と比べて十分に異なる特徴を有することが必要です。また、意匠の内容が違法なものや公序良俗に反するものであってはならず、製品の機能上不可欠な形状のみで構成される意匠も保護の対象外です。スイス意匠法(DesA)では、これらの要件(Art.2)および登録拒絶事由(Art.4)が規定されています。登録手続では、意匠の機能的形状に関する判断(純粋に機能にのみ由来するデザインかどうか)以外の拒絶事由について審査官がチェックしますが、新規性や独自性についての実体審査は行われません。そのため、出願人自身が出願前に類似のデザインが存在しないか確認することが推奨されています(IPIも出願前の先行意匠調査を奨励しています)。
日本の意匠登録要件との比較: 日本の意匠法においても、新規性は厳格に要求されており、国内外で公然と知られた意匠やそれらに類似する意匠は登録できません。さらに、日本では公知のデザインから容易に創作できるような創作非容易性のない意匠も拒絶されます。これはスイス法の「重要な点で既存デザインと異なること」という独自性要件に類似した趣旨ですが、日本では審査官が実体的にこれら新規性・創作容易性を審査し、該当すれば拒絶します。一方、スイスでは新規性等の要件は無審査登録であり、これらの要件違反が問題となるのは無効審判や訴訟の場となります。なお、新規性喪失の例外(グレースピリオド)については、スイスでは12か月、日本では1年と期間は同じですが、日本では出願と同時の手続き(適用申請と証明書類提出)が必要な点に注意が必要です(スイスも意匠法Art.3により12か月のグレースピリオドを認めています)。
出願手続
スイスへの意匠出願は、スイス連邦知的財産庁(IPI)が管轄します。出願に必要な書類は願書(出願人と創作者の氏名・住所、意匠の名称、製品区分等)、意匠の図面または写真(少なくとも1枚)などで、出願時に少なくとも1つの意匠画像が含まれていなければなりません。スイスでは一件の出願で複数意匠を包括的に出願することも可能であり、同一または類似する製品分類(ロカルノ分類)に属する意匠であれば最大100意匠まで一括出願できます。出願費用は基本料が1意匠あたりCHF200で、同一出願に追加するごとに加算(6意匠以上は一律CHF700)され、1意匠につき1点の図の掲載料を含みます。手続言語はドイツ語・フランス語・イタリア語の公用語から選択でき、外国企業・個人がスイスに出願する際には現地代理人(弁理士)を選任する必要があります。出願から登録までの処理期間は平均して数か月〜1年程度で、順調な場合は比較的短期間で登録されます。IPIでは方式審査のみを実施し、前述のとおり実体的要件(新規性・独自性)の審査は行いません。方式審査で不備があれば補正通知が発行され、期間内に補正しないと不登録処分となります。なお、スイスには出願公告後の異議申立制度は存在せず、登録後に第三者が無効審判(取消訴訟)を提起する以外に権利発生前に異議を申し立てる手段はありません。
手続上の特徴として、スイスは意匠の公開を最大30か月間遅らせることができます。出願時に**公開延期(デファード)**を請求すれば、出願日(または優先日)から30か月の範囲で公開を繰り延べでき、その間は非公開状態で権利化を進めることが可能です。これは製品発表のタイミングに合わせて意匠を秘匿したい場合に有用です。
日本の出願手続との比較: 日本では一意匠一出願が原則で、スイスのような複数意匠の一括出願制度はありません(※2020年改正で内装の意匠のように複数物品にまたがるデザインも一体の意匠として保護可能になりましたが、基本的に個別の意匠ごとに出願する仕組みです)。また、日本出願では願書(日本語)に6面図等の厳格な図面一式が必要で、図面補正も制限されるなど、手続き要件は詳細に定められています。審査方式については、日本は特許庁による実体審査制を採用しており、新規性・創作容易性・公序良俗違反などが審査で精査されます。一方のスイスは実体無審査であるため、出願から登録までのスピードは日本より速い傾向があります。日本では出願から一次審査通知まで平均6〜8か月程度かかり、拒絶理由があれば応答を経て登録まで1年強は要するケースが多くあります。公開制度については、日本にも秘密意匠制度があり、登録後最長3年間、公報で意匠を非公開(秘匿)にできる点はスイスの公開延期と似ています(期間は日本36か月、スイス30か月)。しかし、日本の秘密意匠は権利発生後に公報掲載を遅らせる制度であるのに対し、スイスの公開延期は出願段階で登録自体も含め非公開を維持する点が異なります。また、日本出願では願書に設定登録時の登録料(初年度3年分)納付が必要で、その後毎年登録料を納付して存続期間を維持する年金制度になっています。スイスでは更新時に更新料を支払う方式ですが、登録時に初期5年分以上の維持費をまとめて納付する必要はありません(初回登録料に初年度~5年目までの存続含む)。
保護期間
スイスの意匠権の存続期間は、出願日から起算して5年間です。この5年の初期保護期間は最長4回更新(延長)することが可能で、更新手続きを行うごとに5年ずつ延長されます。したがって、最大で出願日から25年が経過するまで意匠権を維持することができます。更新手続きは、存続期間満了前12か月以内(満了後6か月以内の猶予期間あり)に更新申請と所定の更新料支払いを行うことで実現します。例えば、2025年に出願・登録した意匠は、5年目(2030年)にまず更新手続きを行えば2035年まで延長され、以後も5年単位で手続きを行い最終的には2050年まで権利を保持できます。なお権利期間の起算日は出願日であり、権利は登録日の時点で発生しますが、保護期間はそこからではなく出願日を基点に計算される点に注意が必要です(例えば出願から登録までに半年かかった場合でも、その半年も存続期間に含まれる)。更新を行わなければ、5年の満了時に権利は消滅し、その意匠は公有となります。
日本の保護期間との比較: 日本の意匠権の存続期間は、原則として出願日から25年であり、2020年の法改正によりスイスと同様に最長25年間の保護が可能となりました。改正前の日本法では「登録日から20年」でしたが、現行法では「出願日から25年」に変更され、保護期間が実質的に延長・国際調和されています。もっとも、日本では特許権と同様に毎年の年金(登録料)納付によって権利を維持する仕組みで、途中で年金を滞納すればその時点で権利消滅します。一方スイスは5年ごとの更新制であり、5年単位で区切って維持費を支払う形です。日本では更新という概念はなく25年を上限に年金納付により存続させる点や、起算日こそスイスと同じ出願日ですが権利発生が登録日である点(登録時に初期期間の年金納付が必要)など手続面での違いがあります。ただし最長保護期間25年という点では現在両国とも一致しており、保護期間の観点からは国際的にほぼ同水準と言えます。
侵害訴訟
権利範囲と侵害行為: スイスの登録意匠には排他的権利が認められ、意匠権者は第三者による無断使用を排除する権利を有します。具体的には、意匠権者の許諾なく、その登録意匠(または事実上同一といえる意匠)を製造・販売・輸入など業として実施する行為が侵害に該当します。スイス法でも意匠の類似範囲に関する規定があり、登録意匠と「主要な特徴において共通する」(すなわち十分に異ならない)意匠は権利範囲に抵触すると解されます。したがって模倣品がオリジナルと同一または紛らわしいほど似ている場合、意匠権侵害が成立し得ます。もっともデザイン分野では、他人の意匠を意図せず侵害してしまうケースも少なくなく、IPIも「意匠権侵害はしばしば故意でなく発生する」ことに留意するよう呼びかけています。
訴訟の前段階: スイスでは意匠権者自らが市場を監視し、権利行使の必要がある場合にはまず警告状(内容証明等)を送付して相手方に任意の製造販売中止や交渉を促すのが通例です。IPIも慎重かつ実務的な対応策としてまず警告書による私的解決を試みることを推奨しています。警告状には侵害となる事実、意匠権の内容、および継続した場合の法的措置(差止や損害賠償請求)の可能性などを明示し、可能な限り訴訟外で和解・是正を図ることが望ましいとされます。それでも相手が応じない場合、民事訴訟による差止請求や損害賠償請求、また悪質なケースでは刑事告訴による制裁措置を検討します。
訴訟手続と救済: スイスには特許侵害を扱う連邦特許裁判所がありますが、意匠侵害訴訟については各州の商事裁判所や民事裁判所が第一審管轄となる場合が一般的です(特にチューリッヒやベルン等、州によって専門部が設置されていることがあります)。民事訴訟では差止命令(差止判決)と損害賠償が主要な救済です。差止については、権利者が迅速な救済を要する場合、仮差止(仮処分)を申し立て違法な意匠製品の製造・販売を暫定的に停止させることも可能です。損害賠償は侵害者に故意過失が必要ですが、営業上の利益減少やライセンス料相当額などを請求できます。また、意匠権侵害は刑事罰の対象でもあり、故意に他人の意匠権を侵害した者は訴追により罰金刑や懲役刑を課されることがあります(スイス刑法または意匠法上の規定に基づく)。実際に刑事手続がとられるのは悪質で大規模な侵害(例えば組織的な偽造品製造・流通)に限られますが、刑事罰の存在は侵害抑止の効果を持っています。
その他の執行手段: スイスでは知的財産権の執行手段として税関差止も利用できます。意匠権者は連邦税関・国境安全保障局(FOCBS)に申請して、侵害品と疑われる物品の輸入差止め措置を取ることが可能です。申請が認められれば、郵便や空港・国境で税関職員が侵害品を発見し押収・差止します。知的財産の模倣品対策として、商標や著作権と同様に意匠についても国境措置が用意されています。
日本の侵害訴訟との比較: 日本の意匠権も同様に、登録意匠およびそれに類似する意匠に及ぶ排他権を付与し、無断でその意匠を業として実施(製造・販売・輸出入など)する行為は侵害となります。日本では意匠権侵害に対し、民事上の救済(差止請求、損害賠償請求等)に加えて、意匠法69条に基づき10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)の刑事罰が科される可能性があります。実務上は、まず警告書送付→交渉による和解が図られ、それでも解決しなければ東京・大阪などの知的財産に専門部を持つ地方裁判所に訴訟提起する流れが一般的です。日本の裁判所は意匠の類否判断(登録意匠と被疑意匠の美感に基づく全体的な類似性)を詳細に行い、しばしば専門部(知財高裁や知財に明るい部)で審理されるため、スイスに比べ審理期間は長めですが専門的な判断が期待できます。救済内容はスイスとほぼ同様で、差止命令および損害賠償(日本では損害額の推定規定や過失の推定規定(意匠法40条)など権利者救済を図る特則があります)が主となります。また、日本でも税関に意匠権を登録して輸入差止を申請でき、特に模倣品の海外からの流入防止に活用されています。総じて、権利行使の枠組み自体は両国で大きく変わるものではなく、民事手続を基本に、悪質なケースでは刑事罰で担保する構造になっています。ただし、日本では間接侵害規定(意匠製品の直接侵害行為を容易にする部品の提供等も侵害とみなす)を2020年改正で整備するなど、権利行使を強化する措置が講じられている点が特徴です。一方スイスでは間接侵害について明文規定はなく、共犯従犯として扱うことになります。このように細部の違いはあるものの、模倣品からデザインを守るという実務目的において日スイス両国の制度は共通の基盤を持っています。
国際出願との関係
スイスも日本も共にハーグ協定の締約国であり、国際意匠登録制度(ハーグシステム)を利用できます。ハーグ協定に基づく国際意匠出願(WIPO経由)でスイスを指定すれば、ジュネーブのWIPO事務局を通じてIPIに意匠が送達され、スイス国内出願と同様の効果で審査・登録が行われます。スイスの場合、前述のように実体審査が限定的であるため、国際出願でスイスを指定した場合も特段の拒絶通報が無ければ自動的に登録となりやすいと言えます。実際、IPIが拒絶理由通知(Refusal)を出すのは、公序良俗違反や技術的機能のみから成る意匠などの明白なケースに限られ、多くの国際登録意匠はスイスでスムーズに保護が発生します。スイスを指定した国際登録意匠は、その後スイス国内の意匠登録原簿に記録され、保護期間や更新手続も国内出願と同様(5年毎に直接IPIへ更新可)に扱われます。
一方、日本をハーグ出願で指定した場合、日本特許庁(JPO)は国内出願同様に実体審査を行います。そのため、国際登録後6か月以内に日本から拒絶理由の通報が出されることがあり、意匠が新規性欠如や不登録事由に該当すると判断されれば、出願人(国際出願の名義人)は応答期間内に意見書や補正書を日本特許庁に提出して拒絶理由を解消する必要があります。実務上、日本指定では応答のため日本の弁理士を選任するケースが多く、国際出願であっても日本の国内手続に準じた対応が必要になります。これは無審査で登録されるスイス指定の場合と大きな相違点です。例えば、同じ意匠について国際出願でスイスと日本を指定した場合、スイスでは迅速に登録・発行される一方、日本では拒絶理由通知への対応や審査結果確定までに時間と手間を要することがあります。日本企業が自社デザインの海外保護を図る際、ハーグ制度を使えば一度の出願で両国を含む複数国の権利取得が可能ですが、各国ごとの審査水準の違いを念頭に置く必要があります。スイスは登録要件が緩やかな反面、権利化されても後発的に無効主張されるリスクが残るのに対し、日本は厳格な審査で権利の安定性を担保するアプローチと言えます。なお、日本・スイスいずれもパリ条約加盟国ですので、**直接それぞれに出願する場合でもパリ優先権(6か月間)**を主張可能です。例えば、日本に先願して6か月以内にスイスに出願すれば、新規性喪失の例外期間とは別に優先権による不利の排除ができます(意匠の優先権期間はパリ条約上6か月であり、両国もこれを採用)。総じて、国際出願(Hague)の活用は日スイス双方で整備されており、日本企業がスイスで、あるいはスイス企業が日本で意匠権を取得するのは容易になっています。ただし審査フローや権利の安定性に違いがあるため、戦略立案時には各国制度の特徴を踏まえた対応が求められます。
日本制度との比較表
| 観点 | スイスの意匠制度 | 日本の意匠制度 |
|---|---|---|
| 登録要件 | 新規性・独自性を要求(公知でなく既存意匠と十分異なること)。公序良俗違反や純粋に機能のみの形状は不可。実体審査なしで登録されるが、要件不備の意匠は無効審判で無効となり得る。 | 新規性・創作非容易性を要求(公知の意匠およびその類似は不可、既存意匠から容易に想到できるものも不可)。公序良俗違反も不可。特許庁が実体審査を行い、要件を満たさない出願は拒絶される。 |
| 出願手続 | IPIに願書(独語・仏語・伊語)提出。方式審査のみで迅速登録。一出願で最大100意匠(同一分類内)を包括可。公開延期制度あり(30か月)。異議制度なし(登録後無効審判のみ)。外国出願人は現地代理人必要。 | 特許庁に願書(日本語)提出。実体審査有り(審査期間平均6〜12か月)。一出願一意匠(※内装など例外あり)。秘密意匠制度あり(登録後最大3年非公開)。意匠公報発行後、異議制度はなく無効審判のみ。外国出願人は国内代理人必要。 |
| 保護期間 | 出願日から5年+4回更新で最大25年。初期5年経過ごとに更新料を払い延長(猶予6か月)。起算日は出願日(登録日に権利発生)。 | 出願日から25年(2020年以降)。年毎の登録料納付で最長まで維持。起算日は出願日(改正前は登録日から20年)。更新手続の概念はなく、25年経過で自動消滅。 |
| 侵害・訴訟対応 | 権利範囲は登録意匠と同一または主要特徴で共通するデザイン全般。侵害者に対し民事訴訟で差止・損害賠償請求可能。警告書送付による事前解決を推奨。税関差止申請可。故意侵害には刑事罰(罰金・懲役)あり。 | 権利範囲は登録意匠および類似意匠。民事訴訟で差止・賠償請求(知財専門部のある地裁で審理)。税関差止制度あり。意匠権侵害は10年以下懲役または1000万円以下罰金の刑事罰(法人は3億円以下罰金)の対象。2020年改正で間接侵害規定を整備。 |
| 国際出願(ハーグ) | 1961年加盟。WIPO経由の国際意匠登録でスイス指定可能。IPIは方式・一部実体審査のみ行い、拒絶理由なければ国際登録から直接国内権利発生。国際登録意匠の保護期間・更新も国内同様に取扱い。 | 2015年加盟。国際出願で日本指定可能。JPOが国内出願同様に実体審査を行うため、拒絶通報があり得る。拒絶対応には日本代理人による意見書・補正が必要。国際登録意匠の存続期間は国内出願と同様(出願日基準で25年)。国際出願しなくともパリ優先権(6か月)で直接出願可能。 |
出典: スイス連邦知的財産庁(IPI)公開情報、スイス意匠法(Designs Act)条文、WIPO Hague Systemガイド等。また、日本特許庁・関連機関の公開資料および弁理士解説記事を参照しました。上述の比較により、スイスと日本の意匠制度は保護期間など一部共通点も有しつつ、審査の有無や手続の柔軟性など実務上の違いが存在することがお分かりいただけるかと思います。両国でビジネス展開する企業にとって、これら制度差を理解し戦略的に権利取得・行使を行うことが重要です。
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)