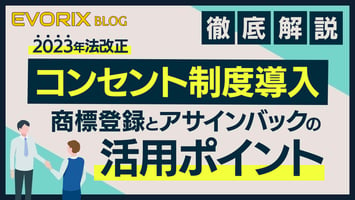承知しました。ブルネイの商標制度について、出願手続、登録要件、異議申立、更新、権利侵害・救済措置、国際制度との関係などを含め、実務向けに専門家向けの詳細な内容でまとめます。...
ネパールの商標制度概要
商標制度の法的枠組みと法的根拠
ネパールにおける商標制度は、特許・意匠と共通の包括法である**「特許意匠商標法(Patent, Design and Trademark Act)」**によって規定されています。この法律は西暦1965年8月30日に制定され(ネパール暦2022年)、それまでの1936年制定の旧法を廃止したものです。その後1987年、1991年、2006年、2010年に改正が行われており、現行制度の法的根拠となっています。商標保護はこの単一の法律の第4章(第16~19条)および第5章に定められています。
同法の下、ネパールでは先願主義(first-to-file)が採用されており、商標権は登録によってのみ発生します。未登録商標に基づく権利主張(パッシングオフ等)は可能なものの成功は極めて困難で、基本的に登録が必要です。商標権の存続期間は登録日から7年間で、以後何度でも7年ごとの更新が可能です(後述)。なお2024年には旧法を全面的に刷新する新たな工業所有権法案が国会承認間近となっており、この新法では周知商標や地理的表示の保護、サービスマーク・団体商標・証明商標制度の創設、不正競争行為の禁止強化など、国際基準に沿った大幅な制度拡充が図られる予定です。
登録可能な商標の種類
ネパールで登録できる商標の種類: 文字(標章)、図形・ロゴ、記号、立体的形状、色彩の組み合わせ、その結合などが挙げられます。商品商標およびサービスマークの両方が保護対象となっており、国際分類(ニース分類)の第1類~第34類(商品)および第35類~第45類(役務)に対応しています。ネパールはニース分類を採用しており、出願時には指定商品・役務をこれらの分類に基づき区分ごとに記載します。一出願で一商標一区分のみ認められ、多区分出願はできません。
登録できない商標: 一般的な登録拒絶事由として、他人の氏名そのもの、一般名称・記述的な標章、各国の国旗・紋章・国際機関の紋章、識別力のない標章、公序良俗に反する標章、誤認を生じるおそれのある標章、地理的表示などは登録不可とされています。また現行法では音商標や香り商標などの非伝統的商標は保護対象に含まれず登録できません。なお立体商標(立体的形状からなる商標)は登録可能であり、文字についてはフォント等を特定しない標準文字商標の制度も導入されています。
(現行法における制度上の制限) 現行の特許意匠商標法には団体商標や証明商標に関する規定がなく、これらの制度は存在しません。また外国の周知・有名商標についても、未登録の場合には現行法上明確な保護規定がなく、先に他者に登録されていると保護が及ばないケースが指摘されています(新法案では周知商標の保護規定が新設予定)。
出願から登録までの手続きと所要期間
手続の流れ: ネパールで商標登録を行うには、まず産業局(Department of Industry, 略称DOI)に商標出願を行います。出願は所定の様式の願書に必要書類と手数料を添えて提出されます(必要書類は後述)。出願後、方式審査および実体審査が行われ、書類不備や分類の誤り、商標の識別力欠如や他人の先登録商標との抵触などがチェックされます。ネパールでは審査で相対的拒絶理由(先願との抵触)も考慮されており、既存の登録商標や先の出願との抵触がある場合は拒絶査定や登録条件付きの通知が発行されます。拒絶理由が通知された場合、出願人は反論・補正を行い、それでも解消できない場合は出願が却下されることになります。
審査を無事通過すると、官報への公告(公開)が行われます。公告後、第三者は一定期間内に異議申立てをすることができます(異議申立制度は後述)。異議申立てがなされず、あるいは異議が棄却されると、商標は最終登録となります。登録時には登録料を納付し、産業局から**登録証明書(Registration Certificate)**が発行されます。
所要期間: 出願から登録証発行までに要する期間は、審査状況や異議申立の有無によって異なりますが、順調なケースで約12~18か月程度とされています。実務上、出願後受理通知まで数日、審査完了まで数か月、公告・異議期間(3~4か月程度)を経て、全く問題がなければ1年程度で登録に至ることが多いようです。ただし異議申立や審査での争点が発生すると、さらに時間を要します。
出願に必要な書類・手数料・代理人制度
必要書類: 2023年5月に産業局が発出した通知によれば、ネパール商標出願時に提出すべき書類は以下の通りです:
-
願書(所定の様式に従い申請人情報・商標・商品役務などを記載)
-
商標見本(提出する商標の表示見本)4点 – 出願書類には商標の鮮明な見本を4枚添付する必要があります。
-
本国登録証または優先権書類(いずれも原本、または公証付きの写し) – 外国法人・個人が出願人の場合、その商標が自国または他国で登録済みであることを証明する書面(登録証の原本または公証済みコピー)を提出しなければなりません。パリ条約に基づく優先権主張を行う場合は、優先権証明書を原本または公証付コピーで提出します。
-
委任状(Power of Attorney) – 出願手続を代理人に委任する場合の委任状。原本か公証付きコピーを提出します。委任状には申請人の署名押印のほか、2名の証人の署名が求められ、さらに公証人による認証が必要とされています。
このほか、ネパール国内の申請者については事業登録証のコピー等が要求される場合がありますが、基本的には上記が必須書類です。また、外国語書面は原則としてネパール語訳の添付が望ましいとされています(公用語はネパール語)。
手数料: 商標出願には所定の官庁手数料がかかります。主要な公式費用は次のとおりです(1ネパール・ルピー≒0.9円):
-
出願料: 2,000ネパール・ルピー(願書提出時に納付)
-
登録料: 5,000ネパール・ルピー(登録査定後、証明書発行前に納付)
-
異議申立料: 1,000ネパール・ルピー(公告された他人の商標に異議を申し立てる際に必要)
-
登録証書の写し発行手数料: 1,000ネパール・ルピー
-
更新料: 500ネパール・ルピー(更新時、後述の期間内に納付)
※上記は官費であり、実際の手続では別途代理人費用等が発生します。
代理人制度: ネパールでは外国企業・外国人在住者が商標出願する場合、ネパール国内に住所を有する代理人を通じて手続を行うのが一般的です。もっとも法律上は申請人がネパールに住所(所在地)を持たない場合でも必ずしも現地住所を提供する必要はなく、外国人が代理人となることも禁止はされていません。しかし実務上、言語や手続面の観点から現地の知的財産専門弁護士・代理人に委任するのが通常です。産業局とのやり取りや提出書類の作成・ネパール語翻訳、現地住所宛の公式通知の受領などを円滑に行うため、現地代理人の選任が推奨されます。またパリ優先権を主張する場合や現地で訴訟が発生した場合にも、現地代理人の存在が不可欠となります。
異議申立制度、取消・無効審判制度などの救済制度
異議申立て(Opposition): 商標出願が官報公告されると、その商標の登録に利害関係を有する第三者は公告日から35日以内に異議申立書を提出することができます。異議申立期間は比較的短く、公告後約1か月強です(※新法施行後は90日に延長予定)。異議申立が提起された場合、申請人は一定期間内に答弁書(カウンターステートメント)を提出して自己の商標を弁護する必要があります。産業局は申立人・申請人双方の主張を考慮して判断を下し、異議が認められれば当該商標出願は登録拒絶となります。異議が棄却されれば出願は登録手続に進みます。異議決定に不服がある当事者は、決定通知から35日以内に裁判所に上訴することが可能です。
商標登録の取消・無効: ネパールでは登録後の商標について、以下のような取消制度が設けられています。
-
不使用取消: 登録から1年以内に商標がネパール国内で使用されない場合、産業局は職権で必要な調査を行ったうえで当該商標登録を取り消すことができます。これは特許意匠商標法第18C条の規定によるもので、登録後速やかな使用が求められる点が特徴です(継続的な不使用期間1年で取消対象となる)。取消の前には、商標権者に対して取消しを免れる正当理由を説明する機会が与えられます。
-
登録無効(職権取消): 登録後であっても、もし当該商標が法第18条(1)に定める登録不可事由に該当することが判明した場合、産業局はその商標登録を**職権で取り消す(無効にする)**ことができます。これは第18条(3)の規定によるもので、たとえば登録後に当該商標が他人の周知商標と抵触していたことが明らかになった場合や、公序良俗違反であった場合などに発動される可能性があります。ただし、この場合も直ちに取消されるのではなく、取消しに先立ち商標権者に意見陳述の機会を与えなければならないと定められています。
上記のほか、登録商標が他人によって不正に出願・登録された場合に、その利害関係人が当該登録の無効を求めて裁判所に提訴することも可能です。また商標権者自身が登録を放棄(抹消)することも認められています。いずれの場合も第一審の判断に不服がある場合は高等裁判所、最終的には最高裁判所まで上訴する道が開かれています。
登録後の保護期間と更新手続き
前述のとおり、ネパールの商標権の存続期間は登録日から7年間です。存続期間満了後は7年ごとに何度でも更新(Renewal)を行うことで、商標権を存続させることができます。更新により商標権の効力が延長される点に回数制限はなく、更新回数に上限はありません。
更新手続: 商標権者は、登録の存続期間が満了した日から起算して35日以内に更新申請を行い、所定の更新料(500ルピー)を支払う必要があります。これは特許意匠商標法第23B条に定められた手続で、満了日後35日以内が通常の更新期間となっています(※現行実務では満了日前の更新手続は認められていません)。万一この期間内に更新できなかった場合でも、6か月以内であれば遅延補充期間が設けられており、延長料1,000ルピーを納付することで更新を行うことが可能です(6か月を過ぎると権利は抹消されます)。更新時には、産業局に所定の更新申請書(様式2(d)等)を提出し、登録証への付記手続きが行われます。更新された商標は更新後も新たな登録証が発行されるわけではありませんが、登録簿上は引き続き有効な商標として存続します。
国際的制度への加盟状況と対応
国際条約への加盟: ネパールは2001年3月にパリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)に加盟しており、パリ条約同盟国の一つです。そのため、パリ条約に基づく優先権主張制度が利用可能であり、他の同盟国での出願日から6か月以内にネパールに出願することで、先の外国出願日を基準とした優先権を主張することができます。また2004年4月に世界貿易機関WTOに加盟し、TRIPS協定(知的財産の貿易関連の側面に関する協定)の義務を履行しています。このほか、ネパールは2006年にベルヌ条約(著作権)にも加盟し、世界知的所有権機関(WIPO)のメンバー国でもあります。
マドリッド協定議定書等への対応: 現時点でネパールはマドリッド協定・議定書(国際商標出願制度)には加盟していません。したがって、ネパールを指定国としてマドリッド方式で国際出願することはできず、ネパール国内で商標権を取得するには直接ネパールに国内出願を行う必要があります。同様に、EUIPO(欧州連合知的財産庁)の欧州連合商標制度や他の地域統一商標制度の適用もネパールには及びません。
ネパール政府は知的財産保護の国際調和を図るため、マドリッドプロトコルへの将来的な加盟も検討していますが、2025年現在まだ実現していません。新たな工業所有権法案でもマドリッド制度への直接的言及はありませんが、国内制度整備が進めば加盟への障壁が下がると期待されています。またネパールはニース分類やウィーン分類(図形分類)など国際的な商標分類も実質的に採用しており、出願書類にそれらを適用しています。なお国際的な商標審査協力(TM5やASEAN商標制度等)には参加していませんが、WIPOの各種トレーニングや協力プログラムには積極的に参画しています。
商標権侵害の対策・執行制度
民事的救済と執行: ネパールにおける商標権侵害の救済は主に民事(行政)手続によって図られます。特許意匠商標法の下では、商標侵害に関する紛争の第一審は裁判所ではなく産業局(DOI)が管轄します。商標権者は侵害者による侵害行為の差止めや損害賠償などの救済を求める申立書を産業局に提出し、産業局が事実調査の上で判断を下します。産業局は差止命令、損害賠償の付与、侵害物品の捜索・差押えなどを命じる権限を有しています。このように産業局は準司法的な役割を果たしており、侵害訴訟における一審裁判所として機能します。産業局の決定に不服がある当事者は、高等裁判所(控訴審)、さらに最高裁判所へと上訴することが可能です。
-
提訴期限: 商標権侵害を理由に救済を求める場合、侵害を知った日から3か月以内に産業局へ申立てを行う必要があります。この期限を過ぎると時効的に救済請求が認められないおそれがあります。したがって侵害を察知したら速やかに証拠を収集し、現地代理人を通じて産業局に申立てを行うことが重要です。
-
要件: 民事救済を受けるためには有効な登録商標であることが前提となります。ネパールで未登録の商標については、先述のとおりパッシングオフ(不正競争行為)に基づく救済を裁判所に求めることも理論上は可能ですが、立証が難しく成功例はほとんどありません。
刑事罰の有無: ネパールでは商標権侵害は刑事上の処罰対象とはされていません。つまり、商標の侵害行為そのものに対して警察が逮捕・起訴するといった直接的な刑事摘発は行われず、商標侵害は民事上の争訟事項として扱われます(※著作権侵害については警察による摘発が可能で刑事罰も規定されています)。ただし特許意匠商標法第19条では、産業局の発する命令に違反した場合などに最大10万ネパール・ルピーの罰金および違反物品の没収を科す規定があり、商標権侵害者に行政処分として罰金刑を課すことは可能です。また新法案では、悪質な商標侵害に対する罰金の上限を従来より大幅に引き上げ(最大100万ルピー)、抑止力を高める条項が盛り込まれています。
エンフォースメント(執行)体制: 商標権侵害品への対策として、民事上の差止命令・損害賠償請求以外にも以下のような手段が存在します。
-
税関における水際取締: ネパールの関税法および輸出入管理法には、知的財産権を侵害する商品の輸出入を差し止める規定があります。商標権者は税関当局に対し、自社の登録商標を無断使用した模倣品等の輸入差止めを申請できます。その際、商標登録証明書、インボイス(請求書)など必要書類を添えて申し立てることで、税関が該当物品の差止めや押収を行います。申請の具体的な期限は法律上明記されていませんが、侵害品が国境を通過する前に迅速に働きかけることが重要です。輸出入管理法では、知的財産保護の目的で政府が特定物品の輸出入を禁止・制限できる旨定めており、必要に応じて行政裁量で侵害商品の流通を止めることが可能です。
-
警察による摘発(限定的): 商標侵害自体は刑事事件とはなりませんが、侵害行為が他の犯罪(例えば詐欺や不正競争防止法違反等)に該当する場合や、著作権侵害など他の知財犯罪と併発している場合には、警察が捜査に乗り出すケースもあります。また2022年頃から、海外ブランドの偽物が市場に出回る事例が増え外国投資の妨げとなっているとの指摘から、新法制定による取締強化が報じられています。その一環で、特に悪質な偽造品については警察や税関と連携した摘発強化が検討されています。
-
その他の救済: 商標権者は侵害者に対し、民事訴訟とは別に不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を提起することも可能です。また模倣品の流通差止めについて、必要に応じ業界団体や国際的なブランド保護団体と協力して市場監視を行い、行政当局に働きかけるケースも見られます。ネパールは近年知的財産意識の啓発に力を入れており、2017年には知的財産政策を策定してIP保護強化を国家優先課題と位置づけました。今後、新法の施行と相まって、商標権侵害への対応が一層充実していくことが期待されています。
【参考文献】 ネパール産業局(知的財産部)公式サイト、WIPO「WIPO Lex」(ネパール法令・条約情報)、日本貿易振興機構(JETRO)「インド周辺国知的財産権制度概説(ネパール編)」、日本国特許庁・ジェトロ海外調査報告書、INTA Bulletin、Apex Law Chamber現地レポート、各種ニュースリリース等。
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)