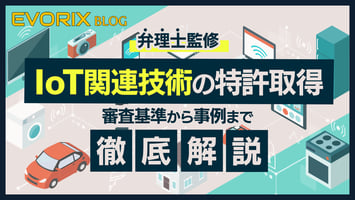バングラデシュの商標制度概要
バングラデシュの商標制度について、知財実務者向けに包括的な概要を調査します。出願から登録、保護期間、異議申立て、更新、使用証明の要否、国際出願制度との関係など、制度全体をカバーする内容でまとめます。
商標の定義と登録可能な標章の範囲
バングラデシュの商標法(Trademarks Act, 2009)は「商標(mark)」を広く定義しており、商品・サービスの出所を示すあらゆる標識が対象となります。具体的には、文字、単語、名称、図形、シンボル、ロゴ、数字、色の組み合わせ、またそれらの組み合わせなど、識別力を有するあらゆる標章が商標登録の対象です。サービスマーク(役務商標)や団体商標・証明商標も登録可能であり、バングラデシュ法は商品商標だけでなくサービス分野にも適用されています。なお 三次元形状 や 音・匂い などの非伝統的商標も、法律上明示的な規定はありませんが「その他の識別力のある標章」に含まれ得るため、実務上も識別力が認められれば登録は可能とされています。
一方、法律で登録が禁止されている商標もあります。公序良俗に反する卑猥・猥褻な標章、現行法に違反する使用態様の標章、他人を欺くおそれのある標章(例えば商品の品質・産地について誤認混同を生じさせるもの)、国民の宗教的感情を害するおそれのある標章、各国の国旗・紋章・政府間機関の徽章など公的標章と同一・類似の標識(正当な許可なく含むもの)は登録が認められません。また、商品やサービスの品質・効能を直接表示するような記述的な標章、ありふれた氏名や地理的名称のみからなる標章、一般的に使用される略語などは識別力がないため原則登録不可ですが、長年の使用により顧客に認識された場合(識別力の獲得)には登録が認められることがあります。バングラデシュは先願主義(first to file)を採用しており、登録によって初めて商標権が発生しますが、未登録商標であっても他人の商品・営業表示として周知なものについては不正競争防止(パッシングオフ)の法理により保護される余地があります。著名商標については未登録であっても異議申立や侵害訴訟で保護が及ぶ場合があり、他人による不正な使用を排除できる制度となっています。
出願手続き(必要書類・言語・代理人・費用)
商標出願は工業省 所管の特許・意匠・商標局(DPDT) に対して行います。出願人はバングラデシュ国内外の個人・法人いずれも可能ですが、外国企業・非居住者が出願する場合は現地の商標代理人(弁護士)の選任が必要です。国内出願であっても、手続の専門性から弁理士・弁護士に依頼するのが一般的です。出願に必要な書類・情報は以下のとおりです。
-
願書(所定の書式): 出願人の氏名・住所(法人の場合は登記情報)など基本情報、商標の詳細(名称や種類)、使用商品・役務の区分などを記載します。様式としてはフォームTM-1を用い、代理人経由の場合は委任状フォームTM-10も併せて提出します。
-
商標見本: 商標を描いた図版(JPEGやPNG形式の画像)を提出します。用紙サイズや貼付方法は規則で定められており、出願書類の所定欄に鮮明な商標見本を貼付します。商標にベンガル語または英語以外の言語による文字が含まれる場合、その翻訳および音訳(発音のカナ表記)を添付し、どの言語かを明記する必要があります。人物の肖像等を含む場合は本人からの承諾書も求められます。
-
商品・サービスの明細: 商標を使用する商品または役務を具体的に記載し、ニース分類の類別ごとに整理します。バングラデシュでは後述のように一出願一類制のため、異なる類の品目については別々に出願する必要があります。
-
優先権主張書類(該当する場合): パリ条約に基づく優先権を主張する場合、最初の出願から6か月以内に出願し、優先権国・出願日等を願書の所定欄に記載します。必要に応じて**外国出願の公認コピー(証明書類)を提出します。
-
手数料の支払証明: 出願時には所定の官費を納付し、その領収証またはオンライン支払の場合の受付番号等を提出します。支払い後、出願受付と出願番号の付与が行われます。
-
委任状(Power of Attorney): 代理人を通じて出願する場合、出願人から署名された委任状を提出します。これは認証不要(サインのみで可)ですが、バングラデシュの印紙(BDT 1,000相当)を貼付する決まりです。
出願言語はベンガル語または英語で行うことができます。出願フォームは基本的に英語で提供されており、外国企業は英語での出願が一般的です。商標の表示に他言語が含まれる場合は上述のとおり翻訳等が必要です。
手数料は商標法規則で細目が定められており、一件当たり下記の官費がかかります(2025年時点):
-
出願料: BDT 5,000(1類につき)。バングラデシュでは1出願で1類のみ指定可能なため、複数類にまたがる場合は類数分の出願が必要です(各出願ごとに5,000タカずつ課金)。
-
公報掲載料: BDT 3,000。審査に合格した場合に商標ジャーナル(官報)に公告する費用です。
-
登録料: BDT 20,000。最終的に登録証発行時に支払う費用です。
これらの官費には別途付加価値税(VAT)15%が課されます。したがって1商標1類を登録まで完了する官庁費用総額は概算で約BDT 28,000(約5万~6万円、USD 300前後)となります。なお代理人に依頼する場合、これとは別に代理人手数料が発生します(依頼内容にもよりますが、出願から登録までUSD 400~800程度が一般的と報告されています)。
出願は現在、DPDT窓口への書面提出が正式な手段です。一部オンライン出願システムも導入されていますが完全には整備されておらず、オンライン申請後に書面提出を求められる場合があります。そのため確実を期すには書面での提出・手続を経る必要があります。
商標分類制度(ニース分類の採用状況)
バングラデシュは商標の区分分類としてニース分類(第11版)を実務上採用しています。公式にはニース協定未加入ですが、出願に際して指定商品・役務は国際的に通用するニース分類の45区分に従って分類する必要があります。具体的には、第1類~第34類が商品、第35類~第45類がサービスに対応しています。願書様式にもニース類を記載する欄があり、DPDTのウェブサイトでも最新のニース表が参照可能です。
重要な点として、バングラデシュではマルチクラス(多区分一括)出願が認められていません。一つの出願申請で指定できるのは1区分のみであり、複数区分にまたがる保護を求める場合は区分ごとに別々の出願を行う必要があります。例えば第9類と第42類の両方で商標を保護したい場合、2件の出願をそれぞれ提出する形となります。したがって、区分数に応じて出願手数料も区分毎に発生します(上記参照)。
バングラデシュはニース協定自体には加盟していないものの、実務上は国際分類を忠実に踏襲しており、指定商品・役務の範囲や表記もニース分類に準拠して審査されます。分類の最新版への対応も適宜行われており、国際的な分類基準と整合した運用が図られています。
審査の内容と方式(絶対的・相対的拒絶理由、審査期間)
バングラデシュでは商標出願に対し、方式審査および実体審査の両方が行われます。まず出願後、DPDTの審査官が願書の記載事項および添付書類を確認し、形式要件を満たしているかチェックします。ここでは願書の記載漏れや分類の誤り、必要書類の欠落、手数料の支払い確認などが検査され、不備があれば補正を求められます。
形式面に問題がなければ、次に実体審査(substantive examination)に移行します。実体審査では主に以下の点が検討されます。
-
絶対的拒絶理由の審査: 商標自体に識別力があるか、法律上登録不可の要素を含まないかがチェックされます。具体的には、その商標が記述的すぎないか(商品・サービスの品質等を直接示す語ではないか)、一般名称・慣用語ではないか、識別力に欠けないか、また前述した公序良俗違反や他人を欺くおそれがないかなどが判断されます。識別力が弱い場合でも使用による識別力取得が立証できれば登録が許されるケースもあります。
-
相対的拒絶理由の審査: 出願商標が既存の他人の商標権と紛らわしくないか(抵触しないか)が審査されます。審査官は商標登録簿や係属中の出願を調査し、同一または紛らわしい類似商標が同じまたは類似商品・役務について登録されていないかを検索します。この調査では外観・称呼・観念における類似性が総合的に判断されます。バングラデシュは他国と同様、既存商標との衝突(相対的理由)も職権審査する制度のため、類似商標が見つかれば拒絶理由となります。
審査の過程で問題があれば、DPDTから審査報告(オフィスアクション)が通知されます。拒絶理由通知には、識別力欠如・記述的であること、既存商標と紛らわしいこと、形式要件不備など理由が具体的に示されます。出願人は通常2か月以内に応答する必要があり、期限内に意見書や補正を提出して拒絶理由の解消を図ります。必要に応じて商品範囲の限定(補正)や商標の図案変更等で対応することも可能です。正当な理由があれば期限延長も申請できます(規則では追加で最大2か月の延長が可能とされています)。
他人の先行商標との抵触が唯一の問題である場合、同意書(レター・オブ・コンセント)の提出によって拒絶を解消できることがあります。先行権者が当該出願商標の登録・使用に同意している旨を記載した正式な同意書を提出すれば、審査官はそれを考慮して拒絶理由を撤回しうる運用です。同意書には両商標の関係や共存に問題がない理由を明記し、先行商標権者の署名が必要です。
審査に要する期間は近年長期化する傾向にありますが、概ね出願から第一次審査結果が出るまで約12~14か月程度が一般的と報告されています。その後、拒絶理由対応や公告手続を経て、順調なケースで出願から登録完了まで合計18~24か月(1年半~2年)ほど要するのが標準的なタイムフレームです。審査段階で異議や補正が生じるとさらに時間を要し、特に異議申立があった場合は解決まで数年かかることもあります。
審査を無事クリアすると、次の公告・異議申立段階に進みます。なお審査結果に不服がある場合、出願人はDPDTに対し再考を求めることもできますが、正式には高等法院への上訴が用意されています。商標法第123条の規定により、登録官(Registrar)の決定に不服がある利害関係人は、高等法院部(最高裁判所の一部)に上訴提起することができます。
異議申立制度(提出期限・要件・手続)
DPDTによる審査で登録適格と判断された商標は、登録に先立ち商標公報(Trademarks Journal)に掲載されます。掲載後、第三者による異議申立(opposition)の機会が設けられており、公告発行日から2か月間は誰でもその商標登録に対する異議を申し立てることが可能です。この2か月の法定異議期間内に所定の異議申立書(フォームTM-5)を提出することで、当該商標の登録手続きを一時停止させ、異議の審理手続きに入ります。異議期間は申立人の請求により最大1か月延長することも可能で、延長には別途申請と手数料が必要です。
異議の申立ができる者は、自らの権利や業務にその商標登録が不利益を及ぼすおそれがあると考える者であれば原則として誰でも可能です。典型的には、同一・類似商標を先に使用または出願・登録している競業者などが想定されます。異議申立の根拠(理由)として主張できる事項は多岐にわたり、絶対的拒絶理由・相対的拒絶理由のいずれも指摘可能です。例えば「申請商標は記述的で識別力がない」「他人(申立人)の周知商標と紛らわしく混同を生じる」「出願が誠実でなく、模倣・悪意に基づくものである」等が主要な異議理由になります。著名商標の希釈化のおそれや、公序良俗違反といった点も異議理由として主張可能です。要するに、その商標が商標法上登録してはならないものであること、または申立人の先の権利に抵触することを示すあらゆる論点が異議理由となり得ます。
異議申立が提出されると、まずDPDTが形式要件を確認したうえでその内容を申請人(出願人)に通達します。以後、異議申立人(オポーネント)と出願人(被申立人)の間で答弁書・反論書の提出による書面審理が行われます。双方はそれぞれ主張理由を裏付ける証拠(例えば先使用の証明、周知性の立証資料など)を提出する機会が与えられます。審理の過程で必要に応じ口頭審理(ヒアリング)も行われ、DPDTの商標登録官または指定審理官が双方の主張・証拠を検討します。最終的に登録官が判断を下し、異議申立を認容(出願を拒絶)するか、棄却(出願を登録許可)するかの決定がなされます。
異議手続の期間は事案によって様々ですが、異議が発生すると登録まで数か月から数年の遅延が生じ得ます。異議申立が却下されれば出願はそのまま登録に進み、認容された場合は当該商標は登録されず出願は拒絶となります。なお異議決定に不服がある当事者(申請人・申立人の双方)は、商標法に基づき高等法院部に上訴することが可能です。裁判所での争いとなった場合、最終的な決着までさらに年月を要する場合があります。
登録と保護期間(初回の保護期間、更新制度、更新手数料)
異議期間を経て問題がなければ、商標は正式に登録(Registration)されます。登録にあたってはDPDTより登録料(前述)を納付する通知が送られ、支払いが確認されると商標登録原簿への登録が完了し登録証(Registration Certificate)が発行されます。登録証には登録番号、商標の詳細、保護対象の商品・役務、出願日および登録日などが記載されます。
商標権の存続期間は、バングラデシュでは初回登録時は7年間と定められています。この7年は法律上「出願日(申請日)から起算して7年」と規定されており、実務上は登録完了時点で過去に遡って出願日から7年後まで有効になる形です。以後は10年ごとに更新(renewal)を行うことで、商標権を何度でも 10年単位で延長することができます。したがって更新を怠らない限り、商標権の存続期間に上限はなく 半永久的に保護 を維持することも可能です。
更新手続は、有効期限が満了する前にDPDTに更新申請(Renewal Application)を行い、所定の更新料を納付することで完了します。更新申請は通常、満了期限の前後で一定期間受け付けられます。バングラデシュ商標法では満了前6か月以内に更新手続きを行うことが推奨されており、万一期限までに更新できなかった場合でも猶予期間(グレースピリオド)として満了後最大6か月程度は遅延更新が認められています(追加料金が発生)。具体的には、期限後4か月以内であれば通常の更新料に加え遅延料BDT 5,000と付加価値税を支払うことで更新可能とされます。この猶予期間を過ぎても更新されない場合、商標は登録原簿から抹消され、権利失効となります。
2025年時点の更新料は1商標あたり約BDT 15,000~20,000程度(10年ごと、1区分につき)と報告されています(付加価値税を別途加算)。更新時には使用証明の提出は不要ですが、後述のように長期間未使用の場合は取消リスクがあるため、権利維持のためにも商標の継続使用が望まれます。
使用証明制度(使用義務・不使用取消請求)
バングラデシュ商標法では、登録商標の継続的な使用が推奨されていますが、登録段階で直ちに使用していなくとも権利は発生します。出願時や登録時に商標の使用実績を証明する必要はなく、「使用していない商標」でも登録は可能です。また、登録から一定期間内に使用を開始しなければならないという明文の義務規定もありません。つまり、意図的に使用する予定(intention to use)さえあれば未使用でも出願・登録でき、更新時にも使用状況の申告や証拠提出は求められません。これは多くの国の先願主義商標制度と同様の運用です。
しかし、登録後まったく使用されていない商標については、一定期間経過後に第三者から不使用取消(cancellation for non-use)を請求されるリスクがあります。バングラデシュでは、登録から5年間連続して商標を使用していない場合、利害関係人はその商標登録の取消しを求めることができます。商標法上、「登録日から5年経過時までに一度も正当な使用がされていない場合」または「登録後5年以上連続して使用が中断している場合」に、取消事由が生じると解釈されています。実務的には、登録公報発行日(登録日)から5年間利用実績がないと取消請求の対象となり得ます。
不使用取消の手続は、利害関係人(例: 同一・類似商標を使用したい第三者など)がDPDTまたは裁判所に対して取消申立を行うことで開始されます。申立人は当該商標が指定商品・役務について登録後5年以上使われていない事実を主張・立証する必要があります。これに対し商標権者は、使用を開始・再開している場合はその証拠を提出し防御します。正当な理由のない不使用が認定されると、商標登録は取消・抹消されます。取消が確定した場合、当該商標は登録簿から削除され、以後同一商標について他者が出願可能となります。
なお、「使用」の範囲には商標権者自身の使用だけでなく、許諾を受けたライセンシーによる使用も含まれます。商標法には防御的商標(Defensive Mark)の規定もあり、著名商標については非類似商品に使用していなくても権利維持できる特例も存在します。しかし一般的な商標については、市場における genuine use(真正な使用)が5年以上ないと取消リスクが現実化します。そのため商標権者は、登録後はできるだけ速やかに商標の使用を開始し、継続して使用することが望まれます。また、5年の不使用期間が経過する前に使用を再開すれば取消請求を回避できます。
バングラデシュでは、不使用取消以外にも商標の取消・無効制度が整備されています。例えば登録から5年以内であれば、識別力欠如や登録時の違法性を理由に無効審判(取消訴訟)を提起することも可能です。しかし使用に関する取消については上記5年経過が一つの目安となっています。万一不使用取消請求がなされた場合に備え、商標権者は日頃から使用証拠(販売実績、広告資料など)を保存しておくことが重要です。
権利侵害と救済措置(民事・刑事・税関措置)
バングラデシュにおける商標権侵害(商標の無断使用)に対しては、民事・刑事の双方で救済措置が用意されています。
民事上の救済: 商標権者は自己の登録商標が第三者に無断使用された場合、地方の民事裁判所(一般には地裁/District Court)に対して差止め請求訴訟を提起できます。裁判所は侵害行為の差止命令(仮処分・恒久的差止)を発令し、被告に違法な商標使用の中止を命じることができます。また損害が生じていれば損害賠償請求も可能で、実損害の賠償のほか、悪質な侵害者に対しては利益の供与(不当利得相当額の返還)を求めることもできます。さらに裁判所は、侵害品(違法な商標を付した商品)の廃棄命令や、誤認払拭のための訂正広告の命令を出すことも認められています。侵害訴訟においては迅速な救済のため、訴訟係属中に暫定的な仮処分(仮差止)を数週間~数ヶ月で取得することも可能です。なお、未登録商標の場合でも、他人の営業上の信用を不当に利用する行為について不正競争防止(パッシングオフ)の法理に基づき民事救済(差止・損害賠償)を求めることができます。
刑事上の救済: 商標法および刑法には、商標に関する違法行為に対する刑事罰規定が設けられています。例えば、他人の登録商標を無断で商品に付して販売する行為(商標権侵害の意図的行為)や、登録商標であると偽って表示する行為は犯罪とされており、摘発された場合罰金刑や懲役刑が科される可能性があります。バングラデシュ刑法(1860年法)の第478~486条も商標に関する詐欺的行為を犯罪として規定しており、例えば他人の商標を偽造・模倣する行為や偽造商標の販売は刑事罰の対象です。権利者は警察など捜査当局に刑事告訴(苦情申立)を行い、摘発・差押えを求めることができます。警察は証拠が揃えば侵害者を逮捕・起訴し、裁判所が有罪と認めれば科料・禁錮などの刑が科されます。刑事手続は抑止効果が高いため、悪質な模倣品業者に対しては民事と並行して刑事措置が取られることもあります。
税関による水際措置: バングラデシュはTRIPS協定の要請に従い、税関での知的財産侵害品の摘発制度も整備しています。商標権者は自らの登録商標を税関当局に登録(recordal)し、侵害物品の輸出入監視を依頼することができます。また、特定の輸入貨物が自社商標の模倣品であると判明した場合、税関に通報し輸入差止めを申立てることができます。税関当局は権利者からの申し立てに基づき当該貨物を検査・差し押さえし、正規品でないと判断されれば没収・廃棄等の措置を取ります。このような国境措置により、海外からの偽ブランド品などの流入を水際で阻止することが可能です。もっとも、税関が自主的に侵害品を探知・摘発するには限界があるため、権利者自身が情報提供や通報を積極的に行うことが重要です。
以上のとおり、バングラデシュの商標法制は民事救済・刑事罰・税関差止めの全てを備えており、商標権者は状況に応じた手段で権利を行使できます。侵害訴訟の出訴期限(時効)は侵害を知った日から3年とされ、迅速な対応が求められます。なお裁判制度としては、高等法院部が地裁判決の控訴審を担当し、さらに上級の最高裁判所(Appellate Division)まで上告可能な二審制が敷かれています。
国際出願制度との関係(マドリッド協定議定書への加入状況・活用方法)
マドリッド協定および議定書(国際商標登録制度)へのバングラデシュの加入状況ですが、2025年時点でバングラデシュは未加盟です。そのため、マドリッドプロトコルを利用してバングラデシュを指定国に含む国際商標出願を行うことはできません。例えば日本やEUで国際登録を出願しても、現状ではバングラデシュにその効力を及ぼすことはなく、バングラデシュで商標権を得るには直接バングラデシュに国内出願する必要があります。外国企業がバングラデシュで商標保護を得たい場合、各国毎の国内出願が必要となり、代理人を通じDPDTへ申請するのが唯一のルートです。
同様に、バングラデシュ国内企業が自国商標を海外で保護したい場合も、現時点ではマドリッド経由で一括出願することはできません。各国の商標庁に直接出願するか、あるいは地域共同体商標制度(EUIPO等)が利用可能な場合はそちらを検討することになります。もっともバングラデシュ政府内では国際的な商標登録制度への参加について議論・検討がなされており、近い将来マドリッド議定書への加盟を目指す可能性も指摘されています(専門家から早期加盟の提言も出されています)。加盟すれば、バングラデシュ企業が国内登録を基礎にマドリッド出願で多数国に商標を出願できるようになり、また外国企業もマドリッド経由でバングラデシュを指定して権利取得が容易になるため、経済界からも加盟を望む声が上がっています。
国際条約面では、バングラデシュはパリ条約(1883年)に1991年加盟済みであり、これにより外国出願から6か月以内の優先権主張が認められています。またWTOのTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)も2000年から順守しており、商標についても最低基準が整備されています。ニース分類も非加盟ながら実務採用しています。これら国際的枠組みの下、バングラデシュは国内法を整備しており、未加盟のマドリッド協定についても今後の法改正による受入れが注目されます。
関連法令と主管官庁
主要な商標関連法令は以下のとおりです。
-
商標法2009年(Trademarks Act, 2009) – 現行の商標の登録・保護に関する基本法です。1940年制定の旧商標法を全面改正・更新したもので、登録手続、商標権者の権利、侵害行為の定義、救済手段、商標の譲渡・ライセンス、違反行為に対する罰則、不使用による取消、その他商標に関する事項を網羅しています。附則で不正競争行為の差止め(周知表示の保護)についても規定しています。
-
商標規則2015年(Trademarks Rules, 2015) – 上記商標法の施行規則で、出願様式、手数料、審査・異議の手順、各種届け出手続等の詳細を定めています。申請書類の様式や提出方法、登録簿の管理、期限延長の手続など実務面の規定が含まれます。
-
特許法1911年・意匠法1911年 – 商標と直接の関係は薄いですが、工業所有権全体の旧法体系の一部です(現在はそれぞれ改正法あり)。
-
刑法1860年 – 第478条~第486条に商標に関する犯罪(商標の偽造・不正使用など)とその刑罰が定められています。商標法2009にも違反行為の罰則規定がありますが、刑法の規定も補充的に適用されます。
-
その他関連 – 消費者保護法や薬事法など、商品表示やラベルに関する業法で商標表示の適正化が求められる場合がありますが、商標権そのものの存否は商標法に従います。またバングラデシュは経済協定上、上記パリ条約・TRIPS協定の義務を負っており、国内法もそれに整合するよう運用されています。
主管官庁は、工業省傘下の**特許・意匠・商標局(Department of Patents, Designs and Trademarks, DPDT)**です。DPDTが商標の出願受付から審査、登録査定、登録簿の維持管理、更新手続、異議申立や取消・無効の審理など一連の行政事務を担当しています。DPDTには商標登録官(Registrar of Trademarks)が置かれ、商標法に基づく様々な裁量権を行使します。DPDTは工業省(Ministry of Industries)配下にありますが、実務的には知的財産庁として独立に機能しており、世界知的所有権機関(WIPO)とも連携しています。
裁判管轄については、商標に関する紛争(例えば異議申立の決定への不服、侵害訴訟など)は高等法院部(最高裁判所の一部門)が管轄します。登録に関する争いはまずDPDTが管轄し、その決定の控訴先が高等法院となります。一方、侵害など民事訴訟は通常、第一審は地方の地裁(District Judge Court)で行われ、控訴があれば高等法院部、最終的に最高裁判所(Appellate Division)まで上告可能です。刑事事件の場合、下級刑事裁判所で審理され、重大事案は高等法院へ移送されることもあります。
以上、バングラデシュの商標制度は2009年の現行法の下で運用されており、国内制度として成熟しつつあります。近年の法改正や国際化動向としては、著作権法の改正や電子出願システムの導入など知財全般の整備が進められており、商標分野でも国際登録制度への加盟検討などアップデートが注目されています。商標実務者(弁理士)にとっては、国内独自の規定(初回7年登録など)の把握と、国際的な制度との違いを踏まえた対応が求められるでしょう。今回まとめた概要が、バングラデシュでの商標制度を体系的に理解する一助となれば幸いです。
参考文献: 商標法2009年・同規則2015年(バングラデシュ)、DPDT公式情報、WIPO Lex、各種実務解説等.
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)

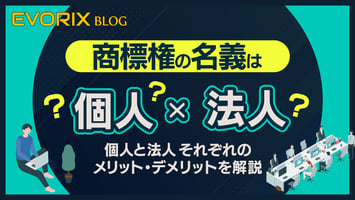
.jpg?height=200&name=unnamed%20(24).jpg)