アップル社の知財ミックス(特許権×意匠権) アップル社の知財ミックス事例についてご紹介します。事例は、スマホのロック状態を解除するボタンに関する権利です。 ...
「あの時こうしていれば…」知財トラブル・失敗事例集(意匠編)
意匠権は、製品のデザインを法的に保護する強力な武器です。しかし、その活用には落とし穴も多く、「もっと早く出願していれば…」「こういう形で権利化しておけば…」という後悔の声は後を絶ちません。本稿では、実務で起こりがちな失敗パターンを事例形式で紹介し、同じ轍を踏まないための教訓を考えていきます。
事例1:発表会での「うっかり公開」で新規性喪失
何が起きたか
ある家電メーカーのデザイナーAさんは、画期的なデザインの加湿器を開発しました。社内での評判も上々で、業界の展示会で披露することになりました。展示会は大成功。多くのバイヤーから注目を集め、SNSでも話題になりました。
ところが、意匠出願の手続きは展示会の「後」に予定されていたのです。展示会で製品が公開された時点で、その意匠は「公知」となり、原則として新規性を失ってしまいました。
何が問題だったのか
意匠法では、出願前に公開された意匠は新規性がないとして登録を受けられないのが原則です。日本には「新規性喪失の例外規定」があり、一定の条件下で救済される可能性はありますが、この手続きには厳格な要件があります。具体的には、公開から1年以内に出願し、かつ公開の事実を証明する書面を提出しなければなりません。
Aさんのケースでは、この例外規定の存在自体を知らなかったため、必要な手続きを踏まずに出願してしまい、後から拒絶理由通知を受けることになりました。
教訓
製品発表・展示会・プレスリリースの予定がある場合は、必ずその「前」に意匠出願を完了させることが鉄則です。どうしても公開が先になってしまう場合は、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための要件を事前に確認し、漏れなく手続きを行う必要があります。また、海外展開を考えている場合は要注意です。新規性喪失の例外規定は国によって要件が異なり、そもそも例外を認めない国もあります。
事例2:「全体意匠」だけの出願で模倣を許す
何が起きたか
文具メーカーB社は、独特の握り心地を実現したボールペンを開発しました。グリップ部分の波形パターンが特徴的で、これがユーザーから高い評価を得ていました。B社は製品全体の意匠を出願し、無事登録を受けました。
ところが数年後、競合のC社が類似のグリップパターンを採用した製品を発売。B社は意匠権侵害を主張しましたが、C社製品は全体的な形状がB社製品とは異なっていたため、「類似」とは認められず、権利行使ができませんでした。
何が問題だったのか
意匠の類否判断では、物品全体の美感が比較されます。B社が登録していたのは「ボールペン全体」の意匠であり、グリップ部分だけを切り出して保護するものではありませんでした。C社は、グリップのパターンは似せつつも、クリップの形状やペン先のデザインを変えることで、全体としての類似を回避したのです。
教訓
製品の競争力の源泉となっている部分が特定のパーツにある場合は、「部分意匠」の出願を検討すべきです。部分意匠とは、物品の一部分のみを意匠登録の対象とする制度で、その部分が類似していれば、周囲の形状が異なっていても権利を主張できる可能性があります。B社がグリップ部分の部分意匠も出願していれば、C社製品に対して権利行使できた可能性が高いのです。
事例3:「関連意匠」制度を知らずにバリエーション展開
何が起きたか
家具メーカーD社は、人気の椅子シリーズについて、基本形の意匠を出願・登録しました。その後、カラーバリエーションや素材違いの製品を次々と発売しましたが、それらについては「どうせ似ているから権利範囲に入るだろう」と考え、追加の出願をしませんでした。
ところが、競合E社が、D社のバリエーション製品に近いデザインの椅子を発売。D社が権利侵害を主張したところ、E社は「登録意匠とは非類似であり、D社のバリエーション製品自体も未登録なので自由に実施できる」と反論しました。裁判の結果、E社製品は登録意匠とは類似しないと判断され、D社は敗訴しました。
何が問題だったのか
意匠権の効力は、登録意匠と「同一または類似」の意匠に及びます。しかし、その類似の範囲は必ずしも広くありません。D社は、基本形から少し変えたバリエーションも当然保護されると思い込んでいましたが、そのバリエーションが類似範囲の境界線付近にあった場合、競合他社はそのすぐ外側で模倣することが可能になってしまいます。
教訓
日本の意匠法には「関連意匠」制度があります。これは、本意匠(基本となる意匠)に類似する意匠を関連意匠として出願・登録することで、本意匠とは別個独立の権利として保護を受けられる制度です。関連意匠を活用すれば、デザインのバリエーションごとに独自の権利を持つことができ、保護の網をより広く張ることができます。製品ラインナップを展開する際は、関連意匠の戦略的活用を検討しましょう。
事例4:「物品」の特定ミスで思わぬ抜け穴
何が起きたか
ベンチャー企業F社は、斬新なデザインの卓上ライトを開発し、意匠出願を行いました。物品名は「電気スタンド」として登録を受けました。
その後、競合G社がほぼ同じデザインの製品を発売しましたが、それは「アロマディフューザー」として販売されていました。光る機能はあるものの、主たる用途は芳香拡散であるとG社は主張しました。
何が問題だったのか
意匠法では、意匠は「物品」の形状等として定義されます。そして、意匠の類否判断においては、物品の同一性・類似性も考慮されます。F社の「電気スタンド」とG社の「アロマディフューザー」は、用途・機能の観点から非類似の物品と判断される可能性があり、そうなれば形状が酷似していても意匠権侵害を問えないことになります。
教訓
デザインの模倣が予想される場合、同じ形状が転用されうる物品についても意匠出願を検討すべきです。また、2020年の意匠法改正で導入された「内装の意匠」や、物品に該当しない「画像の意匠」「建築物の意匠」など、保護対象が拡大していますので、自社のデザインがどのカテゴリーで最も効果的に保護できるかを多角的に検討することが重要です。
事例5:海外展開時の「優先権」期限切れ
何が起きたか
アパレルブランドH社は、新作バッグのデザインについて日本で意匠出願を行いました。その後、欧州・アジア各国でも発売することになりましたが、海外の意匠出願手続きは後回しにしていました。
日本出願から8カ月後、ようやく海外出願の準備を始めたH社は、弁理士から衝撃的な事実を告げられます。意匠の優先権主張期間は特許や商標(12カ月)と異なり、わずか「6カ月」しかないのです。すでに期限を過ぎており、優先権を主張することはできませんでした。
その結果、日本出願から8カ月の間に製品が市場に出回っており、その事実が各国で新規性を否定する先行技術となってしまう可能性が生じました。
何が問題だったのか
パリ条約に基づく優先権制度は、最初の出願から一定期間内であれば、他の加盟国への出願について最初の出願日を基準に審査を受けられる制度です。しかし、意匠については優先期間が6カ月と短く、特許や商標の12カ月と同じ感覚でいると期限を徒過してしまいます。
教訓
海外展開を少しでも視野に入れている製品については、日本出願と同時に海外出願のスケジュールも立てておくべきです。意匠の優先期間6カ月は、翻訳や現地代理人の手配を考えると決して長くありません。また、ハーグ協定(意匠の国際登録制度)を活用すれば、一つの出願で複数国への保護を求めることができ、手続きの効率化が図れます。
事例6:出願前の「秘密保持」が不十分
何が起きたか
スタートアップI社は、革新的なウェアラブルデバイスのデザインを外部のデザイン事務所J社と共同開発しました。開発過程で、J社の担当者はデザイン案をSNSに投稿してしまいました(社名は伏せたものの、デザインの特徴は明確に見て取れるものでした)。
I社がこの事実を知ったのは、意匠出願後のこと。審査過程で、このSNS投稿が公知文献として引用され、新規性がないとの拒絶理由通知を受けることになりました。
何が問題だったのか
共同開発や外部委託の場合、デザインの秘密管理は自社だけでは完結しません。外部の協力者が意図せず(あるいは意図して)デザインを公開してしまえば、新規性は喪失します。秘密保持契約(NDA)を締結していても、いったん公開されてしまえば新規性喪失の事実は覆りません。
教訓
外部との協業時には、秘密保持契約の締結はもちろん、「何をどこまで開示してよいか」「SNS等への投稿は一切禁止」といったルールを明確に文書化し、周知徹底することが必要です。また、重要なデザインについては、開発の初期段階から意匠出願のタイミングを意識し、公開リスクが生じる前に出願を済ませることが理想的です。
まとめ:意匠戦略を成功させるための心得
これらの事例から浮かび上がる共通の教訓は、意匠権の活用には「先を読んだ計画性」が不可欠だということです。
第一に、「出願のタイミング」が極めて重要です。公開前に出願を完了させることが原則であり、展示会・発表会・製品発売などのスケジュールから逆算して出願計画を立てる必要があります。
第二に、「権利範囲の設計」を戦略的に行うことです。製品全体の意匠だけでなく、部分意匠や関連意匠を組み合わせることで、模倣者が権利の網をくぐり抜けにくい布陣を敷くことができます。
第三に、「グローバルな視点」を持つことです。意匠法は国によって制度が異なり、優先期間も短いため、海外展開を見据えた早期の戦略立案が求められます。
第四に、「社内外の連携」です。デザイン部門・知財部門・マーケティング部門・外部パートナーが情報を共有し、意匠出願のタイミングや秘密管理について共通認識を持つことが、トラブル防止の要となります。
意匠権は、取得すれば終わりではなく、そこからがスタートです。適切な権利を適切なタイミングで取得し、それを事業戦略と連動させて活用することで、デザインという無形の資産を最大限に活かすことができるのです。
ご質問や、特定の論点についてより深く知りたい場合は、お気軽にお尋ねください。個別の事例に近いシナリオでのシミュレーションなども可能です。
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)

.jpg?width=1024&height=572&name=unnamed%20(32).jpg)
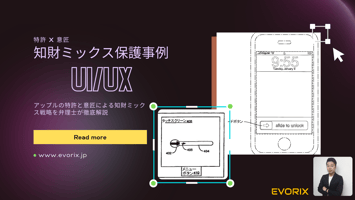
.jpg?height=200&name=unnamed%20(30).jpg)
