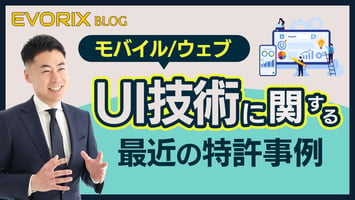意匠登録の要件 バングラデシュ – バングラデシュでは2023年に新たな工業意匠法(Industrial Design Act, 2023)が制定されており、意匠登録の主な要件として...
ミャンマーの意匠制度
1. 意匠出願手続の流れ
ミャンマーでは、意匠登録の出願は商務省傘下の知的財産局(Intellectual Property Department, IPD)の意匠登録官(Design Registrar)に対して行います。2024年2月から新制度による意匠出願の受け付けが正式に開始されており、出願方法はオンラインの電子出願システム(WIPO File)による提出、知的財産局窓口への直接提出、あるいは郵送による提出に対応しています。外国在住の出願人がミャンマーに意匠出願する場合、現地の代理人を選任することが義務付けられています。一つの出願で複数の意匠を同時に手続することも可能ですが、その場合すべての意匠が同一のロカルノ分類クラスに属する必要があります。ただし電子出願システムでは一つの出願に一意匠しか含めることができず、複数意匠をまとめてオンライン出願することは許可されていません。
出願に際して必要な主な書類・情報は以下の通りです。
-
出願人・創作者の情報: 出願人の氏名・住所・(法人の場合)法人登録番号・連絡先、および創作者が出願人と異なる場合はその創作者の氏名・住所・国籍。
-
身分証明書の写し: 出願人が個人の場合、その国民登録証(NRC)またはパスポートのコピー。
-
意匠の図面または写真: 出願する意匠を表す図面や写真(白黒またはカラー)。画像サイズは最大16cm×16cmまで。
-
三次元物品の図面: 意匠が三次元形状を有する場合、7方向(斜視図、前・後・上・下・左・右側面図)の図面または写真を提出。
-
物品の区分: 出願する意匠が使用される製品の種類(ロカルノ国際分類に基づく区分)。
-
意匠の説明: 意匠の特徴を記載した簡潔な説明(100語以内)。
-
代理人関連書類: 代理人経由で出願する場合、代理人の氏名・住所・連絡先情報と、所定の委任状(ID-2フォーム)を提出します。委任状には出願人が署名し、公証人による認証を受ける必要があります。
-
譲渡契約書: 出願人が創作者本人でない場合(創作者から権利を承継した場合)、創作者から出願人への意匠の譲渡契約書またはその写し。
-
優先権関連書類: 外国で先に出願した同一意匠の優先権を主張する場合、その外国出願の詳細(出願番号、出願日、出願国など)および優先権書類(外国官庁発行の出願受付証明や登録証のコピーなど)。
出願後、まず方式審査(形式的要件の審査)が行われ、願書や添付書類が法定の要件を満たしているか確認されます。方式審査をクリアした出願は官報等で公開(公告)され、その公告日から60日間は異議申立て期間となります。利害関係人はこの期間中に、新規性の欠如などを理由として当該出願に異議を申し立てることができます。公告から60日以内に異議申立てがなければ、意匠はそのまま登録に至り証明書が発行されます。異議が提起された場合、知的財産局の登録官が異議理由を精査し、異議を認容するか棄却するか(ひいては出願を拒絶するか登録を認めるか)を決定します。なお、出願人は必要に応じて意匠の公開を最長18か月間まで遅らせる延期申請を行うことができ、IPDは最長18か月の公告延期を認めています。また、ミャンマーは未だパリ条約に加盟していませんが、本制度では外国出願から6か月以内であれば優先権の主張が可能であり、出願時に優先権書類を提出することで国内出願でも同一の優先日を認めてもらうことができます。
2. 意匠権の存続期間および更新
ミャンマーにおける意匠権(意匠登録の存続期間)は、出願日から起算して5年間です。意匠権者は登録から5年の満了前に更新申請を行うことで、更に5年間の存続期間延長を受けることができ、同様の更新を最大2回まで繰り返すことが認められています。したがって、一つの意匠登録について最長で出願日から通算15年間まで保護を維持することが可能です。更新手続は当初の存続期間が満了する6か月前から申請することができ、万一更新期限を過ぎてしまった場合でも、満了後6か月以内であれば所定の追加料金を支払うことで更新申請を行う救済措置(グレースピリオド)も設けられています。この猶予期間(6か月)を過ぎても更新がなされなかった意匠登録は、その時点で権利消滅(抹消)となります。
3. 保護される意匠の定義および範囲
ミャンマー工業意匠法における「意匠(Industrial Design)」とは、工業製品または手工芸品として生産される物品の外観デザインを意味します。その形状・輪郭・模様・色彩・質感・材料・表飾などによって構成される製品の見た目の特徴(全体または一部)が意匠の対象です。意匠として登録を受けるためには、新規性および独自性(オリジナリティ)を備えていることが要求されます。言い換えれば、既存の他のデザインを模倣したものでなく、出願日以前(優先権を主張する場合は優先日以前)に国内外で公に開示・公知になっていないデザインであることが必要です。既に知られた意匠の単なる集合や、従来のデザインと比較してわずかな差異しかないような意匠は、新規なものとは認められません。これらの要件は世界共通の水準に沿ったものであり、ミャンマー法も意匠の国際分類としてロカルノ分類を採用するなど国際的な基準に整合しています。
一方、法律上保護の対象から除外される意匠も定められています。製品の技術的機能を確保するためだけに不可欠な形状(つまり純粋に機能に由来するデザイン)は意匠登録の対象とはならず、また公の秩序や安定、道徳や宗教上の感情、国内の伝統文化を害するおそれのある意匠も登録を受けることができません。例えば、製品の構造や機能そのものに由来するデザイン(機能美のみの形状)や、社会通念上不道徳・冒涜的とみなされる図柄等は法律で登録不可とされています。
4. 審査制度(方式審査・実体審査の有無、審査機関など)
ミャンマーの意匠出願に対する審査は、まず方式審査(フォーマリティチェック)が行われます。願書の記載事項や添付書類が所定の形式・要件を満たしているかを審査官が確認し、要件不備があれば補正が求められます。方式面で適合と判断されると出願が公開され、官報公告後60日間の異議申立て期間に入ります。ミャンマーでは実質的な新規性・創作性について出願段階で厳格な審査を行う制度ではなく、公開後の異議申立て手続きによって実体的な審査機能を担保しています。すなわち、公告から60日以内に第三者が**「その意匠は定義上の意匠に該当しない」、「新規性がない」、「法定の保護除外事由に該当する」、「出願人にその意匠を出願する権利がない」**等を理由に異議を申し立てることができ、異議が出た場合には知的財産局(登録官)がその内容を審査して登録の適否を判断します。この異議期間に異議が全く出されなければ、特段の実体審査を経ることなく登録が認められる仕組みです。
審査・登録業務はミャンマー知的財産局(IPD)が所管します。同局の意匠審査官(Examiner)は出願の審査報告を作成し、登録官(Registrar:知的財産局の長)が最終的に登録査定または拒絶の決定を下します。登録官は公告期間内に異議がなかった出願について登録を許可し、異議が提出された場合はその審理結果に基づき登録を認めるか拒絶するかを決定します。審査・異議を経て登録が認められた意匠には登録証が発行され、意匠公報等に登録公告が掲載されます。
5. 意匠の具体的な実施例や登録実績
ミャンマーでは長年、近代的な意匠登録制度が存在せず、デザインの法的保護手段が限られていました。過去には意匠の創作者や企業は、ヤンゴンの登記所(Office of the Registrar of Deeds and Assurances)において意匠の所有権宣言(Declaration of Ownership of Design)を行い、その旨の**カウショナリー・ノーティス(権利警告公告)**を英字新聞に掲載して周知を図るという措置が取られていました。これは当該デザインの所有権が自分にあることを公示し、万一模倣品が出回った場合に不正競争行為(パッシングオフ)による救済を請求するための準備的な手段でした。しかしこの方法では正式な登録による独占権が与えられるわけではなく、あくまで第三者への牽制と限定的な法的救済手段にとどまっていました。
2024年に工業意匠法が施行され意匠の登録制度が整備されたことで、ミャンマーでも正式な意匠権の付与が可能となりました。現在では国内企業・個人はもちろん、海外企業も自社製品の外観デザインやパッケージデザインなどを積極的にミャンマーに出願し始めており、新制度の下で少しずつ登録件数が増加しています(※具体的な登録統計は公開されていませんが、2024年2月の出願受付開始以降、出願が順次行われています)。登録された意匠の権利者には、登録意匠を無断で製造・販売・輸入する行為を差し止める排他的権利が付与され、さらにその意匠権を第三者にライセンスしたり譲渡したりすることで経済的利益を得ることも可能です。例えば、ある企業が自社の新製品デザインについて意匠登録を取得すれば、競合他社がそのデザインを模倣した製品をミャンマー国内で販売することを法的に禁止でき、必要に応じてライセンス契約を結んでロイヤリティ収入を得るといった活用も考えられます。まだ制度開始から日が浅いため著名な登録事例は限られますが、ファッション、伝統工芸、日用品、電子機器など様々な分野で意匠登録によるデザイン保護の実績が今後蓄積していくものと期待されています。
6. 最新の法改正や施行状況
ミャンマーの新しい工業意匠法(Industrial Design Law, Pyidaungsu Hluttaw Law No. 2)は2019年1月30日に制定されました。しかし直後に施行されたわけではなく、必要な制度準備のため施行は数年延期されました。2023年9月29日付けで本法の施行細則となる工業意匠規則(Industrial Design Rules)が商務省から発出され、同年10月18日に国家行政評議会(SAC)より本法を2023年10月31日から施行する旨の布告(通達第217/2023号)が出されています。これに伴い、10月27日付の商務省通達第71/2023にて意匠出願や各種手続きを行うための公式書式(フォーム類)が定められ、さらに知的財産庁(Intellectual Property Agency)より12月29日付の通達第2/2023にて手数料額が公表されました。こうした実務準備を経て2023年10月31日に意匠法が正式に発効し、翌2024年2月1日からIPDによる意匠出願の受け付けが開始されています。本法の施行により、旧来の「1946年特許・意匠(緊急条項)法」は廃止されました。約70年ぶりに刷新された知的財産法制の一環として、意匠分野にも近代的な保護制度が整った形です。
国際的な連携状況について見ると、ミャンマーは2025年時点でハーグ協定(意匠の国際登録制度)やパリ条約などに未加盟ではあるものの、本法はパリ条約に準じた優先権制度(6か月以内の優先出願の主張)や公表猶予制度、ロカルノ協定に基づく意匠分類の採用など、国際標準に沿った内容となっています。実際、ミャンマーは世界貿易機関(WTO)加盟国としてTRIPS協定上の義務を負っており、本意匠法もTRIPSやパリ条約の趣旨に沿って整備されています。今後、ミャンマーがハーグ協定への加盟やパリ条約への正式加入を果たせば、海外からの国際意匠出願の受け入れや自国デザインの海外保護も一層促進される見込みです。新制度は施行されたばかりであり、引き続き運用状況の改善や知的財産庁の体制整備が進められている段階ですが、ミャンマー国内外の事業者にとって同国でのデザイン保護が現実的な選択肢となった意義は大きいと言えます。
参考文献・情報源: ミャンマー工業意匠法(2019年)および同施行規則、ミャンマー知的財産局公表資料、WIPO Lexデータベース、各種法律事務所による現地法解説。
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)