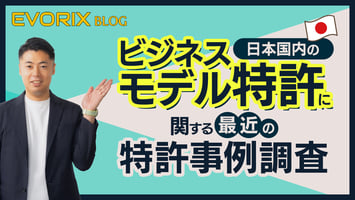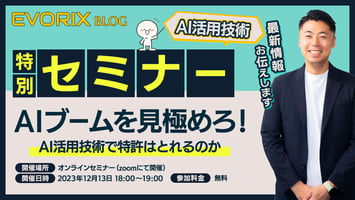...
アメリカの意匠制度概要
1. 登録要件(新規性・非自明性・意匠性など)
米国の登録要件: 米国の意匠特許は特許法の一部として規定されており、「製造物品のための新規で独創的かつ装飾的な意匠」であることが要求されます。したがって、意匠が新規性 (Novelty) を備え、かつ非自明性 (Non-obviousness) を満たすことに加え、装飾性 (ornamentality) があることが登録の条件です。新規性は平均的な観察者(ordinary observer)の視点で判断され、有効出願日以前に公知となった意匠と全体として同一の印象を与える意匠は新規性がないとみなされます。この際、比較対象となる物品の分野(用途や種類)が異なっていても、新規性の判断では考慮されません。非自明性は日本の「創作非容易性」に相当し、先行意匠から見て当該分野の通常のデザイナーにとって容易に想到できない意匠であることが求められます。さらに米国では意匠が純粋に機能に由来する形状ではなく、審美的な装飾性を有すること(機能により決定される形状は保護対象外)が重要で、これが意匠性(装飾性)の要件とされています。例えば、製品の形状がその機能上不可欠で装飾的要素が皆無な場合には、意匠特許の対象になりません。また米国法では、意匠特許の出願前自己開示に対するグレースピリオド(猶予期間)も設けられており、創作者自身による公表から1年以内であれば手続不要で新規性喪失の例外が認められます(米国は1年間の猶予期間)。これは出願時点を基準に適用されるため、日本で出願する直前1年以内の公開であっても米国では許容されます。
日本の登録要件: 日本の意匠法においても新規性および創作非容易性(米国の非自明性に相当)が登録要件です。意匠法第3条により、出願前に公然知られた意匠と同一または類似の意匠は登録できず、また容易に創作できる意匠も拒絶されます。日本では意匠の定義として「物品(部分を含む)の形状・模様・色彩(または結合)であって視覚を通じて美感を起こさせるもの」と規定され、美感(審美性)を生じない純粋に機能だけの形状は保護対象になりません。新規性の判断は日本では一般需要者(需要者=消費者)の視点とも言われますが、実務上は米国と同様に従来意匠との全体的形状の比較で行われます。ただし日本では比較対象とする物品の用途・機能が同一または類似であることが前提となり、仮に形状が同じでも用途・機能が全く異なる物品同士であれば意匠は異なるものと扱われます。例えば、同じデザインのメダルとチョコレートでは物品が異なるため意匠は非類似と判断されます。このように、日本では意匠は物品と不可分とされるため、分野の異なる物品に施された類似形状は直接には競合しないのに対し、米国では物品分野を問わず新規性・非自明性を審査する点に違いがあります。なお、日本にも自己開示に基づく新規性喪失の例外制度(グレースピリオド)があり、近年の法改正で出願前1年以内の自己公表について例外適用が可能になりました(従来6ヶ月)。ただし日本では出願時などに所定の手続(例外適用の申請と証明書類提出等)を要する点で、手続不要で自動適用される米国と異なります。また、米国はフォントやアイコン、画面表示も「製造物品の意匠」として保護可能で意匠の範囲が比較的広いのに対し、日本も2020年の法改正で画像デザイン(画面表示やアイコン自体)の保護が可能となりましたが、歴史的には物品性に重きを置いてきた経緯があります。総じて、米国・日本とも登録要件自体は新規性・非自明性など大枠で共通しますが、物品の捉え方や猶予期間の運用、装飾性要件の明示などに制度上の特徴があります。
2. 出願手続(出願書類・審査・手数料など)
米国の出願手続: 米国で意匠特許を出願する際は、基本的に特許出願に準じた書式で行います。具体的には、願書 (Application) に当たる書面に出願人情報や発明者(創作者)情報を記載し、図面 (Drawings) を添付するとともに、明細書に相当する部分として簡潔な意匠の説明書とクレームを含めます。米国意匠特許ではクレームは通常一つだけで、「The ornamental design for <製品名称>, as shown and described.(<製品>のための装飾的デザインであって、図示し記載した通りのもの)」という定型的な文言で記載します。図面が意匠の詳細を示すため、文章での詳細な説明は多くの場合必要最低限です。また発明者による宣誓書 (Oath/Declaration) の提出が法律上必要で、出願時または出願後に発明者が自分が意匠の創作者であることを宣誓した書面をUSPTOに提出します。さらに情報開示陳述書 (IDS) として、申請人が知り得る関連する先行意匠文献を開示する義務があります。日本とは異なり、米国出願人には先行意匠の開示義務が課されており、これを怠ると不誠実な手続(inequitable conduct)と見なされ、登録後であっても権利行使が制限される可能性があります。
米国は一意匠一出願が原則ですが、実務上複数の実施例 (Embodiments) を1件の出願に含めることが認められる場合があります。これは複数の意匠が単一の創作概念に属すると判断される場合で、例えば形状違いのバリエーションや、全体意匠とその部分意匠を一緒に含めるケースです。出願審査官が単一性要件を満たさないと判断した場合、限定要求(Restriction Requirement)が出され、出願を分割するか請求範囲(実施例)を絞り込む必要があります。一方、類似する意匠を別々に出願すると後願に対し先願を引用して非自明性欠如の拒絶理由が出る場合があり、これに対処するためターミナルディスクレーマ(後願の存続期間を先願と同日に終了させる手続)を行うケースもあります。このように、米国では一件の出願で複数の意匠をカバーする戦略も存在しますが、審査官の判断によっては分割が必要となるため注意が必要です。
審査は、米国では意匠も実体審査主義です。出願後、USPTOで意匠専門の審査官が先行意匠を調査し、新規性・非自明性・意匠性などを審査します。審査期間は平均して8~12ヶ月程度で第一次審査結果(オフィスアクション)が通知されます。拒絶理由があれば、意見書や補正によって対応し、審査官とのやり取りを経て登録可となれば特許料の支払いを経て意匠特許が発行されます。米国意匠特許出願には出願料・審査料・発行料などの手数料が必要で、例えば大企業(通常規模の出願人)の場合、出願時に合計約$1,000~$1,500程度(基本出願料$250+検索料$160+審査料$160等)を納付し、登録時(特許発行時)に発行料としてさらに約$1,000前後(※2025年には$1,300に値上げ予定)を納付します。中小企業や個人(Small/Micro Entity)はその半額または1/4に減額される制度があります。維持年金については、米国の意匠特許には存続期間中の年金(維持費)支払い義務がありません(出願・発行時の費用のみ)という特徴があります。
日本の出願手続: 日本では意匠登録出願として独立の意匠法手続が定められています。願書には意匠の名称(物品名)、創作者・出願人情報などを記載し、図面又は写真を提出します(近年の改正で写真やCG図面による出願も可能になりました)。日本の意匠出願ではクレームの記載は不要で、提出した図面そのものが権利範囲を画定します。必要に応じて「意匠に係る物品の説明」や「意匠の詳細な説明」を記載できますが、権利範囲解釈に直接影響しない補助的なものです。部分意匠を出願する場合は、当該部分を特定するため図面中でそれ以外の部分を破線等で描く方法が採られます(詳細は後述)。日本では一出願一意匠が原則であり、米国のように複数意匠を一つの出願に含めることは基本的にできません。デザインのバリエーションを複数保護したい場合は、それぞれ個別に出願する必要があります。ただし、制度上関連意匠制度というものがあり、本意匠に類似するデザインについて出願日を揃えた関連意匠として紐付けて権利化することが可能です。この場合も出願は別々に行いますが、関連意匠には本意匠の出願日まで遡った存続期間制限などの連係ルールがあります(2020年改正で関連意匠出願可能期間の拡大等が行われています)。日本では部分意匠も独立の出願区分として、製品の一部分のみを意匠として出願できます。米国のように後から部分意匠に補正変更することは認められず、出願時に部分意匠として図面を提出する必要があります。
審査と期間: 日本も実体審査を行う審査登録主義で、特許庁の意匠審査官が先行意匠調査および新規性・創作容易性などをチェックします。近年、日本意匠出願の一次審査通知までの期間は平均6~7ヶ月程度とされ、スムーズなら出願から約8~12ヶ月で登録査定に至るケースが多いです(案件によって変動します)。登録査定となった場合、設定登録料を納付して初めて意匠権が発生します。設定登録料は登録時に第1~3年分をまとめて支払う方式で、例えば意匠の場合登録料は年額8,500円×3年分=25,500円(※2022年時点)を一括納付します。4年目以降は毎年年金を納めて権利を維持する必要があり、第4年以降25年まで各年16,900円と定められています。日本の意匠出願の出願料は16,000円と比較的低額で、審査請求は不要(出願と同時に審査される)ため、出願時費用は抑えられています。なお、日本には秘密意匠制度があり、登録から最長3年間、公報に掲載される意匠を非公開にできる制度があります。これにより新製品発表のタイミングに合わせてデザイン公開を遅らせることが可能です。一方、米国では出願中の意匠は原則非公開(意匠出願は公開制度がなく、特許として発行されて初めて公表)なので、出願から登録まで自動的に秘密状態が保たれる点で事情が異なります。総じて、出願手続面では、米国は特許的な手続(クレームや宣誓書・IDS提出等)が必要で費用も割高ですが維持費負担はないのに対し、日本は手続簡素で費用も低廉な反面、毎年の維持費が発生するといった違いがあります。
3. 保護期間
米国: 米国意匠特許の存続期間は、意匠特許発行日(登録日)から15年です。以前は14年でしたが、2015年の法改正(ハーグ協定加入に伴う改正)により現在は15年に延長されています。この期間中は年次維持料が不要で、出願から権利満了まで追加費用なく保護が継続します。また米国では意匠出願が特許として権利化されない限り公表されないため、出願から15年のカウントダウンが始まるのは発行時点となります。
日本: 日本の意匠権の存続期間は近年延長され、出願日から25年となりました(2020年4月1日施行の改正法。それ以前の出願は「登録日から20年」でした)。改正により世界的に見ても長めの保護期間となっています。存続期間の計算起点が出願日であるため、審査・登録に要した期間も含めて最大25年間保護されることになります。例えば出願から1年後に登録された場合、登録から実質24年程度が保護期間となり、早期登録しても恩恵を損ねない形です(旧制度では審査に時間がかかると実質保護期間が短縮されていました)。日本では毎年の年金納付が必要である点にも留意が必要です(25年目まで毎年納付)。なお、日本の意匠権は存続期間満了前でも意匠権者が放棄すれば権利終了できますし、年金未納でも権利が消滅します。米国意匠特許は期間が短い代わりに維持の手間がかからないのに対し、日本意匠権は期間が長い反面、維持管理が必要という違いがあります。
4. 侵害訴訟(立証の要件、損害賠償、判例など)
米国の侵害判断: 米国意匠特許の侵害可否は**「普通の観察者 (ordinary observer)」テストによって判断されます。具体的には、対象製品を購入するような普通の購買者が、被疑製品のデザインを見たときに、それが意匠特許製品と同じものだと誤認するおそれがあるかどうかという基準です。この全体観察による類似性の判断は、米国連邦最高裁判決 Gorham Co. v. White (1871) 以来の伝統的テストで、2008年の Egyptian Goddess 事件で改めて確立されました。Egyptian Goddess 判決では従来考慮されていた「ポイント・オブ・ノベルティ」テストを不要とし、先行意匠の存在を考慮に入れつつ(既存のデザインから受ける印象との差異も考慮した上で)、全体として見て実質的に同一かを判断する方法が示されています。米国では意匠特許のクレームは図面に示された形状そのものであり、図面の実線部分が権利範囲を構成します。破線で描かれた部分は権利として主張しない(除外された)部分であり、侵害判断でも考慮されません。被疑物が特許意匠と厳密に同一でなくとも、外観上ほぼ同じであれば侵害となりますが、逆に細部の相違よりもデザイン全体から受ける視覚的印象が重視されます。なお米国法には特許クレーム同様に均等論の適用は原則なく、意匠では目視できるデザインそのものが全てです。また侵害判断において、被疑品が特許でクレームされた「物品」と異なる用途の製品であっても、法律上は意匠の実質同一性があれば侵害とされ得ます(例えば特許クレームが「椅子のデザイン」であっても、そのデザインを模した玩具を販売すれば侵害と判断される可能性があります)。もっとも、物品が全く異なれば消費者の誤認も生じにくいため、実務上は同種または類似の製品分野内で問題となる**ことが多いです。
日本の侵害判断: 日本における意匠権侵害の成否は、登録意匠(およびその類似意匠)と被疑意匠が「同一または類似」であるかによって判断されます(意匠法第23条)。この「類似」の判断は二段階で行われ、まず物品の用途及び機能について被疑品と登録意匠の物品が同一または類似であることが前提となります。物品が全く異なる場合には、どれほど形状が似ていても意匠は類似しないと扱われます。次に、物品が一致・類似すると認められた場合に、意匠の形態(デザインそのもの)の共通性を比較します。具体的には、両意匠の構成要素や形状の特徴点を対比し、全体として美感に与える印象が共通か否かが判断されます。日本の裁判例では、意匠の要部(デザイン上、特に顧客の注意を引く特色部分)の類否が重視される傾向があります。共通点が顕著で相違点が細部にとどまる場合は類似と判定されやすく、逆にデザインの要部に明確な差異があれば非類似とされます。例えば、登録意匠と被疑意匠で主要なデザインコンセプトが異なる場合や、細部は似ていても全体のシルエットやプロポーションが異なり印象が違えば非類似となります。以上より、日本では**「物品の同一/類似」かつ「形態の同一/類似」の両方を満たすとき意匠権侵害が成立します。米国に比べると、日本の「類似」の範囲は若干広めで、デザイン全体の細かな差異よりも共通する美感に重きが置かれると言われます。一方、物品が異なると侵害にならない点は日本独特の要件**です。
損害賠償と救済: 米国では意匠特許侵害に対し、他の特許と同様に差止命令(侵害行為の禁止命令)や損害賠償金の請求が可能です。損害賠償について特筆すべきは、米国特許法第289条に規定された**「意匠特許侵害に対する追加的救済」です。同条は「侵害者は、その侵害に係る物品の販売によって得た総利益 (Total Profit) を権利者に支払わなければならない」と定めており、侵害製品1個あたりの利益×販売数量=総利益額がそのまま損害額として認められる可能性があります。これは意匠特許特有の強力な救済措置で、侵害品による利益全額の没収(エンタイヤメント・ルール)とも呼ばれます。例えば有名なApple社 vs. Samsung社のスマートフォン訴訟では、Samsung社製スマホがApple社の意匠特許(iPhoneの筐体デザイン等)を侵害すると認定され、陪審評決で約10億5千万ドルもの巨額賠償(Samsungの該当製品の全利益に相当)が算出されました。その後裁判所や最高裁の判断で、「総利益」の適用対象となる「物品」の範囲が争点となり、スマホ全体ではなく部品単位で利益を算定すべき場合もあるとして差戻しが行われています。最終的にSamsung社がApple社に支払った意匠侵害賠償額は約5億ドルに減額され和解しました。米国最高裁は2016年に、この第289条の「記事(Article of manufacture)」は必ずしも完成品全体を指すわけではなく、場合によっては製品の一部に対応するとも解釈できると判示し、今後は侵害デザインが製品の一部分の場合、部分に対応する利益のみを賠償額とする可能性を示しました。それでもなお米国では意匠侵害に対し売上利益の全額賠償を得られる余地**があるため、意匠権者にとって非常に大きな抑止力・交渉力となります。加えて米国では故意侵害の場合の懲罰的賠倍(最高3倍賠償)も他の特許と同様に適用可能です。また税関に意匠登録を届け出ておけば、輸入段階で模倣品を差し止める制度も活用できます。
日本では、意匠権侵害に対する民事救済は差止請求権および損害賠償請求権で、これは特許権侵害の場合とほぼ同じスキームです。損害賠償額の算定も特許法と同様に、①権利者の逸失利益、②侵害者の利益(ただし権利者の生産能力を超える部分は除く)、③実施料相当額(ライセンスフィー)のいずれかを選択的に立証でき、重複しない限り併用も可能です(民法および特許法105条の3等の準用規定)。侵害者の総利益の全額がそのまま賠償されるわけではなく、意匠が製品の一部に関わる場合はその寄与度が考慮されます。結果として、日本の意匠訴訟で認められる損害賠償額は、米国のような巨額になるケースは稀で、数百万~数千万円規模が一般的です(もちろん市場規模によります)。著名な日本の意匠侵害訴訟例としては、例えば工業製品のデザイン模倣に対して差止・廃棄命令と数千万円の賠償が命じられたケースなどがあります。また日本では刑事罰もあり、悪質な意匠権侵害には10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)が科される可能性があります(意匠法69条)。
判例動向: 米国では前述のApple vs. Samsung事件が意匠権の重要性を一躍高め、以降ハイテク分野でも積極的に意匠特許が活用されています。また最近ではLKQ Corp. v. GM事件において、意匠特許の非自明性判断基準が議論されました。2024年に連邦巡回控訴裁判所(CAFC)大法廷は、長年用いられてきたRosen-Durlingテスト(意匠特有の非自明性判断枠組み)は、最高裁KSR判決の趣旨に反する限り無効となり得るとし、今後は実用特許と同様の柔軟な非自明性判断を適用すべきと判示しました。この変更により、米国意匠特許の有効性が争われる場面で、従来より無効となる可能性が高まるとの指摘もあります。一方、日本では意匠侵害に関する近年の著名判例は多くありませんが、平成年代の「バッグ意匠事件」等で意匠の要部認定や類否判断手法が示されています。2020年改正で関連意匠による権利延長戦略が可能となったこともあり、侵害訴訟での本意匠・関連意匠の使い分けなど、新たな論点も考えられます。全体として、米国は陪審制の下で巨額賠償が生じ得る法制度であり、日本は専門部(知財高裁)を有する安定した審理が特徴ですが、賠償額や抑止力の面で大きな制度差が存在します。
5. 国際出願との関係(ハーグ協定への対応、国際出願の実務)
ハーグ協定加盟: 米国も日本もともに2015年に意匠の国際登録制度であるハーグ協定に加盟しました。したがって現在、企業はハーグ国際出願を利用して一度の出願で複数の国(締約国)の意匠保護を出願できます。米国(USPTO)や日本(JPO)を指定国に含めて国際出願すると、ジュネーブのWIPO国際事務局で方式審査の後、各指定国官庁に送付されます。米国は審査官による実体審査国なので、国際出願であってもUSPTOは受理後、自国出願と同様に新規性・非自明性などの審査を行い、拒絶理由があれば拒絶通報(refusal)を発します。米国指定の場合、原則として国際公開日から12か月以内に拒絶の有無を通知することになっており、拒絶通報がなければその意匠は米国で登録(意匠特許付与)されます。日本も同様に実体審査を行うため、指定後12か月以内に拒絶の有無を判断します。ハーグ出願では、各国官庁から拒絶理由通知を受けた場合に現地代理人を通じて応答しなければその国では保護が得られない点は、通常のパリ条約経由の外国出願と同じです。
国際出願のメリット・留意点: ハーグ協定を利用すると一願で多国の意匠権を管理できるメリットがあります。出願手数料も一括で済み、各国ごとに重複する書類提出を減らせます。特に欧州連合知的財産庁(EUIPO)での登録意匠や韓国・中国など複数国を含めた一括出願の際に有用です。米国・日本両国も加入したことで、日本企業が米国意匠出願をハーグ制度で行うことも増えています。しかしながら注意点もあります。図面(意匠の表現)の統一がその一つです。各国で要求される図面の表現形式・水準が異なるため、一つの図面セットで全指定国の基準を満たす必要があります。例えば日本では線画のみでも受理されるケースであっても、米国では陰影や完全な六面図が要求されることがあります。日本出願時に作成した図面だと米国基準を満たさずそのままでは米国で拒絶されることもあるため、国際出願前に図面の修正を検討する必要があります。米国特有の破線の用法(後述)や陰影の付し方も考慮しなければなりません。ハーグ出願では基本的に出願後の図面補正に厳格な制限があり、優先権主張を伴う場合は出願時に各国要件を満たす図面を提出するのが望ましいです。そのため、日本企業がまず国内で意匠出願し、その図面を用いて米国(や他国)を指定したハーグ出願を行う場合、日本出願時から国際的に通用する図面作成をしておくことが推奨されます。特に米国を指定予定であれば、日本出願の段階で米国式の図面(十分な視図と陰影表現)にしておくことで、後の補正不能問題を避けられます。
また一出願に複数意匠を含めるハーグ出願についても留意が必要です。ハーグ制度自体は1件の国際出願で最大100意匠まで包含できますが、米国や日本のように国内法で一意匠一出願が原則の国では、単一性違反として拒絶される可能性があります。米国・日本を指定国に含む場合、実務的には各意匠ごとに別々に国際出願する方が無難です。一つの国際出願に複数意匠を入れると、USPTOやJPOから「どれか一つしか認められない」旨の拒絶通報が来て、結果的に一部意匠について権利が得られない事態になり得ます(※ハーグ出願にはPCTのような分割移行手続が無く、追加料金で自動的に複数権利化はされません)。従って、米・日を含むハーグ出願では一出願一意匠を原則とするのが実務上の対応策です。
その他の実務: 米国はハーグ協定加盟時に意匠法制を一部変更しており、前述の通り存続期間を15年に延長したほか、国際登録出願にも対応しました。米国を指定したハーグ出願では、国際出願の出願人が米国法上の意匠発明者とみなされ、後日USPTOに宣誓書 (oath) を提出する必要があります(この点は通常の米国出願と同様ですが、国際出願経由では提出方法に若干の追加手続があります)。日本企業にとって、ハーグ制度は欧米をまとめて出願する際に便利ですが、米国出願特有の手続(IDS提出義務や宣誓書など)には引き続き注意が必要です。もっとも、国際出願経由であっても米国で実体審査に通りさえすれば直接出願した場合と同じ意匠特許が与えられますし、日本でも同様です。なおパリ条約に基づく優先権主張による直接出願も引き続き一般的な手段で、例えば日本に出願後6ヶ月以内に米国へパリルート出願するケースも多くあります。ハーグを使うか直接出願するかは、指定国数や費用、手続負担を考慮して選択することになります。総じて、米国と日本が共にハーグ加盟国となったことで、デザインの国際戦略は柔軟性が増した一方、各国の審査基準差異を十分理解した上で図面作成・出願計画を立てる必要があると言えます。
6. 図面要件(図面の品質基準、記載方式、破線の取り扱いなど)
米国の図面要件: 図面は意匠特許出願の中核であり、USPTOは高品質で詳細な図面を要求します。基本的に六面図(正投影図)として、製品の前面・背面・左右側面・上面(平面)・下面の図をすべて提出する必要があります。立体物であればこれらに加えて斜視図(透視図)を提出することが推奨されます。要するに、あらゆる角度から見て形状を完全に開示することが求められます。各図は互いに矛盾なく、全ての図で一貫した形状を描かなければなりません。少しでも各図間で形状が合致しない部分があると審査で不備と指摘されます(例えば一方の図に描かれた線が他の図で欠けている等は不可)。図は通常線画(黒色線の描画)で描き、陰影(シェーディング)を施して立体感や表面の凹凸・曲面を表現することが強く推奨されます。特に部分意匠(一部のみをクレームする場合)では、その部分に陰影を付すことで権利範囲を明確に示すよう要求される場合があります。逆に、断面図については外観上の凹凸が陰影で分かる場合には提出しない方が良いとされています。断面図も権利解釈上有効な図面と見なされ、余計な断面を示すと権利範囲を不必要に限定しかねないためです。米国図面には破線 (Broken lines) の活用も重要です。破線で描いた部分は**「環境もしくは非請求部分」と解釈され、意匠クレームの範囲に含まれないことを示します。例えば、ある部品の部分意匠をクレームする場合、製品全体を描いてその該当部のみ実線、それ以外を破線にすることで「実線部の形状のみを権利請求する」ことを表現します。また、純粋に環境を示すだけの構造(製品の使用状態を示す手や人など)は全て破線で描きます。実線と破線の使い分けによって、意匠の保護対象を明確に限定するのが米国図面の特徴です。米国では写真やCGによる図も例外的に認められていますが、その場合は事前に請願書(Petition)を提出して許可を得る必要があります。線画で表現できない質感やグラデーション等、特別な事情がある場合に限られ、原則は線画です。写真提出が許可された場合でもカラー写真は権利範囲がその色に限定されるなどデメリットがあり、線画を用いる方が望ましいとされています。また線画と写真を混在させたり、線画とCGを組み合わせることも認められません。図面の様式としては、各図にはFig.1, Fig.2,...**等の番号とビューの名称(正面図、側面図等)の説明を明細書中に記載します。米国意匠特許公報には、図面の簡単な説明文(例:「図1は本意匠の正面図である」等)は掲載されますが、詳細な文章による意匠の説明はほとんど載りません。要するに、米国では図面そのものが全てであり、明確で統一性のある図面を提出することが極めて重視されます。
日本の図面要件: 日本でも意匠出願には原則として六面図(6方向図)の提出が求められます。正面・背面・左右側面・上面・下面の図に加え、立体物であれば斜視図(立体図)を付けるのが一般的です。もっとも日本特許庁の運用では、対称形状で片側が他方と同一の場合に一部の図を省略する、など柔軟な取扱いもあります。例えば左右対称の物品なら片側面図を省略したり、上下同一なら下面図を省略することも可能です(その場合、願書に「左右同一につき右側面図を省略」等と記載)。日本では図面の陰影 (シェーディング) は必須ではなく、線画のみで形状が明確に理解できれば問題ありません。実際、日本の公開公報に掲載される意匠図面の多くは陰影のない線図です。細かな曲面形状については、日本審査では図面の筆致から判断することも多く、米国ほど陰影表現を要求される場面はありません。ただしガラスや透明体などの場合には破線や点線で透明部分の背後を描く等、必要に応じた表現を行います。破線の取扱いについて、日本でも部分意匠制度があるため、出願時に権利を求めない部分を破線で描くことがあります。例えば製品全体の中の特定部位のみを登録したい場合、その非請求部分(環境部分)を破線で記載することで部分意匠として認められます。米国との違いは、日本では一旦提出した図面の実線部分を後から破線に変更する補正は原則認められないことです。米国では審査過程で不明瞭な部分を破線化して部分意匠に移行する補正が許容される場合がありますが、日本ではそれを行うと新規事項追加・要旨変更とみなされる可能性が高く、出願時に図面を確定させる必要があります。従って、日本出願では部分意匠か全体意匠かを最初に決め、図面で明示しなければなりません。記載方式としては、図面に Fig番号は振らず、「【図面の簡単な説明】」欄に「(1)は本意匠の斜視図、(2)は正面図…」のように記載します。日本出願では写真画像による意匠登録も2016年頃から可能となり、布地の模様など複雑な意匠では写真提出例も増えています。ただしカラー写真で登録するとその特定色彩に限定される点は米国同様です。近年、日本では3Dモデルデータによる意匠出願も2020年改正で導入準備が進められています(試行段階)。また日本にも参考図の制度があり、製品の使用状態や変形前後を示す参考図を提出できます。参考図は権利範囲に含まれませんが、デザインの理解補助として審査官に考慮される場合があります。提出は任意ですが、不用意な参考図は解釈を狭めかねないため慎重さが求められます。
両国図面基準の差異: 日本で認められる図面がそのまま米国で通用しないケースがあり、その逆もまた然りです。例えば日本出願では省略していた裏面図等が、米国では省略不可で追完を求められることがあります。また日本では平面的に描写して問題ない細部も、米国審査官からは「不明瞭」とされ陰影付加や拡大図提出を求められることもあります。前述のようにハーグ国際出願で両国を同時指定する場合は、これら図面基準の差を埋める図面を用意する必要があります。日本企業が日本ローカル基準の図面で米国出願した場合、補正で対応できないと優先権を放棄してでも図面を描き直す羽目になることもあります。したがって、国際的に権利化を予定する意匠については、最初から米国基準を念頭に図面作成することが推奨されます。具体的には、きちんと6方向図を揃え陰影も付した線画を準備し、日本出願時にもそれを使うことで、後日の米国展開が容易になります。このように、米国は図面品質への要求が非常に厳格で、日本は比較的簡素な図面でも受け付けられるという違いがあります。権利範囲の厳密さという観点では、米国は図面記載に現れない形状は一切権利範囲に含まれないため、見えない部分であっても明示的に「破線」で示すなどの工夫が必要です。一方日本は見えない部分については暗黙的に平坦とみなす等の審査基準がありますが、近年は不明瞭部分には拒絶理由を出す方向で厳格化しています。総じて、図面は意匠権の命であり、米国と日本の双方で問題なく通用する図面作成には専門的なノウハウが不可欠です。
米国・日本の意匠制度の比較表
上記の内容を踏まえ、米国意匠特許制度と日本意匠制度の主要な相違点をまとめると以下の通りです。
| 観点 | 米国(意匠特許) | 日本(意匠登録) |
|---|---|---|
| 登録要件 (新規性・非自明性・意匠性) | ・新規性:世界基準。平均的観察者が同一の印象を受ける先行意匠があれば拒絶(物品分野は不問)。・非自明性:通常のデザイナーにとって自明でないこと(近年KSR基準適用の判例変更)。・意匠性(装飾性):形状が機能にのみ起因せず、美的特徴を有すること。・その他:意匠は「製造物品」に属するもの(フォントやGUIも物品とみなして保護)。自己公表から1年のグレースピリオドあり(手続不要)。 | ・新規性:世界基準。公知意匠と同一・類似なら拒絶(物品・形状とも比較)。・創作非容易性:当業者が容易に想到できないこと(米国の非自明性相当)。・美感要件:視覚を通じ美感を起こす形態(純粋に機能だけの形状は除外)。・その他:意匠は物品と不可分。用途・機能が異なる物品には適用されない。自己公表から1年の例外期間(要手続)あり(2020年改正で6ヶ月→1年)。 |
| 出願手続 (書類・審査・費用) | ・願書書類:クレーム(一項)必須。図面は精密な線画+陰影推奨。発明者による宣誓書提出要。IDSで先行意匠情報開示義務。・一出願複数意匠:原則1意匠。ただし単一概念内の複数実施例を許容(審査で制限要求の可能性)。部分意匠への後補正可。・審査:実体審査(新規性・非自明性)。一次通知まで約8~12ヶ月。拒絶時は意見書・補正で応答。・費用:出願時:約$1,000〜$1,500(大企業)、発行時:約$1,000前後。小規模は減額あり。年維持料不要。 | ・願書書類:クレーム不要(図面が権利範囲)。物品名、図面または写真を提出。必要に応じ部分意匠は破線表示。宣誓書・IDS提出義務なし。・一出願一意匠:原則1意匠/出願。類似デザインは別途関連意匠制度で保護可(別出願が必要)。出願後に部分意匠へ変更補正は不可。・審査:実体審査制。一次結果まで平均6〜10ヶ月程度。拒絶時は意見書・補正で応答。審査請求は不要(出願自動審査)。・費用:出願料16,000円。登録料25,500円(1〜3年分一括)。4年目以降年金16,900円/年。年維持料必要(最大25年分)。 |
| 保護期間 | ・登録日から15年(2015年以降の現行法)。・中間年金不要(15年間維持費なし)。・出願〜登録まで非公開(意匠出願は公開制度なし)。 | ・出願日から25年(2020年改正法。それ以前は登録日から20年)。・毎年年金を納付して最長25年維持。・出願公告なし(登録時に初めて公開)。希望により**最大3年の非公開(秘密意匠)**可。 |
| 侵害要件 (立証・範囲) | ・侵害判断基準:普通の観察者テスト – 一般消費者が見て誤認するほど実質同一なら侵害。全体的外観の比較に重きを置く(細部の相違より全体の印象)。物品の種類問わず比較(用途異なっても外観同じなら侵害の可能性)。・権利範囲:図面中実線部分のみ保護。破線部や記載のない側面は範囲外。均等論主張は基本なし。・立証:被疑物の写真/実物と特許公報図面を対比。意匠の要部(特徴点)の共通性を原告が主張立証。意匠特許証拠に有効性の反証も被告は可能。 | ・侵害判断基準:同一・類似概念 – 登録意匠と物品が同一/類似かつ形状が同一/類似であれば侵害。まず用途・機能面で同種の商品かを見る(異業種なら侵害成立せず)。物品が一致すれば形状の全体印象を比較し、需要者の注意を引く要部に差異が無ければ類似と判断。・権利範囲:登録意匠およびそれに類似する意匠まで及ぶ(意匠法23条)。関連意匠も別個に権利行使可。部分意匠の場合はその部分に限る。・立証:原告が登録意匠図面と被疑製品のデザインを対比し類似点を主張。被告は形態の相違点や、公知意匠との類否を抗弁可能。 |
| 損害賠償 (救済・額) | ・差止請求:可能(侵害製品の製造販売の禁止命令)。・損害賠償:35 USC 289条により侵害品の総利益の没収。製品全体か部品かは事案による。加えて故意侵害なら懲罰的賠償(3倍賠償)適用可。・判例:Apple vs Samsungで総利益賠償が争点となり約5億ドルの賠償例。高額賠償が注目され意匠出願件数も増加。税関差止めによる輸入阻止も有効。 | ・差止請求:可能(仮処分による差止も可)。・損害賠償:特許法と同様の算定(逸失利益、侵害者利益、実施料相当額等)。総利益全額とはならず、意匠の寄与率考慮。・典型額:数百万~数千万円程度が多い(市場規模次第)。懲罰的賠償制度はなし。・判例:意匠の要部認定や類否判断に関する事例多数(バッグ意匠事件等)。模倣品に対し約数千万円の賠償と差止が命じられた例あり。刑事罰も適用可能(10年以下懲役等)。 |
| 国際出願 (ハーグ協定) | ・加盟状況:2015年加盟。国際出願で米国指定可。・審査対応:国際出願でもUSPTOで実体審査し、拒絶通報なければ自動登録(出願から12ヶ月以内審査)。・図面留意:国際図面が米国基準を満たさない場合拒絶。特に陰影・視図不足に注意。・手続:国際出願で米国指定の場合も発明者宣誓書等を別途提出要。複数意匠を一出願に含めると単一性拒絶の恐れ。・直接出願:パリルートでの直接US出願も可(優先期限6ヶ月)。 | ・加盟状況:2015年加盟。国際出願で日本指定可。・審査対応:JPOが実体審査。12ヶ月以内に拒絶通報なければ登録。・図面留意:国際図面が日本基準を満たさない場合拒絶。日本は陰影不要だが米国併願時は付しても問題なし。・手続:国際出願の指定国手数料納付で権利発生。複数意匠含む場合、日本も単一性違反で一部拒絶の可能性あり。・直接出願:優先権主張のパリルート出願も一般的(国内出願後6ヶ月以内)。 |
| 図面要件 (品質基準・破線等) | ・図面品質:精細な線画+陰影必須級。六面図+斜視図で完全開示。図間の一貫性厳格チェック。・破線表示:非請求部分・環境を破線で描画(権利範囲外)。出願後に破線化する補正も場合により許容。・写真図面:原則不可(例外的に許可制)。カラー図面はその色限定。線画と写真の混在不可。・その他:図面の簡単な説明を記載(Fig.番号付与)。参考図は審査・解釈対象となり得るので慎重に。 | ・図面品質:基本線画で可(陰影なくても許容)。六面図+必要に応じ斜視図提出。対称物は一部省略可。・破線表示:部分意匠では非請求部分を破線で描画。出願時に決定し、後から破線変更補正不可。環境を示すのみの部分も破線。・写真図面:カラー/白黒写真やCG図も受付可(近年解禁)。カラー登録時はその色限定(慣例上、可能なら白黒図面推奨)。・その他:図面の簡単な説明欄に(1)、(2)…で各図を説明。参考図提出も可(権利解釈には基本影響せず)。**(注)**日本図面は米国基準に満たない場合あり、国際出願時は米国基準に合わせる必要。 |
以上の比較から、米国の意匠特許制度と日本の意匠制度は基本的な枠組みは似通いながらも、審査基準の運用や権利行使のルールにおいて重要な違いが存在することが分かります。日本企業が米国で意匠権を取得・活用する際は、**米国特有の厳格な図面作成基準や侵害時のリスク(高額賠償)**を十分に踏まえた戦略が必要です。一方で、日本側も2020年の法改正で保護期間延長や画像デザインの保護拡大など国際調和を図っており、今後も両国制度の動向に注目する必要があります。各制度の相違点を正確に理解し、適切に権利取得・権利行使することが、国際市場におけるデザイン保護の鍵となるでしょう。
【参考資料】
-
特許庁 産構審資料「各国意匠制度比較」(2011) 出願料・手数料の比較
-
JETRO「米国における事業進出マニュアル - 意匠特許の出願」(2022) 日米の図面基準差異に関する指摘
-
JETRO「米国における事業進出マニュアル - 意匠特許の救済」(2022) 米国の意匠侵害時の総利益賠償規定とApple対Samsung事件の紹介
-
エムアンドパートナーズ「米国意匠特許の非自明性基準変更(LKQ v. GM)」(2025) 米国における意匠非自明性判断の最新判例情報
-
WIPOニュース「米国と日本のハーグ協定加盟」(2015) 両国の加盟に関するアナウンス
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)

.jpg?height=200&name=unnamed%20(4).jpg)