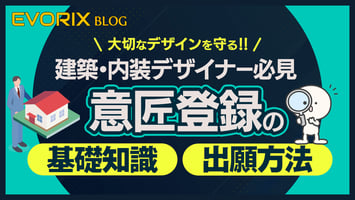1. 登録要件(定義・登録基準・拒絶理由等) 意匠の定義・保護対象:...
インドネシアの意匠制度概要
登録要件(新規性・創作性など)
インドネシアで意匠(産業デザイン)として登録を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
-
新規性(Novelty):出願時に世界中で公に知られていない意匠であることが必要です。具体的には、出願日(または優先日)以前に国内外で公表・使用されていないデザインでなければなりません。インドネシア法では6か月の新規性喪失の例外(グレースピリオド)が認められており、公的な国内外展示会への出品や、教育・研究目的の試験公開から6か月以内の出願であれば新規性を失わないとされています。
-
独自性・創作性(Originality):法律上明文の「創作非容易性(創作の困難性)」要件こそありませんが、既存の意匠と同一又は実質的に類似しない独自のデザインであることが求められます。既存デザインとごく僅かな差異しかないような場合には、新規性が否定され登録が拒絶される可能性があります。意匠はその形状・模様・色彩の創作により美的印象を与えるものでなければならず、純粋に機能を確保するための形状のみから成るものは保護対象外です(※この機能本質の形状の不登録要件は新法案で明文化が予定されています)。
-
産業上の利用可能性:そのデザインが工業製品や手工芸品などの商品に適用できることも要件です。インドネシア意匠法の定義上、意匠とは「製品、工業用品、手工芸品に利用できる形状・模様・色彩からなる創作」であり、美感を起こさせるものと定義されています。したがって純粋に芸術作品のような実用品でないものは意匠登録の対象にはなりません。
-
公序良俗等:法令や公序良俗、宗教的価値観に反する意匠は登録を受けられません。例えば社会倫理に反するデザインは法律上保護が排除されています。
以上がインドネシアにおける意匠登録の主な要件です。日本の場合と異なり創作が容易でないこと(創作非容易性)の明文要件はありませんが、実質的には「既存と類似でない独自性」が求められている点で日本の創作性要件と趣旨は類似しています。
出願手続(出願先・必要書類・言語・図面要件・審査方式・出願公開など)
出願先・言語:インドネシアにおける意匠の出願は法務人権省配下の**知的財産総局(DGIP)**に対して行います。出願書類はインドネシア語で作成し提出する必要があります。出願人が外国法人・個人の場合は現地の弁理士(知的財産コンサルタント)を代理人として選任し手続きを行う必要があります。出願書類一式は所定の用紙にインドネシア語で作成し、正本のほか所定部数の写しを提出します。
必要書類:出願時には(1)出願人・創作者の情報、(2)意匠の図面または写真と意匠の説明書(ディスクリプション)、(3)代理人を通じて出願する場合は委任状、(4)出願料の納付証明、(5)優先権主張がある場合はその証明書類(優先権書類のコピーと必要に応じ翻訳)等が必要となります。出願人が創作者と異なる場合には、創作者から出願人への意匠権譲渡証(署名証書)や創作権利の承継を証明する書面を提出する必要があります。代理人委任状や優先権書類など外国語書面はインドネシア語訳を添付することが求められます。
図面要件:意匠の内容を正確に開示するため、図面(または写真)には厳格な形式要件があります。図面はA4サイズの白紙(厚さ100~200g/m²)に描かれ、複製に耐えうる明瞭なものである必要があります。意匠を十分に開示するため、図面には各視点から見た意匠の形状を示す複数の図(例えば正面、背面、側面、平面、斜視図など)を含め、図ごとに通し番号とその図が示す視角・部位の説明を付す必要があります。出願時に提出する図面には保護を求めない部分を破線で示すことが認められており(保護を求める部分は実線で表示)、これにより部分意匠的なクレームも可能です。提出図面と実物試料が対応していること(図面が実物そのものを正確に表していること)が求められる点も重要です。意匠説明書(ディスクリプション)には、その意匠の特徴および製品の用途・分野などを明確に記載し、必要に応じて意匠の新規性・独自性に関する説明を含めます。
審査方式:インドネシアでは部分審査登録主義とも言える方式が採られています。まず形式審査(方式審査)のみが行われ、方式要件に適合した出願は出願後3か月以内に官報に公告(公開)されます。公告後3か月間は異議申立て(オポジション)期間となり、この期間中に第三者は当該出願意匠に対し新規性など実体的な異議を申し立てることができます。異議がなかった場合、実体審査を経ることなく登録査定が出され意匠権が付与されます。一方、異議申立てがあった場合には知的財産総局内で実体審査が行われ、異議理由(既存意匠との類否など)を考慮して登録すべきか拒絶すべきか判断されます。異議に基づく審査の結果、拒絶となった場合、出願人は通知日から30日以内に意見書を提出して再考を求めることができます(最終的に拒絶が確定した場合には後述のように司法救済も可能です)。このように異議申立てが無い限り実体審査を行わない点が日本などの審査主義とは大きく異なります。なお意匠出願の公告内容には、出願人・意匠のタイトルや図面が含まれます。公開された意匠出願は誰でも閲覧可能であり、知財総局はオンラインデータベースを通じて意匠情報を提供しています。
出願公開の有無:上記のとおりインドネシアでは出願から3ヶ月で出願内容が公開されます。一方、日本では意匠出願は原則非公開で、最終的に登録が成立した意匠のみが意匠公報に掲載され公開される仕組みです(ただし日本では意匠権登録後に最長3年間の非公開期間設定も可能)。インドネシアには登録後の非公開制度はなく、出願公告以降は意匠内容が公知となる点に留意が必要です。
保護期間(存続期間・更新の可否)
インドネシアにおける意匠権の存続期間は出願日から10年間と定められています。この10年は一度きりの固定期間であり、日本やEUのような更新制度はありません。したがって10年の保護期間満了後は意匠権は消滅し、そのデザインは公有(パブリックドメイン)となります。インドネシア法では年金(年次維持料)の制度もなく、登録時に設定登録料を支払えばその後10年間維持される形です。
※参考:インドネシアでは現在意匠法改正が検討されており、短期意匠について登録不要で初公開から3年間保護する制度や、通常意匠の保護期間を5年+5年更新×2回(最長15年)とする案も議論されています。ただし2025年時点ではまだ現行法(10年保護、更新なし)が適用されています。
一方、日本の意匠権の存続期間は出願日から25年間(改正意匠法施行後、従来の「登録日から20年」から延長)とされています。日本では毎年所定の年金を納付することで最長25年まで権利を維持できます。インドネシアの10年と比べ、日本の意匠権は保護期間が長く設定されている点が大きな相違点です。また日本には存続期間の延長や更新制度はありません(25年満了で消滅)が、分割納付として5年ごとの年金前納などの制度があります。両国とも一旦満了した意匠権を復活・延長させることはできません。
侵害訴訟(侵害要件・立証責任・救済措置・裁判管轄など)
侵害の判断基準:インドネシアにおいて意匠権侵害と認められるのは、登録された意匠と同一もしくは実質的に同じ外観の製品を、権利者の許可なく業として製造・販売・使用・輸入・輸出・頒布する行為です。意匠権者には登録意匠の実施を独占する権利があり、第三者による無断実施を差し止める権利が付与されています。したがって模倣品や酷似したデザインの商品を販売することは侵害行為に該当し得ます。意匠の類否判断について法律上明確な規定はありませんが、一般には「需要者の目から見て同一または紛らわしいほど似ているか」が基準となります。なお、登録意匠と単に細部が異なる程度の類似品であれば新規性要件上も登録が認められないはずであるため、実務上は登録意匠と明らかに特徴が異なる製品であれば侵害からは除かれることになります。
立証責任:基本的に意匠権侵害の立証責任は原告である意匠権者側にあります。権利者は被告製品が自らの登録意匠の範囲に属すること(同一または実質同一であること)を証明しなければなりません。インドネシアの訴訟制度には日本のようなDiscovery(証拠開示)制度はありませんが、差止命令や差押えの申し立てを行い、裁判所の権限で証拠収集(例えば在庫品の押収など)を図ることも可能です。被告側は非侵害(デザインが異なること)や無効理由を主張して争います。意匠権の有効性(新規性欠如など)も抗弁として主張でき、その場合被告側に立証責任が転換し、先行意匠の存在を証明して意匠権の無効を図ることになります。インドネシア法では利害関係人が商業裁判所に意匠登録の無効審判(取消訴訟)を提起できる規定があり、侵害訴訟の中で被告が反訴的に無効を求めることも可能です。
救済措置:権利者が裁判で勝訴した場合、主な救済として(1)差止命令(侵害行為の停止および将来の差止)、(2)損害賠償の請求が認められます。差止命令には、侵害品の製造・販売等の即時停止や在庫製品の廃棄などが含まれ得ます。またインドネシア法では仮処分的な救済も規定されており、裁判所に対し訴訟係属中に侵害品の輸入差し止めなど暫定的措置を求めることができます。損害賠償については故意・過失による侵害で生じた実損額や逸失利益等が認められます。インドネシアでは懲罰的賠償の制度はありませんが、悪質な侵害に対しては刑事罰の適用も可能です。意匠法では故意の侵害行為に対し最長4年の禁錮刑または最大3億ルピアの罰金を科す刑事罰規定を設けています。権利行使の手段として、まず民事上の差止・賠償請求を行い、悪質な場合に捜査当局へ刑事告発するケースもあります。
裁判管轄:インドネシアの知的財産権侵害訴訟は各地の商業裁判所(Commercial Court)が第一審管轄となります。被告の住所地を管轄する商業裁判所に提訴するのが原則であり、被告が国外に住所地を有する場合はジャカルタ中央商業裁判所が管轄裁判所となります。商業裁判所の手続は迅速に行われるよう定められており、提訴後すみやかに初公判日が指定され90営業日以内の判決を目指す運用がなされています。第一審判決に不服がある当事者は、直接最高裁判所に対し上告(Cassation)を提起することができます。インドネシアの商業裁判所制度では中間控訴審を置かず、知財事件は迅速に最終審まで進行する仕組みです。日本における知財高裁に相当する専門控訴審は存在しません。なお前述のとおり、第三者による登録意匠の取消訴訟も商業裁判所が管轄し、これは権利存続期間中であればいつでも提起可能です。
国際出願との関係(ハーグ協定ジュネーブ改正協定の加盟状況、国際出願の取扱い)
2025年時点で、インドネシアは意匠の国際登録制度である**ハーグ協定(ジュネーブ改正協定)**に未加盟です。そのためハーグ国際意匠出願によってインドネシアを指定することは現行ではできず、インドネシアで意匠権を取得するには日本企業であってもインドネシア知財総局への直接出願(パリ条約に基づくパリルート出願)を行う必要があります。インドネシア政府もハーグ協定への加盟準備を進めており、改正予定の意匠法にはハーグ協定1999年ジュネーブ改正協定への対応規定が盛り込まれています。新法施行後はインドネシアもハーグ協定加盟国となり、単一の国際出願でインドネシア意匠の保護を得ることが可能になる見込みです。しかし現時点では未加盟のため、外国からインドネシアへの意匠出願はパリ条約に基づく優先権主張による直接出願が唯一のルートです。
ちなみに日本は1999年ジュネーブ改正協定の締約国であり、2015年に加盟しています。日本に本拠を有する企業はハーグ国際出願制度を利用して、多数国への意匠一括出願が可能です。また日本を指定国に含む国際意匠登録も受け入れられており、日本特許庁が所定の期間内に実体審査を行い拒絶の有無を判断することになります。インドネシアが協定加盟すれば、日本企業にとってインドネシアへの意匠保護取得が容易になると期待されますが、それまでは個別出願による権利化が必要となります。
インドネシアと日本の意匠制度の比較表
最後に、インドネシアと日本の意匠制度の主な相違点を以下の表にまとめます。
| 比較項目 | インドネシアの意匠制度 | 日本の意匠制度 |
|---|---|---|
| 登録要件 |
・新規性:世界レベルでの新規性が必要(6か月のグレースピリオドあり) ・創作性:法律上明文の創作非容易性要件はないが、既存意匠と同一・類似でない独自性が要求 ・美感要件:美的外観を有すること(純粋に機能的形状のみのデザインは不可) ・産業適用性:工業製品等に具体化できること |
・新規性:世界的に新規であること(グレースピリオドは1年以内) ・創作非容易性:既存デザインから容易に創作できないこと(独創的なデザインであること)が必要 ・美感要件:美観を起こすデザインであること(機能のみの形状は不可) ・産業適用性:工業上利用可能なデザインであること |
| 出願書式 ・言語 | ・願書等は所定フォーマットにインドネシア語で記載・図面または写真(A4判、各視図に説明付記)と意匠の説明書が必要・代理人委任状、優先権書類等はインドネシア語訳を添付 | ・願書は日本語で提出(図面の注記等も日本語)※英語等外国語での出願も可だが出願後日本語訳提出が必要・図面(または写真)6面図が原則(2019年改正で厳格な6面図要件は緩和)・部分意匠出願の場合、保護部分を実線、非保護部分を破線で明確に区別 |
| 一出願当たりの意匠数 | ・1出願1意匠が原則。但し**組物(一組の物品)**として統一的なデザインであれば複数物品を一括出願可能(例:カトラリーセット等) | ・従来1出願1意匠(一意匠一出願)が原則だったが、2020年改正で一出願に複数意匠(複数Embodiment)を含めることが可能に。出願内の各意匠ごとに審査・登録が行われる |
| 審査方式 | ・方式審査後、出願公告・異議申立て制度あり(公告後3か月以内に異議可能)・実体審査:第三者異議があった場合にのみ実施(異議なき場合無審査で登録)・拒絶時:30日以内に意見書提出可。さらに不服の場合は商業裁判所に提訴可能 | ・無審査登録主義ではなく実質審査主義:方式審査後、必ず特許庁による実体審査が行われる。新規性・創作性など拒絶理由がなければ登録査定。・出願の一般公開制度は無し(非公開のまま審査され、登録時に初めて公報で公開)・拒絶査定不服:特許庁審判(不服審判)を請求可能。さらに知財高裁へ司法救済可 |
| 保護期間 | ・出願日から10年(延長・更新なし)・年金制度なし(登録料のみで10年間有効)*改正案では5年+更新2回(計15年)案も | ・出願日から25年(※2019年改正で延長)・更新制度なし(25年で終了)ただし**年次料(年金)**を毎年納付して存続させる必要あり・意匠権存続期間の延長制度なし(満了後は消滅) |
| 権利範囲 | ・登録意匠と同一またはほとんど同じデザインに及ぶ(類似範囲の明文規定はないが、実質的に同じ外観の製品は侵害と判断)・部分意匠の明確な制度はないが、破線による権利範囲の限定が可能で、実務上部分的デザインも権利化可能 | ・登録意匠と同一または類似の意匠に及ぶ(意匠法で類似意匠も権利範囲に含まれると明記)・明確な部分意匠制度あり:製品の一部も意匠登録可能(2005年導入) |
| 侵害に対する救済 | ・民事救済:差止請求(侵害行為の停止、差止)、損害賠償請求・仮処分:侵害品の輸入差し止め等を暫定的に命じる仮の救済制度あり・刑事罰:悪質な侵害には最長4年の禁錮刑等の刑事罰規定あり | ・民事救済:差止(侵害行為の差止・予防、侵害品の廃棄等)、損害賠償(通常損害に加え逸失利益推定計算や信用回復措置請求も可能)・仮処分:侵害行為の差止めの仮命令を得ることが可能・刑事罰:意匠権侵害についても10年以下の懲役刑など刑事罰規定あり(ただし適用例は少ない) |
| 管轄と手続 | ・商業裁判所が知財侵害の専門管轄(各地主要都市に設置)・被告所在地管轄が基本。被告が外国在住ならジャカルタ中央商業裁判所管轄・第一審判決→最高裁へ直接上告(迅速な二審制)・無効請求は商業裁判所に取消訴訟提起(一審制で最高裁まで) | ・地方裁判所(東京・大阪地裁等の専門部)が第一審管轄(知財高裁が控訴審)・通常は被告所在地の地裁だが、特許等と同様東京・大阪の専門部への集中管轄あり・第一審→知的財産高等裁判所(東京高裁内)→最高裁判所と三審制・無効審理は特許庁の無効審判(行政手続)、その審決を知財高裁で争う構造 |
以上のように、インドネシアの意匠制度は日本と比較して審査制度や保護期間に大きな違いがあります。特にインドネシアは無審査登録(異議がなければ登録)で保護期間が短いのに対し、日本は実体審査有りで保護期間が長く設定されています。それぞれの相違点を理解し、現地制度に合わせた戦略を立てることが重要です。
参考文献・情報源:インドネシア意匠法(Law No. 31 of 2000)および施行規則、WIPO Lexデータベース、インドネシア知的財産総局公開情報、WIPOおよびJETRO等の国際出願制度解説、日本意匠法(意匠法第3条等)及び日本特許庁・日本弁理士会解説資料。
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)