登録要件(新規性・創作性など) インドネシアで意匠(産業デザイン)として登録を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
ベトナムの意匠制度概要
ベトナムの意匠制度(工業意匠制度)は、2005年制定の知的財産法(その後の改正を含む)によって規定されており、日本の意匠権に相当する「意匠特許(industrial design patent)」として保護されます。以下では、日本企業の知財担当者や弁理士向けに、ベトナムにおける意匠制度の主要ポイントと実務上の留意点を整理しています。
登録要件(新規性・創作性・産業上の利用可能性)
ベトナムで意匠として保護を受けるには、新規性、創作性(非容易創作性)、産業上の利用可能性という3つの要件を満たす必要があります。
-
新規性: 出願日または優先日前に、世界のいかなる場所でも公に知られた同一または類似の意匠が存在しないことが求められます。具体的には、製品の使用や刊行物による記載などいかなる形で公表された意匠とも著しく異なることが必要です(知的財産法第65条1項)。他の意匠との差異が一見して識別しにくい程度であったり、意匠自体が独自性に欠ける場合には、新規性が認められず登録を受けられない点に注意が必要です。なお、「公表されていない」とみなされるための条件として、限られた者に秘密保持義務の下で知られただけの場合は公知とはみなされません。
-
創作性(非容易創作性): 出願時または優先日前に公知となっている意匠に基づいて、当業者(当該分野の平均的な知識を有する者)が容易に考案できない程度の創作的特徴を有していることが要求されます。これは日本の意匠法における創作非容易性に相当し、従来の意匠の単なる寄せ集めや模倣でない独自性が求められます。
-
産業上の利用可能性: 工業的または手工業的手段によって量産が可能であることが条件とされています。言い換えれば、その意匠に係る製品を工業的に繰り返し生産できる場合に産業上利用可能と判断されます。なお、製品の機能上必然的に決まる形状のみから成る意匠、建築物の外観、使用時に外部から見えない部分の形状は意匠として保護を受けられない旨が法律上明記されています。
以上の要件を充たせば、意匠出願は実体審査を経て登録が認められます(ベトナムは意匠について方式審査・実体審査の両方を行う審査主義です)。特に新規性・創作性については日本と類似した基準ですが、部分意匠の保護に関して相違点があります。部分意匠(製品の一部の形状のみの保護)は従来ベトナムでは認められておらず、意匠は完成品全体の外観として登録されます(図面における破線による部分的な権利主張は不可、後述)。ただし2022年改正の知的財産法では「製品または複合製品を構成する部品の外観」も工業意匠の定義に含まれると規定され、今後は複合製品の部品自体も意匠登録の対象として認められる余地が生まれています。実務上は依然として破線による非請求部分の表示は受け入れられない状況ですが、部分意匠を保護したい場合はその部分自体を単独の製品として表現するなど工夫が必要です。
出願手続(必要書類、言語、出願人資格など)
出願手続の基本フローは、日本の制度と概ね類似しており、出願(方式審査)→公開→実体審査→登録となります。出願に必要な書類・情報や手続上の留意点は以下のとおりです。
-
必要書類: 願書(所定書式)、意匠の図面または写真(後述の図面要件参照)、意匠の説明書(当該意匠の形状・模様・色彩等の説明や物品の名称を記載)、及び出願人・創作者の情報を準備します。また、パリ条約に基づく優先権を主張する場合は優先権書類が必要です。出願時に所定の出願手数料を支払い、受理されると方式審査へと進みます。
-
言語要件: 出願書類は原則ベトナム語で作成・提出する必要があります。願書や意匠説明、図面説明等はいずれもベトナム語で記載しなければなりません。ただし、委任状や優先権証明書等の添付書類はベトナム語以外でも提出可能で、必要に応じて翻訳提出を求められる仕組みです。現地代理人が用意する定型の委任状フォーマット等は英語で作成し署名提出するケースもあります(後述)。
-
出願人資格: 意匠の創作者(考案者)本人、もしくはその雇用者・依頼者(職務意匠の場合の企業など)が出願人となります。外国企業・外国人も出願可能ですが、ベトナムに居住・営業拠点を持たない外国の個人・法人は現地の知的財産代理人(弁理士など)を通じて出願する必要があります。これは現地法(知財法第89条)の定めによるもので、日本企業が直接ベトナム知財庁に出願することはできず、必ずベトナムの代理人を選任して手続きを依頼する形となります。
-
出願から登録までの流れ: 出願後、まず方式審査が行われ、不備がなければ出願から約2か月程度で官報に公開されます(出願公開)。公開から登録査定までの間、第三者は意見書を提出することができます(正式な異議制度ではなく意見申出制度)。公開後に実体審査が行われ、新規性・創作性などの登録要件が満たされていれば登録査定となります。近年の審査期間は実務上、出願から登録まで平均1~2年程度と報告されています(案件により変動)。登録時には設定登録料を納付し、意匠登録証(証明書)が発行されます。
-
優先権主張: パリ条約に基づく優先権を主張する場合、最先の出願日から6か月以内にベトナム出願を行う必要があります。優先権書類(優先出願の公報や出願受付証など)の提出期限は出願日から3か月以内で延長不可と定められています。また、優先出願人とベトナム出願人が異なる場合は、その権利承継を証明する書類(譲渡証など)の提出も必要となります。デジタルアクセスシステム(DAS)による電子優先証明の提供はベトナムでは現在利用できないため、紙の優先証明書を原本で提出する運用です。
-
その他の実務留意点: 意匠出願の区分としてロカルノ分類を用いる必要があり、願書に該当する意匠の分類(第○類○×)を記載します。もし申請人が分類を記載しなかった場合、知財庁側で分類作業が行われ、その手数料が請求されます。また一意匠一出願が原則ですが、複数の意匠が「セット商品」を構成する場合(例:ティーカップとソーサーのセット)や、「互いによく似た意匠のバリエーション(Embodiments)」である場合には、一つの出願にまとめることが許容されます。ベトナム法の定める意匠の単一性要件では、同一または類似する意匠のみを一件の出願に含めることが可能であり、例えば形状の大部分が共通し細部のみ異なるバリエーションは一出願で包括できます。一方で、ロカルノ分類が同じであっても形態が顕著に異なる複数意匠は分割が必要となりますので注意してください。
図面要件
図面(または写真)の提出要件は非常に重要で、ベトナム出願の成否に直結します。審査官にとって図面が意匠の内容を把握する唯一の手がかりとなるため、以下の基準を満たす明確な図面を用意する必要があります。
-
基本図面の種類と数: 通常は7面図を提出します。具体的には、製品の前面、背面、左側面、右側面、上面、下面および斜視図(立体図)の7つが基本とされています。斜視図を含め全方向から製品の外観を漏れなく示す必要があります。左右対称の意匠で一方の側面が他方と同一の場合や、裏表が同一の場合には、一方の図を省略することが認められています。また、大型・重量物で下面が実質的に平坦かつ通常視認されない場合には下面図を省略することも可能です。ただし省略する場合でも、意匠の要部が全ての図面で開示されていることが前提となります。
-
図面の品質と形式: 提出する図面は線が鮮明でコントラストがはっきりしたものを用意します。写真の場合は無地で均一な背景で撮影し、ディテールが見やすいようにしてください。複数の図面間でスケール(縮尺)は統一し、一貫性を保つ必要があります。図面は手描きよりもCAD等で正確に描いた線図や高解像度の写真が望ましく、審査基準に照らして不鮮明な場合は補正を求められる可能性があります。
-
部分意匠の図示: 前述のように破線(点線)による非請求部分の表示は認められていません。そのため、日本出願で部分意匠として破線表示した図面をそのままベトナムに流用すると受理されないおそれがあります。部分を保護したい場合は、その部分のみを独立した製品として描くか、実線のみで描いた上で説明書で権利範囲を明示するといった対応が必要です(例えば、「実線で示す部分が意匠登録を受けようとする部分である」等の記載)。なおベトナム知財庁は、組物(セット)意匠や複合製品の部品の意匠については、必要に応じて「製品に組み込まれた状態を示す図面(組込図)」の提出を求めることがあります。複雑な部品意匠では、その部品が最終製品のどこに使用されるか説明する補助図面を要求される場合があります。
-
追加の視図: 基本7面図で形状を十分に表現できない場合、拡大図、断面図、展開図などを追加提出することが認められています。例えばごく細部の模様や内部構造が特徴となっている意匠では、その部分の拡大図や断面図を添付することで審査官の理解を助けることができます。
-
写真提出の可否: ベトナムでは写真による提出も可能です。立体物の場合、CAD図面が用意できない場合には高品質な写真でも差し支えありません。ただし上記のとおり背景は無地とし、製品の輪郭がはっきり分かるよう調整します。提出後に審査官が図面の描き直しを指示することは基本的に無いため、最初の提出段階で完成度の高い図面を用意することが重要です。
-
2次元的意匠: 模様や色彩のパターンなど平面的な意匠(2Dデザイン)も保護対象になります。その場合は模様の展開図やパターン自体の図面を提出します。布地の模様等で繰り返しパターンの場合は、一単位分を示す図などで対応可能です。
以上のように、図面要件は厳格ですので、日本の意匠図面を流用する際もベトナム基準に適合させるよう留意してください。必要に応じて現地代理人と相談し、最適な図面構成を検討することが大切です。
新規性喪失の例外
ベトナム知財法には、出願前の公表に関する新規性喪失の例外規定が設けられています。他人による無断公表や、出願人自身による学会発表・展示会出品など、一定のケースに該当する公開であれば公開後6か月以内の出願によって新規性喪失の例外が認められます。具体的には以下の3つの状況です:
-
無断公表: 出願権者(創作者やその承継人)の同意なく第三者によって当該意匠が公開された場合。例えば、製品のデザインを盗用され出願前に勝手に公表されてしまったようなケースでは、被害救済の観点から新規性喪失の例外が適用されます。
-
学術発表: 出願権者が学会や論文など科学的報告の形で意匠を公開した場合。デザインの技術的・学術的意義を発表した場合には、新規性喪失の例外として6か月以内の出願が認められます。
-
公式展示会への出品: 出願権者がベトナム国内の国家的展示会や公式に認められた国際展示会で当該意匠を展示した場合。例えば、公的に認定された国際見本市で新製品を出展した際の公開がこれに該当します。日本の意匠制度における公表例外(いわゆる「例外期間」)とほぼ同様で、公式または公認の展示会で公開した場合に限り保護されます。
上記いずれの場合も、公開から6か月以内に出願することが条件です。この6ヶ月のグレースピリオドはパリ条約の優先期間とも同期間ですが、優先権とは別枠の国内法上の救済措置です。したがって、自己の公開から6か月以内であれば優先権主張のないベトナム直接出願でも新規性は喪失しません。なお、「公式に認められた国際展示会」の範囲など細かな点は法令上定義がありますので、該当する公開を行った場合は現地代理人に事前相談すると安心でしょう。
保護期間
ベトナムの意匠権の存続期間は最大15年です。具体的には、出願日を起点として最初の5年間が保護期間となり、さらに5年ごとの更新を2回まで可能とすることで、出願日から通算15年まで延長可能という仕組みです。この点は日本(登録日から20年・更新なし)と異なり、更新登録料の支払いによって期間延長する点が特徴です。
-
起算日: 意匠権の効力は登録日から発生しますが、その保護期間の満了日は出願日から5年経過時と定められています(知財法第93条4項)。たとえば2018年1月1日に出願し2020年1月1日に登録査定された場合でも、初回の保護期間は2023年12月31日まで(出願から5年)となります。審査に時間がかかった分、実質的な権利期間は短縮される点に留意が必要です。
-
更新手続: 初回5年の満了前に更新出願(存続期間の延長申請)を行うことで、さらに5年間の延長が認められます。更新は2回まで可能であり、1回目の更新で10年目まで、2回目の更新で15年目まで延長できます。更新手続は各保護期間の満了前6か月から受付が可能で、多少遅れても6か月以内であれば猶予期間があり、その場合は月ごとに10%の追加料金を支払うことで更新が可能です。猶予期間を過ぎると権利は消滅しますので、期限管理が重要です。
-
維持年金: ベトナムの意匠には特許のような年金制度は無く、上記更新時に所定の更新料を納付する形となります。更新しなかった場合は期間満了をもって権利消滅となり、それ以降は意匠の独占権は発生しません。
なお、2020~2024年にかけて新型コロナ対策等の理由でベトナム政府は知的財産権の手数料を一時的に減額する措置を取っていましたが、2025年1月1日以降は通常料金に戻っています(詳細は後述の減免制度の節を参照)。したがって2025年現在、意匠権の更新料も通常額となっています。長期にわたる権利維持にかかる費用も考慮して、必要な期間だけ権利を維持する戦略も検討されます。
意匠権の効力と侵害時の対応(民事・行政・刑事)
意匠権の効力として、登録意匠の権利者(意匠権者)は、登録意匠またはそれと紛らわしい意匠を無断で業として実施する第三者に対し排他的権利を有します。具体的には、登録意匠を使用した製品の製造、販売、頒布、輸出入、広告、販売の申し出、保管などの行為を権利者の許諾なく行うことを禁止できます。意匠権者は自らその意匠を実施(製造・販売等)する権利のほか、第三者に実施を許諾したり(ライセンス)、意匠権自体を譲渡したりする権利も有します。なお、権利内容や侵害判断基準については、意匠の要部の類否など日本と共通する部分も多いですが、ベトナム独自の実務も存在します。
意匠権侵害に対する救済手段として、ベトナムでは民事訴訟と行政措置の2つが主要な対応策となります(刑事罰については後述)。これは知財法第198条・第199条の定めるところで、侵害の態様・重大性に応じて民事または行政の手続を選択できます。実務上、それぞれ次のような特徴があります。
-
行政措置による対応: ベトナムの大きな特徴として、知的財産権侵害に対する行政救済制度が発達している点が挙げられます。権利者は市場管理局(Market Surveillance)や科学技術省傘下の知的財産庁査察局、または公安当局など行政執行機関に対して侵害調査・取り締まりを申し立てることができます。行政ルートでは、侵害品の差止めや差押え、在庫品の没収・廃棄、営業停止命令、違反者への過料(罰金)の賦課といった措置が期待できます。例えば悪質な模倣品が出回っている場合、行政当局による臨検や市場取締りにより迅速に差し止めることが可能です。罰金額は個人に対し最大2億5千万ドン(約1.1万USD)、法人に対し最大5億ドン(約2.2万USD)という高額の制裁も規定されています。もっとも、行政措置では**権利者への損害賠償(民事上の賠償金)を直接得ることはできません】(科された罰金は国庫に納付されます)。それでも、手続が比較的簡易で迅速(通常1~3か月で措置実行)かつ費用負担も訴訟より軽いことから、多くの意匠侵害事案は行政措置で解決されているのが実情です。特に専門の知財裁判所が未整備な現状では、熟練した行政官による取締りの方が効果的との評価もあります。
-
民事訴訟による対応: 意匠権者は民事訴訟を提起し、裁判所から侵害差止命令や損害賠償命令を得ることも可能です。民事ルートでは侵害者に対し実際の損害額に基づく賠償金の支払いを命じることができます。ベトナムの裁判所は損害額の上限を法律で定めていませんが、権利者は実際に被った損害(売上減少や逸失利益、調査費用等)を立証する必要があります。もっとも知財訴訟全般の運用は未だ発展途上であり、専門知識を持つ裁判官が少ないことや立証のハードルの高さから、訴訟で十分な成果を得るのは容易ではありません。実際、被った損害を証明できずに名目上の少額賠償しか認められないケースも多く、手間や費用の割に得られるメリットが小さいとの指摘があります。そのため権利行使手段としてはまず行政措置を検討し、必要に応じて民事訴訟を追加的に行うのが一般的です。なお、ベトナムには意匠侵害を専門に扱う知財高等裁判所のようなものは無く、各地の人民裁判所の民事部が管轄します。
-
刑事罰の適用: かつてベトナムでは悪質な知財侵害に刑事罰(罰金刑や懲役刑)を科す規定も存在しましたが、現在の刑法では意匠権侵害に対する刑事制裁規定はありません。知財法上は「重大な場合に刑事措置もありうる」と規定されていますが、2017年施行の現行刑法では特許・意匠侵害に関する罰則が削除されており、意匠権の侵害は刑事事件とはならない運用です。したがって意匠に関しては行政措置または民事訴訟のみが実効的な救済手段となります(商標や著作権の悪質侵害については依然として刑事罰適用がありえます)。もっとも、模倣品の摘発に際し公安(経済警察)が関与することもあり、ケースによっては刑事罰相当の重い処分(例えば大型の意匠侵害案件で関与者に科刑)に繋がる可能性も否定できません。2025年現在、法制度上は意匠侵害の刑事罰は無しと理解しておけばよいでしょう。
-
税関による水際取締(国境措置): ベトナムでは商標や著作権と同様、**税関に知的財産権を登録(Recordal)**し、輸入段階で侵害品を差し止める制度があります。意匠権者は税関当局に所定の申請を行い、自社の登録意匠を侵害する疑いのある商品の輸出入監視を依頼できます。税関は全国の関所にその情報を展開し、該当商品を発見した際には貨物を一時留保して権利者に通知します。その後、権利者は行政措置あるいは民事手続を進めることで正式な没収や差止めにつなげることができます。模倣品が海外から持ち込まれるケースでは有力な予防策となるため、必要に応じて活用が推奨されます。
以上のように、ベトナムで意匠権を行使する際は行政ルートの活用が中心となります。まずは現地のIP専門弁護士やコンサルタントと相談し、最適なエンフォースメント手段を選択すると良いでしょう。侵害の証拠保全や事前調査も重要なプロセスです。なお、意匠出願が公開された後、登録前であっても仮保護として一定の権利が認められる点にも留意が必要です。知財法第131条により、公開後に第三者がその意匠を商業目的で使用している場合、出願人が通知した上で権利化後に相当額の補償金を請求できる可能性があります。実務上頻繁ではありませんが、権利化前から模倣されている場合にはこの規定も検討すべきです。
国際出願(ハーグ協定との関係)
ベトナムは2019年12月30日にハーグ協定(ジュネーブ改正協定)が発効し、ハーグ国際意匠登録制度の締約国となりました。これにより、日本を含む加盟国の企業はハーグ経由でベトナムを指定し意匠出願することが可能です。国際出願とベトナム国内出願の関係や留意点について整理します。
-
ハーグ協定加盟の概要: ベトナム加入により、WIPOを通じた国際意匠出願でベトナムを指定国に加えることができます。ハーグ経由でベトナム指定出願をすると、国際登録公報での公表後、ベトナム知財庁(IP Vietnam)が審査を行います。ベトナム知財庁は原則6か月以内に拒絶の通報(通称「通知書」)を発しなければなりません。拒絶理由がない場合または意見書対応等で解消できた場合、ベトナム政府は国際登録に対する保護付与の通報を行い、そのデザインはベトナム国内で登録意匠と同等に保護されます。この6か月という短い期間制限はハーグ協定の規定によるもので、審査官が期限内に拒絶通知を出さなかった場合は自動的に保護決定があったものと見なされます。
-
ハーグ経由出願の審査対応: ベトナム指定の国際登録に拒絶通知が出た場合、出願人は通知の発送日から3か月以内に意見書や補正書を提出して応答できます。この期限は1度だけ追加3か月の延長(計6か月まで)を申請可能です。応答はベトナムの代理人を通じて行う必要があり、内容もベトナム語で提出します。拒絶理由が解消されれば、知財庁はWIPO経由で保護付与(登録査定)の通報を行います。ハーグ出願で登録となった意匠の保護期間は国際登録日から最大15年間(5年ごとの更新2回)であり、国内出願と同等です。
-
WIPO公表と国内公告: ハーグ制度ではWIPO公表(国際公報)がなされますが、ベトナム知財庁独自の国内公報には掲載されません。そのため第三者がベトナム国内公報のみを監視している場合、ハーグ経由出願は見逃される可能性があります。実務上はWIPOのデータベースで国際公表をウォッチするか、ベトナム知財庁に問い合わせて確認する必要があります。なお、第三者意見の申出もハーグ出願の場合は国内出願と同様に可能ですが、意見は参考情報として扱われるのみで正式な異議には発展しません。
-
優先権書類提出の新ルール: 重要な実務変更点として、2023年8月23日施行の政令第65号により、ハーグ出願でベトナムを指定し優先権を主張する場合、優先権証明書類をベトナム知財庁に直接提出しなければならないと規定されました。具体的には、WIPOによる国際公開日から3か月以内に、そのハーグ出願が主張する優先出願の証明書(公的な出願受付証など)を現地代理人を通じて知財庁に提出する必要があります。これはWIPOのデジタルアクセスサービス (DAS) を介した提供では認められず、**紙の原本(発行官庁の公印付)を提出する必要があります。提出にはベトナムの代理人宛の委任状(POA)**が必要で、代表者の自署があれば認証や領事確認は不要です。この新要件はWIPOから十分周知されておらず、見落としている出願人もいるため注意が必要です。期限内に適切な優先証明を提出しない場合、優先権主張が認められなくなるリスクがあります。
補足: 2023年8月施行時点で既に公開済みのハーグ出願には猶予措置があり、2023年5月23日以前に公開されたものについては追加提出不要とされています。しかしながら今後WIPOが正式にこの要件を公表した日以降は、期限厳守が求められ、3か月の提出期限を過ぎた後の補充は一切認められなくなる予定です。2024年末現在まだWIPO公表はなされておらず、経過措置的に期限後提出も受け付けていますが、いつでも正式運用が始まる可能性があるため、ハーグ出願でベトナムを指定する際は早期に優先権書類を現地提出するよう心掛けましょう。
-
ハーグ出願利用の是非: 日本企業がベトナムで意匠保護を図る場合、ハーグ経由と直接出願の二通りが使えます。利点として、ハーグは英語で一括出願でき手続簡便な点があります。一方で留意点として、上記優先権書類提出義務のように結局現地代理人の関与が必要となる場面がありうること、また拒絶対応も現地代理人を通す必要があるため、完全に代理人不要とはならない点があります。さらに、ハーグ経由の場合はベトナム側での手続状況が見えにくく、通知もWIPO経由になるためレスポンスにタイムラグが生じる恐れがあります。一方、直接出願は現地代理人とのやり取りになるものの手続の透明性や柔軟性(例えば早期審査の非公式な相談等)が期待できます。ケースバイケースですが、ベトナム単一国のみを狙うのであれば現地直接出願の方が確実とも言われています。複数国同時出願で手間を省きたい場合はハーグを検討しつつ、上記追加手続きを見落とさないようにしましょう。
減免制度・委任状要件
最後に、出願や権利維持に関する料金減免制度の有無や、手続代理に必要な委任状(POA)の要件について解説します。
-
手数料の減免制度: ベトナム知財庁では、新型コロナウイルス対策として2020年から2024年末まで意匠を含む産業財産権の各種手数料を一時的に50%減額する措置が取られていました。この措置は2024年末をもって終了し、2025年1月以降は通常の料金体系に復帰しています。しかし現在もオンライン手続に限り手数料を半額とする優遇策が別途実施されています。具体的には、2024年1月1日から2025年12月31日までの間、電子出願などオンラインで行う手続については基本手数料が50%減額されます。このオンライン減免措置は産業財産権分野全般に適用され、意匠出願や登録料の納付、更新料の支払い等にも適用があります。したがって、コスト面ではオンライン出願を活用するメリットが現在は大きいと言えます。なお、小規模事業者向けの恒久的な減免制度(例えば小規模企業割引等)はベトナムには存在しません。外国出願人だからといって追加料金が課されることもありません(代理人費用等は別として、公式料金は内国人・外国人で同一です)。費用削減の観点では、必要に応じセット意匠や類似意匠を一括出願して件数を抑えることも検討できます(同一出願内の複数意匠には追加図面料が課されますが、別々に出願するより割安です)。
-
委任状(POA)の要件: 外国企業が現地代理人を通じて手続きを行う際には委任状(Power of Attorney)の提出が求められます。ベトナム知財庁の規定では、委任状原本(現地代理人宛てに署名したもの)を提出する必要があります。公証人認証や領事認証は不要で、代表者等の自署押印のみで有効です。従来は出願日から1か月以内に委任状原本を提出する厳格な期限があり、延長も認められていませんでした。しかし2023年の改正(科学技術省の通達23号)によりこの期限が撤廃され、現在では方式審査で受理可と判断される前までに委任状を提出すればよい運用に緩和されています。つまり、出願時に委任状が間に合わなくても直ちに却下とはならず、方式審査の過程で提出すれば受理されます。ただし依然としてできるだけ早期に提出することが望ましいのは言うまでもありません。委任状を欠いたままですと知財庁から補正指令が出されますし、応答がないと不受理となる可能性もあります。また、国際出願(ハーグ)の場面でも、前述の優先権書類提出など現地代理人を介する手続きには委任状が必要です。包括委任状(General POA)を現地代理人にあらかじめ預けておくことも可能で、同じ代理人に継続して依頼する場合はその写しで対応できます。
-
その他の書類署名要件: 意匠出願や登録・更新手続では、委任状以外に場合により譲渡証明書や変更届などの書類提出が発生します。これらについても一般に認証不要で、署名原本や公証写しで足ります。複数ページにわたる書類は署名漏れ(各ページへの割印等)がないよう注意が必要です。ベトナムの官庁手続では書式や署名に厳格な面があるため、書類提出時は代理人の指示に従い慎重に準備してください。
以上、ベトナムにおける意匠制度のポイントを概説しました。最後に、上記内容を簡潔にまとめた比較表を示します。
ベトナム意匠制度の主要ポイント(比較表)
以下の表は、本稿で解説したベトナム意匠制度の主要事項を整理したものです。
| 項目 | ベトナム意匠制度の概要 |
|---|---|
| 登録要件 | 新規性、創作性(非容易創作性)、産業上の利用可能性。公知の意匠と顕著に異なることが必要。機能にのみ由来する形状等は保護対象外。 |
| 出願人資格 | 創作者本人またはその雇用主等。外国法人・個人は現地のIP代理人経由で出願必須。 |
| 必要書類・言語 | 願書(ベトナム語)、図面/写真、意匠説明書等。全書類原則ベトナム語(POAや優先証明は他言語可)。優先権主張時は証明書を3か月以内提出。 |
| 図面要件 | 原則7面図(前後左右上下+斜視)。線は明瞭・背景無地。破線による部分意匠不可。必要に応じ拡大図等追加提出可。 |
| 新規性喪失の例外 | 公開後6か月以内の出願で例外適用。無断公表、学術発表、公式展示会出品が対象。 |
| 保護期間 | 出願日から5年。更新2回可能で最長15年。更新は満了前に申請、猶予6か月(追加料)あり。 |
| 意匠権の効力 | 登録意匠と同一または類似の製品の製造・販売・輸入等を独占。権利者は実施許諾・譲渡も可。私的・実験的利用や消尽、一部先使用には権利効力及ばず(法第125条)。 |
| 侵害への対処 | 行政措置(市場管理局等による差止め・罰金)と民事訴訟が主要手段。行政ルートが迅速・多用。民事は損害賠償請求可も実効性課題。刑事罰規定は現行法になし。税関による水際差止めも利用可。 |
| 国際出願(ハーグ) | 2019年末加盟。WIPO経由でベトナム指定出願可。知財庁は6か月内に拒絶通報。拒絶時は3か月以内応答(+3か月延長可)。優先権証明の現地提出が新要件。 |
| 減免制度 | 2024年までコロナ減免実施、現在通常料金。ただし2025年末までオンライン手続料50%減額。小規模事業者向け恒久減免なし。 |
| 委任状 (POA) | 外国人出願は委任状必須。署名原本提出(認証不要)。2023年より提出期限の厳格な制限撤廃(方式審査前までに提出)。 |
出典・参考文献
-
ベトナム知的財産法(Law on Intellectual Property)および関連政省令・通達(No.65/2023/ND-CPほか)
-
INVESTIP IP LAW FIRM「Vietnam - Industrial Designs Q&A」(2021)
-
明倫国際法律事務所「ベトナムにおける知的財産権に関する法令の概要 [前編]」(2021)
-
ASL LAW(Nguyen Thi Thu)「Conditions for Industrial Design Protection in Vietnam in 2025」(2023)
-
Tilleke & Gibbins (Thomas J. Treutler et al.)「Registering Industrial Designs for Household Appliances in Vietnam...」(2023)
-
KENFOX IP & Law Office「IP Practice - Industrial Design in Vietnam」(2022)
-
KENFOX IP & Law Office「Measures To Deal With Industrial Design Infringement In Vietnam」(2021)
-
Rouse & Co. International「Patent & Design Updates from Vietnam: January 2024」(2024)
-
Rouse & Co. International「Vietnam: New regulations around priority documents for Hague Applications」(2024)
-
Lexology/INVESTIP「Update on official industrial property fees in Vietnam for 2025」(2025)
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)


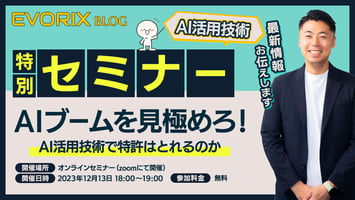
.jpg?height=200&name=unnamed%20(4).jpg)