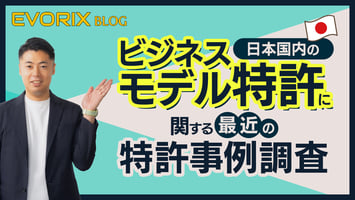...
香港における商標制度概要
1. 商標登録制度の概要(制度の特徴・主管官庁)
香港は中国本土とは独立した知的財産制度を有しており、商標法制も中国本土とは別個に運用されています。商標の登録制度は、2003年4月4日施行の「商標条例(第559章)」(及びその実施規則559A)を根拠法とし、イギリス法由来のコモンロー原則を踏襲しています(登録による権利付与が原則ですが、未登録商標でも使用による一定の保護あり)。主管官庁は香港特別行政区政府の**知識産権署(Intellectual Property Department, IPD)**で、その内部の商標登録処(Trade Marks Registry)が出願受理・審査・登録を管轄します。なお香港で商標登録を得ても中国本土では効力は及ばず、またその逆も同様です。
香港の商標制度上、商標権は登録によって取得されます(先使用のみでは権利取得不可)が、他方で使用により蓄積された営業上の信用(コモンロー上の権利)も存在し、未登録商標でも周知であれば不正競争(Passing off)で保護し得る点が特徴です。登録可能な商標は、文字・図形・記号・色彩・立体形状・音・匂い等、視覚的に表現できるあらゆる標識に及び、商品商標・サービス標章のほか団体標章、証明標章および防護標章も認められています。防護標章とは、自他商品識別機能はないものの著名商標の保護拡張のための制度で、特定の著名商標について使用していない商品類型にも登録を認めるものです(日本の防護標章制度に相当)。
出願形態の柔軟性も香港制度の特徴です。1出願で複数区分を指定できるマルチクラス出願制度を採用しており、ニース分類(第12版)に基づく商品・サービス区分に準拠しています。また、英語および中国語(繁体字)の二言語が公用語であり、出願書式や審査・登録証は英語か中国語のいずれかで手続可能です(英語での手続が外国企業には一般的)。外国からの出願人は香港内の送達先住所(通常は代理人住所)を指定する必要がありますが、現地代理人による委任状提出は不要であり、母国での事前登録も要求されません。このように香港の商標制度は、イギリス連邦系の制度を基盤としつつ、地域特性(中国語使用など)を反映したものとなっています。
2. 出願から登録までの手続きの流れ
出願および審査
商標出願は所定の願書(様式T2)に必要事項を記入し、商標図案と商品役務の区分リスト等を添えて知識産権署・商標登録処に提出します。出願はオンライン(電子出願)でも24時間受け付けており、紙出願と同額の手数料で利用可能です。願書に記載する主な情報は、(1)出願人の氏名・住所(外国人は香港内代理人住所を要記載)、(2)商標の表示(文字商標は文字列、図形等は画像ファイル)、(3)指定商品・サービスとそれぞれの国際区分、(4)優先権主張の有無などです。電子出願の場合、提出と同時に受領確認が発行されます。紙面提出では受領後に出願番号が付与され、受領通知書が送付されます。
方式審査(形式チェック): 出願を受け付けると、まず方式的要件の確認が行われます。願書の記載漏れや手数料の不足等の不備がないかを審査し、不備があれば補正通知が出されます。例えば商品区分番号の誤記等の軽微な不備であれば訂正を求める通知が送られ、2か月以内に補正すれば出願は継続します(※この場合、原出願日が維持)。一方、商標図の未提出等重大な欠陥があれば、補正後の提出日が新たな出願日とされる場合があります。定められた期間内に補正・追完できない場合、出願は却下・放棄扱いとなるので注意が必要です。
実体審査: 方式面で問題がなければ、次に実体審査が行われます。香港の審査官は、まず先行商標のサーチを実施し、同一または類似の商標が同一または類似の商品・サービスについて既に登録・出願されていないか確認します。加えて、商標そのものが法律上登録適格か(識別力を有し、記述的でなく、公序良俗に反しない等)という絶対的理由の審査を行います。審査基準の詳細は条例に定められていますが、例えば以下の点がチェックされます:
-
商標が識別力を備えているか(他人の商品・サービスと区別できるか)。ありふれた語句や産地・品質を直接表示する標章はこの要件で拒絶され得ます。
-
商標が他人の登録商標と混同のおそれがあるほど類似していないか。香港では審査官が類否判断を行い、抵触する先願があればこの段階で拒絶の通知を出します。
-
商標に不適切な要素が含まれていないか(例えば国旗・皇室の紋章、公益に反するマーク等は禁止されています)。
以上の観点から問題がなければ、審査官は登録を承認する旨の通知を出します。一方、問題がある場合には拒絶理由通知(office action)が書面で送付され、登録できない理由(例えば「○○は商品品質を直接表示するため識別力を欠く」等)が示されます。先行類似商標がある場合などは、その登録番号や詳細が通知書に引用されます。審査官は修正可能と考える場合には改善提案(例えば識別力を高めるためのディスクレーマー付加等)を示すこともあります。
拒絶理由への対応: 出願人(代理人)は、拒絶理由通知の発送日から6か月以内に応答して審査意見に対応することができます。応答期間は一度に限り3か月延長(合計9か月まで)することも可能です。応答方法としては、(1)審査官の指摘に沿って出願内容を補正する(例:指定商品を削減して先行商標との抵触を解消する、商標にディスクレーマーを付す等)、(2)意見書を提出して登録主張を行う、のいずれかまたは双方です。例えば識別力の問題であれば、使用による識別力獲得(Secondary Meaning)の証拠を提出して登録を求めることも可能です。審査官が再考し、問題が解消したと判断すれば出願は公告段階へ進みます。
審査合格~登録査定: 応答の結果、拒絶理由が解消され審査官が登録適格と判断すると、仮受理(受理通知)が出され、次の公告手続へと進みます。一方、繰り返し応答しても審査官がなお拒絶すべきと判断する場合、6か月経過時または出願人の最終応答後に最終見解が通知されます。それでも登録を希望する場合、出願人は通知日から3か月以内に審問(ヒアリング)請求を行うことができます。審問では知識産権署内の聴査官(Hearing Officer)が双方の主張・証拠を精査し、口頭審理ののちに判決(登録を認めるか否か)を下します。審問の判断に不服がある場合、出願人は高等法院(High Court)へ上訴することも可能です。
公開と異議申立て
商標が審査を通過すると、登録に先立ちその内容が**公開(公告)されます。香港では毎週基本的に香港知識産権公報(Hong Kong Intellectual Property Journal)**が発行されており、商標の出願公告もこの公報に掲載されます。公告には商標の図案、指定商品・サービス、出願人などの情報が記載され、第三者による閲覧・異議申立てに供されます。
公告日から起算して3か月間は、利害関係を有する第三者がその商標登録に異議申立てを行うことが可能です(※実務上「3か月マイナス1日」と表現されますが、概ね3か月と理解して差し支えありません。必要に応じ一度だけ2か月の延長申請も可能です)。異議を申し立てる者(異議申立人)は、所定の**異議申立通知(様式T6)**を提出し、手数料800香港ドルを納付します。異議申立書類には、当該出願を阻止したい法的根拠(例えば「申立人の先願商標に類似し紛らわしいため、登録11条違反である」等)を具体的に記載します。
商標出願の公告がなされると、該当号の公報はIPDサイト上でも閲覧できます。他人の出願に気付いた利害関係人は、この期間内に異議申立てを検討することになります。日本企業の場合、自社ブランドと類似した他人の商標が公告された場合に備え、香港公報をウォッチすることが推奨されます。
異議申立て手続: 異議申立てが提出されると、商標登録処はその写しを出願人に送付します。出願人は通知受領後3か月以内に、異議に対する答弁書(カウンターステートメント:様式T7)を提出できます。カウンターステートメントの提出には手数料はかかりません。もし期限内に答弁書を提出しなければ、出願は放棄されたものとみなされ、登録不許可となります。
答弁書提出後、異議申立人・出願人の双方に証拠提出の機会が与えられます(主張を裏付ける宣誓供述書や資料の提出)。まず異議申立人が陳述書(証拠)提出を行い、それに対して出願人が反証の提出を行い、必要に応じて申立人が再反証を提出します。証拠期間がすべて完了すると、知識産権署は**審理(ヒアリング)**の日時を指定します。ヒアリングでは双方が口頭で主張・反論を行い(代理人が法廷弁論的にプレゼンテーションを行います)、聴査官が審理後に決定を下します。異議の判断基準は、主に商標条例の登録拒絶事由(絶対的事由・相対的事由)に該当するかどうかです。聴査官の判断は書面で通知され、通常は勝訴側への訴訟費用の一部支払い(コストの償還)も命じられます。
異議申立てで出願人が敗れた場合、当該商標は登録されません。逆に申立人が敗れた場合、商標はそのまま登録査定へ進みます。なお、異議決定に不服な当事者は高等法院に上訴することができます。香港の異議手続は、日本の異議申立て制度(登録後異議)とは異なり登録前に第三者意見を募る制度です。実務上、香港では異議申立てはそれほど多くなく、大半の商標は異議なく登録に至ります(費用対効果の観点から異議申立てが乱発されない傾向があります)。
登録(登録証の発行)
公告期間を経て、異議申立てがなされなかった場合、または異議が申し立てられたものの最終的に出願人が勝訴した場合、商標は**登録(Registration)となります。登録処は商標を登録簿(Register)に記載し、正式な登録証(Certificate of Registration)**を発行します。登録証は出願言語(英語or中国語)で電子的に交付され(希望すれば紙でも受領可)、登録の事実は再度公報に公告されます。
香港の商標権は、出願日を基準として発生します。すなわち登録された商標権は、その効力が出願日に遡って発生するため、出願から登録までの間に他者がその商標を使用していた場合でも、登録後は出願日に遡って差止めや損害賠償請求の対象となり得ます。この点は日本と同様です。
商標登録が完了すると、登録原簿への記載内容(商標、権利者、指定商品/役務など)が公開され、第三者は誰がどのような商標権を有しているかを確認できます。権利者は登録商標について、指定商品・サービスに関する専用権を取得し、無断使用に対する差止めや損害賠償請求を行う法的権限を得ます(詳細は後述)。なお、順調にいった案件では出願から登録まで約6か月程度で完了することもあります。平均的には9~12か月ほどかかるのが通常で、審査での応答や異議が生じればさらに長期化します。
3. 登録にかかる費用および期間
-
出願時の公式費用: 香港商標出願の公式手数料は区分数に応じた定額制です。1区分までの基本料金が2,000香港ドルで、2区分目以降は1区分追加ごとに1,000香港ドルが加算されます。これは通常の商標(個人・法人の商標、団体標章、証明標章)に適用される料金です。なお、前述の防護標章については出願料がやや高額で、基本2,300香港ドル+追加区分1区分ごとに1,150香港ドルとなっています。これらの費用は出願時に一括して支払います。公告料や登録料は不要であり、追加の公式費用なく登録証の発行まで完了します(出願料に登録までの処理費用が含まれている形です)。
-
審査・登録までの所要期間: 新規出願から登録査定・証明書発行までの期間は、案件の状況によって変動します。前述のように、順調なケースでは6か月程度での登録も可能ですが、一般には約9か月~1年前後を要します。知識産権署によれば、第一次審査結果(審査意見)の通知は平均2か月程度で発せられています。その後、拒絶理由がなければそのまま公告・登録へ進みますが、何らかの拒絶理由対応で応答期間をフルに使えば数か月の遅延となります。また、公告後に異議申立てが入った場合、異議手続だけで1年以上かかることも珍しくなく、裁判所への上訴があればさらに長期化します。したがって、新ブランドの香港投入時期が決まっている場合は、少なくとも1年前には出願しておくことが望ましいと言えます。
-
代理人費用等: 外国企業が香港に出願する場合、通常は現地の商標代理人や法律事務所に依頼します。その際の代理人手数料は事務所やサービス内容によって様々ですが、出願から登録まで一括で依頼する料金体系が一般的です。日本企業向けには、日本国内の特許事務所と提携して手続きを進めるケースもあります。香港出願では委任状の提出義務がないため、日本から代理指示を出す際の煩雑さは比較的少ないです。出願後に拒絶理由への対応や証拠提出が必要になった場合、それらの追加対応費用が発生します。また、異議申立てや無効審判など紛争となった場合は、別途の手続費用・弁護士費用が高額になる可能性があります。
-
その他の公式費用: 登録後の異議申立てにかかる費用としては、異議申立人が支払う800香港ドル(様式T6の提出料)があります。異議を受けた側の出願人が答弁書を出す際の費用は無料です。無効審判・取消審判等(後述)を請求する場合も、請求人は1件あたり800香港ドルの手数料が必要です。更新登録の費用については次節で述べます。
(参考)香港は2024年より電子証明書の発行を開始し、電子媒体での商標登録証交付に移行しています。電子証明書発行への移行に伴い手数料の変更はありませんが、権利者にとって登録証の受領が迅速になるメリットがあります。
4. 商標の使用義務と更新制度
-
商標の使用義務: 香港では、商標は実際に使用する意思をもって出願・登録することが求められます(出願時点で未使用でも構いませんが、登録後は使用していく予定であることが前提)。そして、登録商標は登録後3年以上香港で不使用の場合、利害関係人からその登録を取り消される(権利を喪失する)おそれがあります。具体的には、ある商標が登録された日から3年間連続して香港で真正な使用(genuine use)がされていない場合、第三者は**不使用による取り消し(revocation for non-use)**を知識産権署に申立てることができます。この「3年」は香港における商標権の実際の登録日(=出願日)から起算されます。正当な理由なく3年間使われなかった商標は、いわば休眠商標として市場から排除される仕組みです。
ただし、取消しを避ける猶予措置もあります。3年の不使用期間が経過した後でも、第三者に取消しを請求される前に使用を開始または再開していれば、原則として取消しは認められません。一方で、取消し請求を見越して慌てて使い始めたような場合(例えば3年不使用期間終了後、取消し請求が来そうだと知ってから3か月以内に使用を再開した場合)には、その再開使用は考慮されず取消しが認められてしまうという規定もあります。これは権利維持のための駆け込み的な使用を防ぐためのルールです。以上を踏まえ、香港で商標登録を取得したら、少なくとも3年以内には現地で商標の使用を開始・継続することが肝要です。正当な理由なく長期間放置すれば、第三者から権利を奪われるリスクがあります。
※「正当な理由」としては、例えば輸入規制や不可抗力で使用できなかった場合などが考慮され得ますが、ハードルは高いです。また、使用には香港域内での実際の商取引における商標の表示が必要で、単なる登録維持目的の象徴的な使用(token use)は認められません。
-
商標権の存続期間: 登録商標の存続期間は出願日から起算して10年間です(香港条例上は「登録日から10年」と規定されていますが、登録日=出願日と扱われるため実質的に出願日基点です)。例えば2025年7月1日に出願し2026年1月1日に登録査定がおりたケースでも、2025年7月1日から2035年6月30日までが1期目の登録期間となります。登録から10年目以降も商標を保護したい場合は更新登録の手続を行うことで、10年ごとに権利を延長できます。更新の回数に制限はなく、理論上は永続的に権利を維持することも可能です。
-
更新手続と費用: 商標の有効期限が近づくと、知識産権署から権利者あてに更新期限のお知らせが郵送されます。通常、有効期限の約6か月前に通知が届きます。更新を希望する場合、期限までに**更新申請(様式T8)**を提出し、所定の更新料を納付します。更新料は、1商標につき2,670香港ドル(1区分)で、2区分目以降は1区分ごとに1,340香港ドルが加算されます。例えば3区分の商標を更新する場合、2,670 + 1,340×2 = 5,350香港ドルとなります。
更新申請は有効期限の1年前から受付可能で、期限日までに手続すれば問題ありません。もし期限までに更新できなかった場合でも、救済措置があります。香港では期限後6か月間の猶予期間が設けられており、この期間内であれば追加の延滞料金(500香港ドル)を支払うことで遅れて更新することが可能です。したがって最長で期限から6か月遅れまで更新可能ですが、延滞料金が発生するため可能な限り期限内更新が望ましいです。
猶予期間(延長6か月)を過ぎても更新されなかった場合、その商標は登録抹消(権利抹消)となり、商標登録原簿から削除されます。しかしそれでも完全に権利喪失ではなく、更に6か月以内であれば登録復活(Restoration)の申請が可能です。復活には復活料4,000香港ドル(+通常の更新料)が必要で、期間を過ぎると復活も認められず商標権は消滅します。復活が認められた場合は、公報に復活告示が掲載され、権利が回復します。
-
使用宣誓の不要: アメリカなどと異なり、香港では更新時に使用宣誓書(Declaration of Use)等を提出する必要はありません。更新料さえ払えば形式上は権利を維持できます。ただし上述のように、実体的には不使用で放置すれば第三者から取消しを請求され得ますので、維持には実質的な使用が伴っていることが重要です。更新申請の審査自体は形式的なものなので、更新処理は比較的迅速に完了します。
5. 国際出願(マドリッド・プロトコル)との関係と利用可能性
-
現状(2025年時点): 香港は現時点でマドリッド協定議定書(Madrid Protocol)による国際商標出願制度に加入していません。そのため、日本企業が香港で商標保護を得るには、香港へ直接国内出願する以外に方法がありません。例えば、日本で国際登録出願(マドリッド出願)を行っても、現行では香港を指定国に加えることはできませんし、また中国本土をマドリッド指定しても香港には効力が及びません(香港は中国とは別の独立関税地域・法域として扱われます)。これは香港が独立のWIPO加盟地域ではない(中国の一部である)ためですが、特例的にパリ条約やTRIPS協定の義務は中国を通じて適用されています。その一環で国際商標制度についても、長らく香港政府はマドリッド制度参加の検討を進めてきました。
-
マドリッド制度導入の動き: 香港特別行政区政府は、マドリッドプロトコルの香港への適用に向けた法整備と実務準備を進めています。2014年に一度パブリックコメントを実施した後、2020年6月19日に**「2020年商標(改正)条例」**が官報公布され、マドリッド協定議定書実施のための枠組みが整えられました。この改正条例により、国際商標登録に関する規則制定やシステム構築を行える権限が付与され、現在までに:
-
実務規則の整備: 国際出願に対応するための細則や手続規定の策定(提出書類フォーマット、手数料、処理期間等)が準備されています。
-
電子システム対応: マドリッド出願を受理・処理するための専用ITシステムの開発が進められています。
-
中央政府との調整: 中国中央政府の承認を経て、香港でのマドリッド協定議定書の適用についてWIPOに通知するプロセスが取られています(香港自身は締約国になれないため、中国による締約拡張という形をとります)。
政府発表によれば、2025年までに香港でマドリッドプロトコルを運用開始することを目標としています。つまり、早ければ2025年中にも香港をマドリッド経由で指定できるようになる見通しです。実現すれば、香港は世界100以上の国・地域が参加するマドリッドシステムの一員となり、香港での商標保護取得・管理が格段に容易になります。
-
-
マドリッド導入後の利用想定: 香港がマドリッドプロトコル下で指定可能になった場合、日本企業・弁理士にとっていくつかの利点・留意点があります。
-
香港を含む一括出願: 日本の基礎出願/登録に基づきマドリッド国際出願を行う際、将来は香港も指定国に加えることができます。従来は中国本土と香港にそれぞれ別出願が必要でしたが、一度の国際出願で両者をカバーできるようになります。ただし、中国本土と香港は審査機関が別々であるため、それぞれ独立に審査・拒絶の判断が下されます。
-
香港発の国際出願: 香港の商標権者(香港に実営業拠点がある企業など)は、香港を官庁(Office of Origin)としてマドリッド国際出願を提出できるようになります。香港から海外へのブランド展開を図る地元企業にとって、マドリッド加入はコスト削減と手続簡素化のメリットが大きいと期待されています。
-
指定後の手続: 国際登録で香港を指定した場合でも、香港知識産権署が従来どおり審査を行います。審査期間(国際登録日から18か月以内)に拒絶通報がなされなければ保護が認められます。拒絶理由への対応も現地代理人を通じて行うことになる点は、従来の国内出願と同様です。また、登録後の異議申立てや取消審判も通常通り行われます。国際登録であっても、香港で与えられる権利内容・効力は国内出願で得た場合と同一です。
-
費用面: マドリッド経由の場合、香港を指定する際にはWIPOに支払う個別手数料(香港の設定額)を納付することになります。香港政府は適用時に手数料額を告知するはずですが、概ね現行の国内出願費用水準を反映した額になると見込まれます。いずれにせよ、複数国への出願を別々に行うより国際登録による一括管理のメリットが上回るでしょう。
-
-
現時点での対応: 以上のように香港でのマドリッド利用開始が近づいていますが、2025年現在ではまだ利用不可です。そのため、日本企業が差し迫って香港に出願する必要がある場合は、待たずに香港への直接出願を行うべきです。一方で、例えば2025年後半以降にブランド展開予定で時間に余裕があるなら、マドリッド制度開始を待って国際出願する選択肢も視野に入ります。最新情報については香港知識産権署やWIPOからの発表を随時確認し、制度開始時期にあわせて適切な出願戦略を立てることが重要です。
6. 商標権の行使(侵害対応、差止請求、損害賠償)
-
民事的救済(侵害訴訟): 香港で商標権を侵害された場合、権利者は民事訴訟により救済を図ることができます。商標権侵害とは、登録商標と同一もしくは紛らわしいほど類似した商標を、登録商標の指定商品・役務と同一または類似の範囲で無許可で使用する行為を指します。侵害が疑われる場合、まず権利者は差止めの警告書を送付することが多いですが、任意の停止が得られなければ**高等法院(高等裁判所)**において侵害訴訟を提起します。
訴訟で商標権侵害が認められた場合、香港の裁判所は以下のような救済命令を発します:
-
差止命令(Injunction): 被告(侵害者)に対し、侵害行為の停止を命じる裁判所命令です。現在侵害行為が継続している場合、仮処分(臨時差止命令)として速やかに発令されることもあります。最終的に勝訴すれば恒久的な差止命令(恒久禁止命令)が出され、侵害行為を将来にわたり禁止できます。
-
損害賠償(Damages): 侵害によって被った経済的損失の賠償金支払いを侵害者に命じるものです。損害額の立証には、侵害による売上減少やライセンス料相当額等を算定して示す必要があります。香港では懲罰的賠償は通常ありませんが、悪質な侵害では高額の賠償が認められる場合もあります。
-
利益の移転(Account of Profits): 損害額に代えて、侵害者が侵害行為によって得た利益の全額または一部を権利者に移転させる救済です。裁判所はケースによって損害賠償とアカウント・オブ・プロフィッツのいずれか適切な方を選択します。権利者は両方を同時に得ることはできませんが、利益額の方が損害額より大きい場合はこちらが選択されることがあります。
-
訴訟費用の命令: 勝訴した権利者は、弁護士費用や裁判費用の一部について敗訴者からの償還を受けられることが一般的です(香港は英米法系のコスト原則採用のため)。
-
その他の救済: 必要に応じて、侵害品・偽造品の廃棄命令や、将来の違反行為に対する声明広告命令等が出されることもあります。
香港の裁判制度では、当事者は英語または中国語のいずれかを手続言語として選択できます。多国籍企業の事件では英語で行われることが多く、証拠書類も英語翻訳を用意すれば提出可能です。裁判所にはIP案件に通じた裁判官もおり、商標侵害に対する救済は比較的迅速かつ実効的に得られると評価されています。
-
-
刑事的取締り(模倣品対策): 商標権侵害のうち、偽造商標を付した商品(模倣品)の製造・販売は香港では刑事犯罪となり得ます。香港政府の税関(Customs and Excise Department, C&ED)は、商標権および著作権の刑事執行を担当する機関であり、模倣品の取締りや水際措置を実施しています。例えば、有名ブランドの偽物を大量販売している店舗があれば、権利者の情報提供に基づき税関が捜索令状を取得して強制捜査・差押えを行い、違反者を起訴します。発覚した商標法違反(商品説明等条例違反など)の刑罰は高額な罰金刑や懲役刑が科される可能性があり、これが抑止力となっています。
権利者は税関に対して自社商標の保護依頼(通報)を行うことができます。また香港税関は海外の法執行機関や権利者とも協力しており、国際的な模倣品摘発にも積極的です。香港はWTOのTRIPS協定加盟地域として、**国境措置(Border Enforcement)の義務も負っています。具体的には、税関に商標を登録(Recordation)**しておくことで、輸出入時に疑わしい貨物を差し止めてもらう制度があります。香港は貿易港でもあるため、この水際取締り制度は模倣品流通の抑止に役立っています。
-
コモンロー上の救済(Passing Off): なお、香港には**営業上の信用棄損(Passing off)**に基づく救済もあります。これは登録の有無にかかわらず、他人の商品・営業表示を真似て顧客を混同させる行為について、不正競争行為として差止めや損害賠償を求められるものです。未登録商標でも、香港市場で周知であればこのPassing Offで保護可能です。典型的には、著名ブランドの名前や包装を真似た商品に対し、商標権侵害とあわせて予備的にPassing Offも主張する、といった形で用いられます。勝訴すれば救済内容は商標侵害とほぼ同じですが、立証負担が重いため通常は登録商標を有している方が有利です。
[補足] 香港で商標権を行使する場合、日本と比べ強制力のある証拠収集手段(開示命令やアントンピラー命令など)が充実しています。必要に応じ、裁判所に申請して侵害の証拠を相手方の施設から差し押さえることも可能です。また、差止命令違反に対しては法廷侮辱罪が適用され、経営者個人に対する制裁もあり得るため、命令の遵守率も高いと言われます。総じて、香港は知的財産権の司法的執行がしやすい法域であり、侵害発生時には民事・刑事両面から迅速に対処することが肝要です。
7. 無効審判・取消審判等の制度
香港では、登録査定後の商標について、その登録の効力を争ったり取り消したりするための事後的な救済手段も整備されています。日本の「無効審判」「取消審判」に相当する制度があり、第三者または政府当局が一定の事由で登録を無効化・取消すべく手続きをとることが可能です。これらの手続はまず知識産権署の**商標登録処(Registrar of Trade Marks)**に申立てを行い、その決定に不服なら高等法院へ上訴する仕組みです。
-
登録無効(無効宣言 / Invalidation): 登録商標が本来であれば登録されるべきでなかった場合(=登録時に拒絶理由があったのに見逃されていた等)、無効審判(無効宣言の申立て)によってその登録を遡及的に無効にできます。申立権者は利害関係人であれば足り、典型的には「先願・先登録商標を有する者」や「著名表示の所有者」などが該当します。無効事由として主張できるのは、商標条例第53条に定められる内容で、日本の無効審判における絶対的無効事由・相対的無効事由に対応します。具体的には:
-
絶対的事由: 登録商標が識別力を欠いていた、記述的であった、その他公序良俗に反していた等。例えば全く特徴のない地理的名称だけの商標や、一般的商品名そのものを登録していた場合などが該当します。
-
相対的事由: 登録商標が他人の先般の権利と紛/conflictしていた場合です。典型例は、ある登録商標が実は他社の先登録商標と類似しており、本来拒絶されるべきだったケースです。また、他人の著名商標の希釈化を目的とした不正な出願(悪意の出願)の場合も無効事由となり得ます。
無効申立てはForm T6で行い、1件ごとに800香港ドルの申立料がかかります。申立書には無効理由と事実関係を詳細に記載し、必要に応じ証拠も添付します。被請求人(登録商標権者)は、通知を受け取ってから6か月以内に答弁書(Counter-statement)を提出して防御できます。答弁しない場合、そのまま無効が認められる可能性が高くなります。答弁がある場合、申立人・被請求人双方に証拠提出や反論の機会が与えられ、最終的に聴査官による審理・決定となります。
無効理由の時限: 無効事由のうち相対的事由(他人の先権利との抵触)については、一定期間内に申し立てる必要があります。香港法はEUなどと同様、権利不行使による**黙示の容認(acquiescence)**の規定があり、5年以上平穏に使用されている登録商標に対して、特定の条件下では先権者が無効を主張できなくなる可能性があります。具体的には、先権者が後から登録された類似商標の存在を知りながら5年間以上使用を容認した場合などが該当します。ただし悪意で登録された商標や、公序良俗違反の商標については時間の経過に関係なく無効主張可能です。また絶対的事由に基づく無効(例: 著しく記述的だった等)は期間制限なくいつでも申し立て可能です。
無効の申立てが認められると、その商標登録は初日(出願日)に遡って無効となったものと扱われます。つまり初めから権利が存在しなかったのと同じ状態になり、権利者は既に得ていた独占権や差止請求権を失います。
-
-
登録の取消し(Revocation): 取消審判に相当する制度で、登録商標が登録後に発生した事情により取り消し対象となる場合に適用されます。主な取消事由は以下の通りです。
-
不使用取消し: 上述したとおり、登録商標が連続3年間香港で使用されていない場合、第三者はその商標登録の取消しを請求できます。この不使用取消しは最も典型的なケースで、請求人は商標登録処に不使用の事実を示して取消申立て(Form T6)を行います。申立料は800香港ドルです。被請求人(商標権者)は通知後6か月以内に答弁書を提出し、使用実績または不使用の正当理由を示す必要があります。使用の事実は売上資料、広告資料、出荷記録などで立証します。答弁がなかったり、立証が不十分な場合、商標は全部または一部取消し(指定商品の一部について取消しも可能です)となります。取消しが認められると、その決定日以降について商標権が消滅します(遡及効はありません)。
-
商標の普通名称化: 商標がその商品の普通名称(一般名称)になってしまった場合も取消事由となります。例えば、登録商標が消費者の間で特定商品そのものを指す言葉として定着してしまい、もはや識別標識として機能しなくなった場合などです。これは商標権者の不作為(適切にブランドを管理しなかった等)が原因で生じるものですが、この場合も第三者が取消しを申立てることができます。
-
使用による誤認・非品質化: 商標の使用方法が原因で、登録商標が商品・サービスの品質や産地について公衆を欺くおそれが生じた場合や、登録時の条件に違反した場合も取消し得ます。例えば、品質を保証する目的の証明標章なのに適切に管理されず粗悪品にも使われている、といったケースが該当します。
-
防護標章の取消し: 防護標章については、該当商標がもはや著名ではなくなった場合等には取り消される可能性があります。防護標章は不使用でも維持できますが、その前提であった高名性が失われたと第三者から指摘されれば取消し得ると解されています。
取消し申立て手続は、不使用取消しを含め無効申立てとほぼ同様で、Form T6で行い手数料は800香港ドル、権利者は6か月以内に答弁して争う流れです。審理・決定も商標登録処内で行われます。取消しが認められれば、対象商標登録は将来に向かって効力を失います(決定日以前の期間は有効だったが、以後消滅)。決定には不服申立(高等法院への上訴)が可能です。
-
-
その他の手続: 上記のほか、登録簿の訂正(Rectification)や登録の分割・譲渡など、登録後の各種管理手続もあります。Rectification(登録の訂正)は、登録記録に誤記がある場合や、登録内容に変更が必要な場合に申請できます。例えば登録人の住所の誤字等は通常届出で簡易に訂正できますが、権利範囲に関わる訂正は利害関係人との争いになることもあります。また、権利の分割(一つの登録を区分ごとに分割する)や部分抹消(指定商品・役務の一部について権利を放棄する)、権利の譲渡・ライセンス登録(第三者への移転やライセンス契約の登録)などの制度も整えられています。これらは権利者側から届出・申請する手続で、必要に応じて知識産権署に所定のフォーム(T5/T10/T11等)を提出します。たとえば商標の譲渡(権利移転)を行った場合、登録名義人の変更を届け出て登録簿に反映させる必要があります。
以上のように、香港でも登録後の商標をクリアにする仕組みがあり、正当な理由のない権利占有や、権利の形骸化を防ぐようになっています。日本の審判制度と概念は似ていますが、審理はまず行政庁(知識産権署)の範囲で完結し、裁判所は上訴審として関与する点が異なります。実務上は、競合他社の休眠商標が障害となる場合に不使用取消しを利用したり、自社ブランドに酷似する商標登録が存在する場合に無効申立てを検討するといった対応が取られます。なお、異議申立てと同様に、無効・取消しの審決情報も知識産権署の公報や公式ウェブサイトで公開されています。判例・先例の蓄積もありますので、ケースに応じて専門家が適切な戦略を立てることが求められます。
8. 実務上の留意点(審査傾向、先使用、言語等)
香港での商標出願・権利行使にあたり、以下のポイントに留意すると良いでしょう。
-
審査基準・傾向: 香港商標登録の審査では、絶対的要件(識別力など)および相対的要件(先行商標との抵触)の両面で厳格なチェックが行われます。特に絶対的要件について、審査官は日本以上に記述的商標にシビアとの指摘があります。例えば商品やサービスの質・効能・用途・産地等を表すにすぎない語句、業界で日常的に使われる慣用語、シンプルな図形やありふれた標章は、まず登録は困難です。一方、造語や任意の語の組み合わせであれば比較的登録に適しています。また香港では審査段階で類否の判断が行われるため、出願前に競合他社の商標を十分調査し、クリアランスをしておく必要があります。知識産権署はオンラインで商標データベースを提供しており、無料で誰でも検索が可能です。専門家による調査や、公式の予備調査サービス(様式T1での登録可能性見解取得)の活用も検討すると良いでしょう。
-
未登録商標の保護(先使用権): 前述の通り、香港では未登録でも使用による信用が築かれていれば法的保護が認められる場合があります。これは特にPassing Off(信用棄損)の法理で、先に商標を使用して顧客層に周知性を確立している事業者は、後から同じ・類似商標を登録した他者に対し、権利行使や登録取消しを求めることができます。従って、香港展開を考える日本企業は、自社ブランドが現地で第三者に無断使用されていないか常に注意が必要です。また、自社が長年香港市場で使ってきた未登録のブランドがある場合、早期に出願して公式な権利を確保することが重要です。香港は先願主義ですが、上記のように先使用による一定の保護もあり得るため、早めの出願で紛争を予防する戦略が推奨されます。万一、他人に先に登録されてしまった場合でも、諦めずに無効申立てで取り戻せる可能性はありますが、その際には香港市場での使用実績や周知性を証明する多くのエビデンスが必要となります。
-
言語・商標の現地表記: 香港は英語と中国語(繁体字)が公用語の社会です。商標の出願自体は英語・中国語どちらでも可能ですが、現地でのブランド浸透という観点では中国語名の検討も不可欠です。香港の消費者は欧米系・日本系ブランドでも独自の漢字名で呼称することが多く、たとえば「Canon(キヤノン)」は「佳能(カイノン)」、無印良品は「無印良品(ムーピンヨウヒン)」といった具合です。もし日本企業側で公式の漢字商標を用意しないと、代理店やメディアが勝手に命名してしまうこともあります。そうなると第三者にその漢字名を出願・登録されるリスクも生じます。従って、英語名だけでなく対応する中国語名もセットで商標登録しておくと安心です。香港で漢字商標を出願する際は、繁体字で登録する点に注意してください(中国本土のような簡体字登録はかえって不自然です)。なお、審査官は英語商標と漢字商標の類否について、発音・観念面も含め幅広く考慮します。特に有名商標の翻訳・翻案は類似と見做される可能性があります。例えば「LION」の商標を出願すると、中国語で「獅子」に相当する既存商標とコンセプトが近いとして引用される、といったケースも考えられます。このようにバイリンガル環境特有の留意点があるため、出願戦略立案時には現地語への翻訳・類義語も検討に入れることが望ましいです。
-
その他実務上のポイント:
-
マルチクラス出願の活用: 香港では一件の出願で複数クラスを指定できます。関連商品や役務をまとめて権利化できるため、費用対効果が高いです。ただし広範なクラスを指定しすぎると不使用取消しリスクも増えるため、将来的に使用予定の範囲に絞るのが無難です。
-
シリーズ商標: 類似したバリエーション違いの商標を一括出願するシリーズ商標制度があります。例えば色違いのロゴや、語順を入れ替えただけのスローガンなどはシリーズとしてまとめて登録可能です。シリーズ登録された商標は、構成要素の差異がごくわずかな場合に認められます。日本にはない制度なので有効活用を検討してください。
-
防護標章: 前述の防護標章制度は、ブランド拡張戦略として覚えておく価値があります。香港市場で著名な商標をお持ちの場合、現時点で使用していないクラスについても防護標章として登録することで、他社による異分野での商標登録を牽制できます。ただし、防護標章は取得要件が厳しく、対象商標の著名性を証明する必要があります。また、著名性が低下すれば取消されるリスクもあるため、取得・維持には専門的判断が求められます。
-
電子出願と電子証明: 香港知識産権署は電子化が進んでおり、オンライン出願や電子通知に対応しています。2024年からは電子登録証の発行も開始されました。ユーザー登録すれば出願経過もオンラインで追跡できるため、最新技術を積極的に活用すると効率的です。
-
他地域との相違: 香港・中国本土・マカオはそれぞれ商標制度が異なります。例えば、中国本土では審査で相対的要件も見る点は共通しますが、指定商品類似の判断基準(類似群コード運用)や、異議申立てのタイミング(中国は登録前と後の二本立て)など手続が異なります。マカオは単一クラス出願制で、ポルトガル語・中国語が公用語です。香港への出願戦略を立てる際は、他地域での商標戦略とも整合させ、必要に応じ各地域での権利取得を検討してください。
-
商標ブロッカー対策: 香港は中国本土に比べれば商標ブロッカー(商標の先取り屋)の問題は大きくありませんが、全く皆無ではありません。特に中国本土で知られている日本ブランドは、香港やマカオでも第三者が投機的に出願している例があります。香港における自社商標の権利状況についても、中国本土同様に早めの出願と定期的なモニタリングを行い、権利の死角を作らないことが大切です。もし第三者に先に出願・登録された場合でも、悪意の立証や不使用立証によって排除できる可能性はありますが、訴訟コスト・時間がかかるため予防が最善です。
-
以上、香港の商標制度について、香港知識産権署の公式情報等に基づき主要ポイントを解説しました。香港は一国二制度の下で中国本土とは異なる知財環境を維持しており、法制度も英国由来の枠組みを踏襲しています。そのため日本や中国本土と共通する部分と独自の部分が混在しています。日本企業が香港で商標戦略を立てる際は、上記の点に留意し、必要に応じ現地の知財専門家とも連携して対応することをお勧めします。
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)